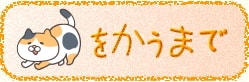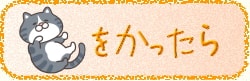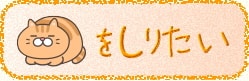猫の歯の本数と種類
1歳を超えた成猫の永久歯は30本からなります。犬の永久歯42本に比べるとずいぶん少ない本数ですが、猫の頭蓋骨はかなり小さいため、あまりたくさんの歯を詰め込むことができないのです。
成猫の歯の本数と役割
生後5~6ヶ月で生え揃う30本の永久歯の各部名称と主な役割は下図です。


- 犬歯(牙)✓本数=上2+下2=4本
✓役割=獲物の首筋に食い込ませて脊髄を切断する - 門歯(切歯)✓本数=上6+下6=12本
✓役割=肉を噛みちぎる・骨から削ぎ落とす - 前臼歯✓本数=上6+下4=10本
✓役割=肉や猫草を噛み切る - 後臼歯✓本数=上2+下2=4本
✓役割=肉を噛み切る・硬いものを噛み砕く
犬歯の特徴・役割
合計30本ある永久歯の中でも、上下合わせて4本ある犬歯(けんし, canine tooth)は獲物を捕らえるときに役立ちます。この歯は横幅が広いため、ちょうど「くさび」としての機能を果たします。この「くさび」を獲物の首筋にグサリと刺し込むと、うまい具合に脊髄(せきずい)に当たり、効率的に切断することができるのです。脊髄とは、背骨の中を通っている神経線維の束で、これを切断された動物は即死してしまいます。
なお犬歯の根元には特殊なセンサーがあり、獲物の脊髄を正確に噛み切れるよう、歯の方向を微調整していると言われています。また犬歯の表面にある小さな溝は「血溝」(bleeding groove)と呼ばれるもので、獲物から流れ出た血が歯に付着しないよう、効率的に流す下水溝のようなものだと考えられています。ただし猫のものは、ライオンのキバで見られるほど明瞭ではありません。

なお犬歯の根元には特殊なセンサーがあり、獲物の脊髄を正確に噛み切れるよう、歯の方向を微調整していると言われています。また犬歯の表面にある小さな溝は「血溝」(bleeding groove)と呼ばれるもので、獲物から流れ出た血が歯に付着しないよう、効率的に流す下水溝のようなものだと考えられています。ただし猫のものは、ライオンのキバで見られるほど明瞭ではありません。
門歯(切歯)の特徴・役割
門歯(もんし)は切歯(せっし)とも呼ばれ、上下とも6本ずつあります。この歯の裏にはヤコブソン器官の入り口があり、フレーメンによって大きく開き、フェロモンを取り込みやすくします。またグルーミングの際は櫛(くし)のような働きをします。猫が前足や後ろ足の爪をガジガジと噛んでいることがありますが、この時の門歯の役割はグリップです。
臼歯の特徴・役割
一般的に「奥歯」と呼ばれている臼歯(きゅうし)は、「前臼歯」と「後臼歯」に分かれています。
 しかしこれらは、私たちの奥歯のように上の歯と下の歯の面がピッタリとかみ合いません。猫の臼歯は先端がとがっており、なおかつ上下の歯が前後で微妙にずれた構造になっているため、ちょうど肉切りバサミのような役割を果たします。これは猫が肉を噛みちぎることに特化した構造の歯を発達させた結果で「裂肉歯」(carnassial)などとも呼ばれます。肉だけでなく、猫草をおいしそうにシャリシャリ噛みちぎる時に用いているのもこの歯です。ちなみに上顎の「後臼歯」はほとんどお情け程度にしかついておらず、ほとんど見分けることができません。
しかしこれらは、私たちの奥歯のように上の歯と下の歯の面がピッタリとかみ合いません。猫の臼歯は先端がとがっており、なおかつ上下の歯が前後で微妙にずれた構造になっているため、ちょうど肉切りバサミのような役割を果たします。これは猫が肉を噛みちぎることに特化した構造の歯を発達させた結果で「裂肉歯」(carnassial)などとも呼ばれます。肉だけでなく、猫草をおいしそうにシャリシャリ噛みちぎる時に用いているのもこの歯です。ちなみに上顎の「後臼歯」はほとんどお情け程度にしかついておらず、ほとんど見分けることができません。
 上の図で示したように、口を開けたり閉じたりする時に働く筋肉は「咀嚼筋」(そしゃくきん)と呼ばれます。口を閉じるときに働く筋肉は側頭筋(T)、咬筋(M)、内側と外側翼突筋(P)。逆に口を開けるときに働く筋肉は顎二腹筋(D)です(Kim, 2018)。これらの筋肉によって生み出される力は、犬歯で7.5kg(73.3N)、裂肉歯で12kg(118N)程度と推計されています。ただしこれは骨格模型を用いて計算した値ですので、実際の猫の歯にはもっと強い力が加わっているかもしれません。ドライフードをカリカリ噛み砕くことができるのは、咀嚼筋と歯が健康な証拠です。
上の図で示したように、口を開けたり閉じたりする時に働く筋肉は「咀嚼筋」(そしゃくきん)と呼ばれます。口を閉じるときに働く筋肉は側頭筋(T)、咬筋(M)、内側と外側翼突筋(P)。逆に口を開けるときに働く筋肉は顎二腹筋(D)です(Kim, 2018)。これらの筋肉によって生み出される力は、犬歯で7.5kg(73.3N)、裂肉歯で12kg(118N)程度と推計されています。ただしこれは骨格模型を用いて計算した値ですので、実際の猫の歯にはもっと強い力が加わっているかもしれません。ドライフードをカリカリ噛み砕くことができるのは、咀嚼筋と歯が健康な証拠です。
 しかしこれらは、私たちの奥歯のように上の歯と下の歯の面がピッタリとかみ合いません。猫の臼歯は先端がとがっており、なおかつ上下の歯が前後で微妙にずれた構造になっているため、ちょうど肉切りバサミのような役割を果たします。これは猫が肉を噛みちぎることに特化した構造の歯を発達させた結果で「裂肉歯」(carnassial)などとも呼ばれます。肉だけでなく、猫草をおいしそうにシャリシャリ噛みちぎる時に用いているのもこの歯です。ちなみに上顎の「後臼歯」はほとんどお情け程度にしかついておらず、ほとんど見分けることができません。
しかしこれらは、私たちの奥歯のように上の歯と下の歯の面がピッタリとかみ合いません。猫の臼歯は先端がとがっており、なおかつ上下の歯が前後で微妙にずれた構造になっているため、ちょうど肉切りバサミのような役割を果たします。これは猫が肉を噛みちぎることに特化した構造の歯を発達させた結果で「裂肉歯」(carnassial)などとも呼ばれます。肉だけでなく、猫草をおいしそうにシャリシャリ噛みちぎる時に用いているのもこの歯です。ちなみに上顎の「後臼歯」はほとんどお情け程度にしかついておらず、ほとんど見分けることができません。
 上の図で示したように、口を開けたり閉じたりする時に働く筋肉は「咀嚼筋」(そしゃくきん)と呼ばれます。口を閉じるときに働く筋肉は側頭筋(T)、咬筋(M)、内側と外側翼突筋(P)。逆に口を開けるときに働く筋肉は顎二腹筋(D)です(Kim, 2018)。これらの筋肉によって生み出される力は、犬歯で7.5kg(73.3N)、裂肉歯で12kg(118N)程度と推計されています。ただしこれは骨格模型を用いて計算した値ですので、実際の猫の歯にはもっと強い力が加わっているかもしれません。ドライフードをカリカリ噛み砕くことができるのは、咀嚼筋と歯が健康な証拠です。
上の図で示したように、口を開けたり閉じたりする時に働く筋肉は「咀嚼筋」(そしゃくきん)と呼ばれます。口を閉じるときに働く筋肉は側頭筋(T)、咬筋(M)、内側と外側翼突筋(P)。逆に口を開けるときに働く筋肉は顎二腹筋(D)です(Kim, 2018)。これらの筋肉によって生み出される力は、犬歯で7.5kg(73.3N)、裂肉歯で12kg(118N)程度と推計されています。ただしこれは骨格模型を用いて計算した値ですので、実際の猫の歯にはもっと強い力が加わっているかもしれません。ドライフードをカリカリ噛み砕くことができるのは、咀嚼筋と歯が健康な証拠です。
子猫の歯の生え変わり
猫にも人間と同様、歯の生え変わりがあります。「歯牙脱換」とも呼ばれるこのプロセスは、生後6ヶ月齢になるまでに終わるのが普通です。
生まれたての子猫には歯が生えておらず、口の中が母猫のお乳や人工ミルクを吸うことに特化されています。その後、授乳期が終わる生後15~20日目から乳歯が生え始め、乳離れが進むと同時に離乳食への移行が始まります。生後30~35日目になって26本の乳歯すべてが生えそろうと、3ヶ月齢くらいから頭蓋骨の成長に合わせて乳歯が少しずつ抜け落ち、この先ずっと使うことになる永久歯が生え始めます。
乳歯が永久歯に生え変わるおおよその時期と順番は以下です。口腔スペースの関係上、後臼歯の乳歯はそもそも生えません。
 乳歯から永久歯に生え変わる際、一時的に歯茎から2本の歯が同時に顔を見せます。通常は乳歯の方が抜け落ちますが、まれにそのまま歯茎の中にとどまってしまうことがあります。これが「乳歯遺残」(にゅうしいざん)と呼ばれる現象です。
乳歯から永久歯に生え変わる際、一時的に歯茎から2本の歯が同時に顔を見せます。通常は乳歯の方が抜け落ちますが、まれにそのまま歯茎の中にとどまってしまうことがあります。これが「乳歯遺残」(にゅうしいざん)と呼ばれる現象です。
放置すると正常な歯並びが崩れ、しっかりとフードを噛めなくなってしまいますので、生後6ヶ月を過ぎても乳歯が残っている場合は獣医さんに相談しましょう。場合によっては抜歯する必要があるかもしれません。
NEXT:猫の口にいる雑菌
生まれたての子猫には歯が生えておらず、口の中が母猫のお乳や人工ミルクを吸うことに特化されています。その後、授乳期が終わる生後15~20日目から乳歯が生え始め、乳離れが進むと同時に離乳食への移行が始まります。生後30~35日目になって26本の乳歯すべてが生えそろうと、3ヶ月齢くらいから頭蓋骨の成長に合わせて乳歯が少しずつ抜け落ち、この先ずっと使うことになる永久歯が生え始めます。
乳歯が永久歯に生え変わるおおよその時期と順番は以下です。口腔スペースの関係上、後臼歯の乳歯はそもそも生えません。
乳歯が生え変わる時期と順番

- 門歯(切歯)✓乳歯生え始め=2~3週齢
✓乳歯脱落+永久歯萠出=3~4ヶ月齢 - 犬歯✓乳歯生え始め=3~4週齢
✓乳歯脱落+永久歯萠出=4~5ヶ月齢 - 前臼歯✓乳歯生え始め=3~6週齢
✓乳歯脱落+永久歯萠出=4~6ヶ月齢 - 後臼歯✓乳歯生え始め=なし
✓乳歯脱落+永久歯萠出=4~6ヶ月齢
 乳歯から永久歯に生え変わる際、一時的に歯茎から2本の歯が同時に顔を見せます。通常は乳歯の方が抜け落ちますが、まれにそのまま歯茎の中にとどまってしまうことがあります。これが「乳歯遺残」(にゅうしいざん)と呼ばれる現象です。
乳歯から永久歯に生え変わる際、一時的に歯茎から2本の歯が同時に顔を見せます。通常は乳歯の方が抜け落ちますが、まれにそのまま歯茎の中にとどまってしまうことがあります。これが「乳歯遺残」(にゅうしいざん)と呼ばれる現象です。放置すると正常な歯並びが崩れ、しっかりとフードを噛めなくなってしまいますので、生後6ヶ月を過ぎても乳歯が残っている場合は獣医さんに相談しましょう。場合によっては抜歯する必要があるかもしれません。
詳しくは「猫の不正咬合」というページでも解説してあります。不正咬合(ふせいこうごう)とは歯並びが正しくない状態のことです。
猫の口の中にいる常在菌
常在菌(じょうざいきん)とは、猫の口の中に生息しているけれども症状を引き起こさない無害な菌のことです。過去に行われた調査では数百種類の細菌が確認されており、エサのタイプ(ドライかウエットか)、ライフスタイル(完全室内飼いか放し飼いか)、および品種によって、口内細菌叢(口内フローラ)の構成に個体差や品種差が生まれることが報告されています。
猫の口内細菌で問題となるのは、万が一人間に噛み付いてしまった時に症状を引き起こすタイプの細菌です。具体的には「パスツレラ菌」と「カプノサイトファーガ属菌」が挙げられます。これらの菌はほぼすべての猫の口の中に生息しており、人獣共通感染症(じんじゅうきょうつうかんせんしょう)を引き起こす危険性がありますので、特に免疫力の低下した人においては十分注意しなければなりません。
パスツレラ菌
 犬や猫の口腔には、かなりの高率でパスツレラ属菌が常在菌として存在しています。犬や猫、および免疫力が正常な人において問題になることはありませんが、糖尿病やアルコール性肝臓障害といった基礎疾患で抵抗力が落ちている人においては、髄膜炎(脊髄を包んでいる膜に菌が入り込むこと)などを引き起こすこともあります。近年のペットブームにより、ペットから人間への感染が年々増加していますが、そのほとんどは噛み傷やすり傷から菌が侵入するという経路です。
犬や猫の口腔には、かなりの高率でパスツレラ属菌が常在菌として存在しています。犬や猫、および免疫力が正常な人において問題になることはありませんが、糖尿病やアルコール性肝臓障害といった基礎疾患で抵抗力が落ちている人においては、髄膜炎(脊髄を包んでいる膜に菌が入り込むこと)などを引き起こすこともあります。近年のペットブームにより、ペットから人間への感染が年々増加していますが、そのほとんどは噛み傷やすり傷から菌が侵入するという経路です。
カプノサイトファーガ属菌
カプノサイトファーガ・カニモルサスという細菌は犬や猫などの口腔内に常在しており、咬まれたり、引っ掻かれたりすることで人間にも感染します。免疫機能の低下した人においては、敗血症や髄膜炎を起こし、ショックや多臓器不全に進行してしまうことがあります。一般的な症状は、発熱、倦怠感、腹痛、吐き気、頭痛などです。
なおこの感染症は、動物による咬傷事故等の発生数に対し、報告されている患者数が非常に少ないことから、極めて稀(まれ)にしか発生しないと考えられています。しかし日頃から、動物との過度のふれあいは避け(ペットとスプーンや食器を共用したり、手や顔などを好き放題なめさせるなど)、動物と触れあった後は手洗いを実行するに越したことはないでしょう。
NEXT:口の健康チェック
なおこの感染症は、動物による咬傷事故等の発生数に対し、報告されている患者数が非常に少ないことから、極めて稀(まれ)にしか発生しないと考えられています。しかし日頃から、動物との過度のふれあいは避け(ペットとスプーンや食器を共用したり、手や顔などを好き放題なめさせるなど)、動物と触れあった後は手洗いを実行するに越したことはないでしょう。
ひどいときには噛まれた傷口から雑菌が入り、指などを切断しなければならないこともあります。くれぐれも噛まれないようご注意ください。
猫の歯・口の健康チェック
以下でご紹介するのは、猫の歯・口によく見られる異常と、それに関連した疾患の対応一覧表です。もし猫の歯・口に以下で述べるような異常や変化が見られた場合は、念のため疾患の可能性を疑い、場合によっては獣医さんに診てもらいます。
 NEXT:猫の歯・口Q & A集
NEXT:猫の歯・口Q & A集
猫の歯・口の異常と病気
- 口が臭い猫エイズウイルス感染症 | 歯周病 | 虫歯 | 口内炎 | 歯根吸収 | 慢性腸炎 | 小腸性下痢症 | 口腔ガン | 急性糸球体腎炎
- 歯がぐらぐらする歯周病
- 歯が変色している歯根吸収
- 口の中が腫れている猫ウイルス性鼻気管炎 | 猫白血病ウイルス感染症 | 猫エイズウイルス感染症 | 口内炎 | 歯根吸収 | 歯周病 | 口腔ガン
- 口の中が赤い熱中症にかかった
- 口の中が青紫(チアノーゼ)有毒生物に刺された | 毒物の摂取 | 異物を飲み込んだ | 心不全 | ファロー四徴症 | 喘息
- 口の中が蒼白猫白血病ウイルス感染症 | 猫伝染性貧血 | 溶血性貧血 | 急性腎不全 | 慢性腎不全 | 急性糸球体腎炎 ・ ネフローゼ症候群 | 水腎症 | 尿毒症
- 口の中に点状出血血小板減少症 | 白血病
- 口の中が黒い口腔ガン
- 口の中に潰瘍がある口腔ガン
よくある口内病変

- 流涎(よだれ)=100%
- 口臭=90%
- 口内潰瘍=80%
- 歯肉炎=70%
- 歯周炎=60%
- リンパ節腫脹=60%
猫の口の中は全身の健康を反映するバロメーター。日常的にチェックする習慣をつけましょう。
猫の歯・口Q & A
以下は猫の歯や口についてよく聞かれる疑問や質問の一覧リストです。思い当たるものがあったら読んでみてください。何かしら解決のヒントがあるはずです。
猫の口が閉じません
顎関節症のうちの「閉口障害」かもしれません。
開いた口が閉じなくなることを「閉口障害」と言います。猫における原因は顎関節の脱臼、顎の骨折、後天的な不正咬合、下顎の麻痺などさまざまです。脱臼の場合は患側の逆側に下顎がずれるのが特徴で、骨折の場合は患側に下顎がずれるのが特徴です。
 猫の口が開いたまま急に閉じなくなったという場合は、骨格に何らかの怪我を負っている可能性がありますので、動物病院でレントゲンなどを撮影してもらいましょう。脱臼の場合は整復、骨折の場合は固定治療などが行われます。
猫の口が開いたまま急に閉じなくなったという場合は、骨格に何らかの怪我を負っている可能性がありますので、動物病院でレントゲンなどを撮影してもらいましょう。脱臼の場合は整復、骨折の場合は固定治療などが行われます。
猫の口が開きません
顎関節症のうちの「開口障害」かもしれません。
閉じた口が開かなくなることを「開口障害」もしくは「顎関節の強直症」と言います。強直症には関節自体が関わる「真性強直症」と、関節以外の組織が関わる「偽性強直症」とがあり、猫においては若い頃の外傷を原因とする偽性強直症が多いとされています。
顔面部の骨折の原因となる「交通事故」「落下」「衝突」の後に口が開かなくなった場合は、線維性の組織が顎をロックしているのかもしれません。いずれにしても動物病院を受診しましょう。なお、猫が投薬を嫌がって口を開けないのは単なる拒絶です。効果的な口の開け方に関しては「猫に薬を飲ませる方法・完全ガイド」で解説してありますのでご参照ください。
猫の口が半開きのままです
歯並びが悪いのかもしれません。
猫の歯並びが正常であれば、以下の写真で示すように上下の歯がうまく噛み合わさってお互いを邪魔することはありません。
 しかし何らかの理由で歯並びに異常が生じると、歯と歯がぶつかって口が半開き状態になります。先天的な理由として多いのが遺伝や乳歯遺残、後天的な理由として多いのが怪我や歯の破折です。
しかし何らかの理由で歯並びに異常が生じると、歯と歯がぶつかって口が半開き状態になります。先天的な理由として多いのが遺伝や乳歯遺残、後天的な理由として多いのが怪我や歯の破折です。猫の口が半開きのまま急に閉じなくなったというときは、取り急ぎ怪我の可能性を考慮して動物病院を受診しましょう。一方、生まれつき半開きのまま閉じないという場合は、そもそも歯並びに異常があると考えられます。歯列矯正の方法としてインクラインプレイン、咬翼装置、インクラインキャップなどがあるものの、専門的な技術を要するためどの動物病院でもできるわけではありません。
 上の写真で示したように、特に短頭種の鼻ぺちゃ猫では骨格の異常により歯並びが大きく歪められていますので、抜歯など猫に対する負担が大きい治療をする必要があります。先天的な問題を解決する根本的な方法は、鼻ぺちゃ猫を繁殖しないことです。
上の写真で示したように、特に短頭種の鼻ぺちゃ猫では骨格の異常により歯並びが大きく歪められていますので、抜歯など猫に対する負担が大きい治療をする必要があります。先天的な問題を解決する根本的な方法は、鼻ぺちゃ猫を繁殖しないことです。
乳歯が残ったままです
ネコ膝-乳歯症候群かもしれません。
生後半年を過ぎた子猫において乳歯が抜け落ちずに歯茎に残っている場合は乳歯遺残と呼ばれます。乳歯遺残の発生原因はよくわかっていませんが、より厄介な病気として「ネコ膝-乳歯症候群」(Feline Knees-Teeth Syndrome)というものがあります。
これは明確な外傷なく発生する膝蓋骨(お皿)の骨折と、乳歯が抜け落ちず歯槽骨の中に残る乳歯遺残を特徴とする奇病で、2004年に文献内に初登場して以来、アメリカで60例弱、イギリスで数例が報告されているだけの極めて珍しい病気の一つです。また近年、日本でも症例が報告されるようになりました(
 :日本動物高度医療センター)。
:日本動物高度医療センター)。暫定的な診断基準は、乳歯遺残(特に臼歯)、最低1つの非外傷性の膝蓋骨骨折、膝蓋骨以外の場所に発生した両側性の非外傷性骨折で、よくある骨折部位は脛骨(すね)、大腿骨(ふともも)、骨盤(特に坐骨)、上腕骨などです。
乳歯遺残のほか原因のわからない骨折が見られるような場合は、念のためこのネコ膝-乳歯症候群を疑ったほうがよいでしょう。なお近年は病態をより正確に表した「膝蓋骨骨折・歯牙異常症候群」(Patellar fracture And Dental anomaly Syndrome, PADS)という病名が提唱されています。
猫の歯が折れました
歯髄が露出している場合は積極的な治療を行う必要があります。
歯が折れることを「破折」(はせつ)と言います。猫で特に多いのが犬歯(牙)の破折です。例えば交通事故、高い場所からの落下、遊んでいる時の衝突など、歯に対して強い力が加わるような状況でポキンと折れてしまいます。
歯の中心に歯髄(しずい=血管と神経の束)が見えていない時は、単純歯冠破折(=歯が欠けた状態)、歯の中心に小さな穴が空いて歯髄が露出している時は複雑歯冠破折(=歯が折れた状態)などとも呼ばれます。
複雑歯科破折、いわゆる歯が折れた状態の場合、それが乳歯であっても永久歯であっても積極的に治療しなければなりません。もし放置してしまうと、露出した歯髄がひどい痛みを引き起こしたり、中心部の穴から病原体が入り込んで膿瘍を形成してしまうことがあります。
乳歯に対する治療は抜歯が基本となり、永久歯に対する治療は抜歯もしくは歯髄キャップによる保護が基本となります。いずれにしても、歯が折れて中心部の穴が赤くなっているような場合は、茶色~黒に変色する前に速やかに動物病院を受診しましょう。
猫の歯がグラグラします
歯茎の根本にある歯根部が折れているかもしれません。
歯茎の上にあって外から見える部分のことを「歯冠部」と呼ぶのに対し、歯茎の中に埋もれて見えない部分を「歯根部」と呼びます。この歯根部が何らかの理由で折れてしまった状態が「歯根破折」です。
歯冠部が折れた場合は歯が短くなっていたり出血が見られますのですぐに気付くことができます。一方、歯根部は外から見えない部分にあるため、仮に折れていたとしてもなかなか気づきません。確かめる際の最も簡単な方法は、歯をつかんで軽く左右に動かしてみることです。根元が折れているとグラグラ動きますのですぐに分かります。
歯根部の歯髄(神経や血管)が生きている場合は、折れた部分を安定化させれば自然治癒力によってゾウゲ質やセメント質が元通りになる可能性があります。一方、歯髄がすでに死んでいる場合は自然治癒が見込めず、また細菌感染の危険もありますので、抜歯が第一選択肢となります。
猫の歯の色が変です
さまざまな病気の可能性があります。
さまざまな原因により猫の歯の色が変わってしまうことがあります。ケースバイケースですが一般的な例を挙げると以下のようになるでしょう。
猫の歯の変色原因
- 黄色い猫の歯が黄色いという場合は、加齢に伴う自然な着色だと考えられます。ドライフードにしてもウェットフードにしても茶色っぽい色合いですので、長い間食べ続けていると色素成分が歯の表面に沈着し、全体として黄ばんだ色合いになります。日常的にコーヒーを飲んだりカレーを食べる人の歯が黄ばんでしまうのと同じ理屈です。
- 茶色い猫の歯が茶色いという場合、歯の表面に歯石が蓄積している可能性があります。特に奥歯(前臼歯+後臼歯)で顕著です。詳しくは猫の歯周病を参照ください。
- ピンク~赤い猫の歯が赤いという場合、歯肉炎や歯の破折に伴う出血、もしくは歯根吸収病変の可能性があります。根本が赤く変色しているときは要注意です。
- 灰色~黒い猫の歯が黒いという場合、神経と血管の束である「歯髄」が死んでしまっている可能性があります。人間で言う「歯の神経が死んでしまった状態」です。歯髄が壊死すると、壊死組織から出る硫化水素と血液の中に含まれる鉄分とが反応して硫化鉄が生成されます。この物質は黒っぽい色合いをしていますので、歯に染み込むと全体的に黒っぽく見えてしまうというわけです。
口をぺちゃぺちゃ鳴らします
口の中に痛みを抱えている可能性が大です。
猫が口をぺちゃぺちゃくちゃくちゃ鳴らす理由は、口の中に何らかの違和感を抱えているからかもしれません。よくある原因は舌の炎症である舌炎、唇の炎症である口唇炎、歯茎の炎症である歯肉炎、口蓋の炎症である口内炎などです。また舌の根元に紐状の異物が絡んでいるときもくちゃくちゃと音を鳴らすことがあります。
 痛みや違和感が原因のくちゃくちゃは多くの場合、何の脈絡もなく出ますが、ストレスが原因のくちゃくちゃはある特定の状況において頻繁に出ます。例えば猫の顔をじっと覗き込んだ時とか周囲で大声を出した時などです。カメラを向けたとき、目線を逸(そ)らせて急に口をペチャペチャ鳴らすのは「やめて」という猫からのストレスシグナルですので、無理強いせずそっとしておきましょう。
痛みや違和感が原因のくちゃくちゃは多くの場合、何の脈絡もなく出ますが、ストレスが原因のくちゃくちゃはある特定の状況において頻繁に出ます。例えば猫の顔をじっと覗き込んだ時とか周囲で大声を出した時などです。カメラを向けたとき、目線を逸(そ)らせて急に口をペチャペチャ鳴らすのは「やめて」という猫からのストレスシグナルですので、無理強いせずそっとしておきましょう。
口の端の黒いブツブツは何?
それは猫ニキビでしょう。
 「猫ニキビ」とは毛穴に詰まった角栓(コメド)が飛び出して黒い点々に見えた状態のことです。皮脂を分泌する顎の下や唇の端っこ(口角)によく現れます。命を脅かすような恐ろしい病気ではありませんが、ツブツブ状のものを異常に嫌う「トライポフォビア」の人ならどうしても気になってしまうでしょう。
「猫ニキビ」とは毛穴に詰まった角栓(コメド)が飛び出して黒い点々に見えた状態のことです。皮脂を分泌する顎の下や唇の端っこ(口角)によく現れます。命を脅かすような恐ろしい病気ではありませんが、ツブツブ状のものを異常に嫌う「トライポフォビア」の人ならどうしても気になってしまうでしょう。原因がよく分かっていないため治療はケースバイケースの対症療法となります。詳しくは以下のページをご参照ください。
猫の口が臭いです…
歯根膿瘍かもしれません。
そもそも猫の口臭はそれほど芳(かぐわ)しいものではありません。軽度では「ドブの臭い」「魚の臭い」、重度では「卵の腐った臭い」とか「おならと同じ臭い」といった臭いがあります。
重度に分類されるようなひどい口臭の原因は、多くの場合「歯根膿瘍」です。歯根膿瘍とは歯の根本に炎症が起こり膿が溜まってしまった状態のことで、人間においても犬や猫においても、ひどい悪臭を放つことで知られています。悪臭の原因は硫黄を含む様々な物質で、排泄物の中にも含まれていますので「おならと同じ臭い」と感じる人もいることでしょう。
歯根膿瘍は歯周病を併発していることもありますので、飼い主は日常的に猫の口の中をチェックし、歯磨きを習慣化するのが理想です。しかしその猫は素直に口を開けてくれません。歯磨き効果のあるフードや歯磨きグッズで代用するのが現実的でしょう。
歯磨きのやり方は「猫の歯磨きの仕方・完全ガイド」、安全な歯磨きグッズの選び方は「歯磨き粉の成分・大辞典」でまとめてあります。