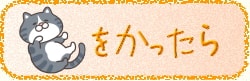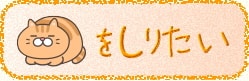炎症性腸疾患の病態と症状
慢性腸炎とは腸管粘膜に免疫細胞が集合し、長期に及ぶ炎症状態が引き起こされた状態のことです。炎症の原因として食事やがん(リンパ腫)が除外されたものの、依然として原因がはっきりしない状態は特に「炎症性腸疾患」(Inflammatory Bowel Disease, IBD)とも呼ばれます。


炎症性腸疾患の病態
猫の消化管で見られる原因不明の炎症性病変は1970年代から報告されていました。しかし内視鏡が十分に普及していなかったため「非特異的な腸疾患」という漠然とした診断名を与えられ、安楽死になることも少なくありませんでした。その後、1980年代の半ばに入ってから医療カンファレンスや医学情報誌で「リンパ球・形質細胞性」や「炎症性腸疾患」という言葉が使われだし、疾患の認知度が少しずつ高まっていきました。
現在、WSAVA(世界小動物獣医療協会)の胃腸疾患標準化グループは猫の炎症性腸疾患(IBD)を以下のように定義しています( :WSAVA, 2009)。
:WSAVA, 2009)。
 疾患の特徴は粘膜固有層における炎症性細胞の増加で、細胞のタイプは単一の場合もあれば複合の場合もあります。最も多いのがリンパ細胞と形質細胞であることから「リンパ球・形質細胞性腸炎」と呼ばれることもあります。その他の所見は、粘膜の萎縮、陰窩の過形成を伴わない腸絨毛の萎縮、腸絨毛の融合、上皮組織のただれ、線維症などです。
疾患の特徴は粘膜固有層における炎症性細胞の増加で、細胞のタイプは単一の場合もあれば複合の場合もあります。最も多いのがリンパ細胞と形質細胞であることから「リンパ球・形質細胞性腸炎」と呼ばれることもあります。その他の所見は、粘膜の萎縮、陰窩の過形成を伴わない腸絨毛の萎縮、腸絨毛の融合、上皮組織のただれ、線維症などです。
現在、WSAVA(世界小動物獣医療協会)の胃腸疾患標準化グループは猫の炎症性腸疾患(IBD)を以下のように定義しています(
 :WSAVA, 2009)。
:WSAVA, 2009)。
IBDの定義(WSAVA)
- 胃腸の症状が3週間超継続
- 食事療法や線虫駆除への反応が悪い
- 組織学的に粘膜の炎症性病変を確認できる
- 抗炎症薬や免疫調整療法に対する反応が良い
- 他の疾患が見当たらない
 疾患の特徴は粘膜固有層における炎症性細胞の増加で、細胞のタイプは単一の場合もあれば複合の場合もあります。最も多いのがリンパ細胞と形質細胞であることから「リンパ球・形質細胞性腸炎」と呼ばれることもあります。その他の所見は、粘膜の萎縮、陰窩の過形成を伴わない腸絨毛の萎縮、腸絨毛の融合、上皮組織のただれ、線維症などです。
疾患の特徴は粘膜固有層における炎症性細胞の増加で、細胞のタイプは単一の場合もあれば複合の場合もあります。最も多いのがリンパ細胞と形質細胞であることから「リンパ球・形質細胞性腸炎」と呼ばれることもあります。その他の所見は、粘膜の萎縮、陰窩の過形成を伴わない腸絨毛の萎縮、腸絨毛の融合、上皮組織のただれ、線維症などです。
炎症性腸疾患の症状
炎症性腸疾患(IBD)の症状は別の疾患でも見られるありふれたものばかりです。5~8歳に好発するとされますが、8歳以上で発症する例や1歳未満で発症する例も報告されています( :Jergens, 2012)。
:Jergens, 2012)。
慢性的な嘔吐、小腸性の下痢、体重減少のうち少なくとも1つと、超音波検査で小腸壁の肥厚が確認された猫100頭を対象として組織生検を行ったところ、99頭において消化管の病変が見つかったといいますので「猫がよく吐くのは普通のこと」と油断しないほうが良いでしょう( :Norsworthy, 2013)。
:Norsworthy, 2013)。
 嘔吐は基本的に非噴出性で、透明・泡状の胃液や黄色みがかった胆汁酸を吐き出します。未消化~半消化のフードを含むことがあり、血液はほとんど見られませんが、見られる場合は胃や上部消化管の潰瘍性損傷が疑われます。
嘔吐は基本的に非噴出性で、透明・泡状の胃液や黄色みがかった胆汁酸を吐き出します。未消化~半消化のフードを含むことがあり、血液はほとんど見られませんが、見られる場合は胃や上部消化管の潰瘍性損傷が疑われます。
症状は発症と自然寛解(一時的な軽快状態)を繰り返すため、飼い主が「いつの間にか治った」と安心して受診が遅れてしまうことが少なくありません。症状再発のトリガーはよく分かっておらず、食事内容、病原性細菌、薬剤(ステロイド・抗生物質・抗菌薬)の摂取などが想定されています。 膵管が総胆管に連なり近位十二指腸に開くという解剖学的な特徴から、腸管内の炎症が総胆管を上昇し膵臓、胆道に波及してしまうことがあります。肝炎と膵炎を伴っている場合は特に「三重炎」(triaditis)とも呼ばれます。
膵管が総胆管に連なり近位十二指腸に開くという解剖学的な特徴から、腸管内の炎症が総胆管を上昇し膵臓、胆道に波及してしまうことがあります。肝炎と膵炎を伴っている場合は特に「三重炎」(triaditis)とも呼ばれます。
 :Jergens, 2012)。
:Jergens, 2012)。慢性的な嘔吐、小腸性の下痢、体重減少のうち少なくとも1つと、超音波検査で小腸壁の肥厚が確認された猫100頭を対象として組織生検を行ったところ、99頭において消化管の病変が見つかったといいますので「猫がよく吐くのは普通のこと」と油断しないほうが良いでしょう(
 :Norsworthy, 2013)。
:Norsworthy, 2013)。
IBDの主症状
胃十二指腸や小腸の炎症では嘔吐、体重減少、小腸性の下痢症が多く見られ、大腸の炎症では大腸性下痢症、血便、粘液便が多く見られます。またIBDに起因するリンパ腫(がん)、吸収不良に起因する出血性下痢、免疫抑制剤に後続するトキソプラズマ症など特殊な合併症も報告されています。
 嘔吐は基本的に非噴出性で、透明・泡状の胃液や黄色みがかった胆汁酸を吐き出します。未消化~半消化のフードを含むことがあり、血液はほとんど見られませんが、見られる場合は胃や上部消化管の潰瘍性損傷が疑われます。
嘔吐は基本的に非噴出性で、透明・泡状の胃液や黄色みがかった胆汁酸を吐き出します。未消化~半消化のフードを含むことがあり、血液はほとんど見られませんが、見られる場合は胃や上部消化管の潰瘍性損傷が疑われます。症状は発症と自然寛解(一時的な軽快状態)を繰り返すため、飼い主が「いつの間にか治った」と安心して受診が遅れてしまうことが少なくありません。症状再発のトリガーはよく分かっておらず、食事内容、病原性細菌、薬剤(ステロイド・抗生物質・抗菌薬)の摂取などが想定されています。
 膵管が総胆管に連なり近位十二指腸に開くという解剖学的な特徴から、腸管内の炎症が総胆管を上昇し膵臓、胆道に波及してしまうことがあります。肝炎と膵炎を伴っている場合は特に「三重炎」(triaditis)とも呼ばれます。
膵管が総胆管に連なり近位十二指腸に開くという解剖学的な特徴から、腸管内の炎症が総胆管を上昇し膵臓、胆道に波及してしまうことがあります。肝炎と膵炎を伴っている場合は特に「三重炎」(triaditis)とも呼ばれます。
炎症性腸疾患の原因
猫における炎症性腸疾患(IBD)の原因はよくわかっていません。人間で見られるクローン病や潰瘍性大腸炎と同様、環境要因、腸内フローラ、食事内容、消化管粘膜の免疫システムが複雑に絡み合って発症するものと推測されています。
腸内フローラ
腸管粘膜に生息している細菌の数と十二指腸の構造異常、マクロファージやT細胞の浸潤、炎症性サイトカインの増加が連動していることから、腸内フローラ(細菌叢)が発症に関わっていると推測されています( :Janeczko, 2008)。腸内フローラは食事内容によって変化しますので、フードが間接的な原因になっているとも言えるでしょう。
:Janeczko, 2008)。腸内フローラは食事内容によって変化しますので、フードが間接的な原因になっているとも言えるでしょう。
しかし腸内フローラがどのようなバランスになったら毒素症(dysbiosis)につながるのかはよくわかっていません。例えばIBDを発症した猫の小腸では腸内細菌科が多くなり、便サンプル中のビフィドバクテリウムとバクテロイデスが減ってデスルフォビブリオ属が増えるといった報告がある一方( :Suchodolski, 2011)、消化管疾患を抱えた猫の腸管粘膜において球菌、クロストリジウム属、大腸菌の割合が増えるといった別の報告もあります(
:Suchodolski, 2011)、消化管疾患を抱えた猫の腸管粘膜において球菌、クロストリジウム属、大腸菌の割合が増えるといった別の報告もあります( :Simpson, 2015)。
:Simpson, 2015)。
 :Janeczko, 2008)。腸内フローラは食事内容によって変化しますので、フードが間接的な原因になっているとも言えるでしょう。
:Janeczko, 2008)。腸内フローラは食事内容によって変化しますので、フードが間接的な原因になっているとも言えるでしょう。しかし腸内フローラがどのようなバランスになったら毒素症(dysbiosis)につながるのかはよくわかっていません。例えばIBDを発症した猫の小腸では腸内細菌科が多くなり、便サンプル中のビフィドバクテリウムとバクテロイデスが減ってデスルフォビブリオ属が増えるといった報告がある一方(
 :Suchodolski, 2011)、消化管疾患を抱えた猫の腸管粘膜において球菌、クロストリジウム属、大腸菌の割合が増えるといった別の報告もあります(
:Suchodolski, 2011)、消化管疾患を抱えた猫の腸管粘膜において球菌、クロストリジウム属、大腸菌の割合が増えるといった別の報告もあります( :Simpson, 2015)。
:Simpson, 2015)。
免疫システム
片利共生細菌や病原菌を免疫システムがどのように認識するかによってリスクが変わると考えられます。たとえば人間におけるNOD2/CARD15、犬におけるTLR4やTLR5など、免疫受容器に関連した遺伝子の個体差などです。
猫においてはシャムを始めとするアジア発祥品種における遺伝的な脆弱性が指摘されているものの、はっきりしたメカニズムは解明されていません。一例としては「IBDの腸管上皮細胞における抗原提示分子(MHCII)の発現量増加→片利共生菌・病原菌・食品成分に対する免疫応答の亢進→T細胞の過剰な反応と炎症促進性サイトカイン(IL-17・TNF-α)の生成増加→慢性的な炎症」などが考えられます。
猫においてはシャムを始めとするアジア発祥品種における遺伝的な脆弱性が指摘されているものの、はっきりしたメカニズムは解明されていません。一例としては「IBDの腸管上皮細胞における抗原提示分子(MHCII)の発現量増加→片利共生菌・病原菌・食品成分に対する免疫応答の亢進→T細胞の過剰な反応と炎症促進性サイトカイン(IL-17・TNF-α)の生成増加→慢性的な炎症」などが考えられます。
炎症性腸疾患の検査・診断
炎症性腸疾患の検査
疾患を鑑別診断するために推奨される検査は病歴、身体検査、CBC(全血算)、血清T4(甲状腺ホルモン)、感染症検査、尿検査、腹部X線検査などです。葉酸は十二指腸、ビタミンB12(コバラミン)は回腸から吸収されるため、これらの臓器に異常があると参照範囲内から逸脱した低値を示します。見落とすと治療が遅れるため、血液検査項目に入れた方が安全です( :Simpson, 2008)。
:Simpson, 2008)。
炎症性腸疾患の確定診断には組織サンプルの採取と病理検査が必要です。共通所見としては炎症性細胞の浸潤と粘膜の構造的劣化が見られます。食欲不振、体重減少、頻回嘔吐、小腸性下痢症などが見られる場合は胃や小腸粘膜の生検、血便や粘液便が見られる場合は大腸粘膜の生検が優先的に行われます。 胃腸の組織学的な検査に関してはWSAVAが正常と異常のガイドラインを示しているものの、採取したサンプルが少なくて低質、夾雑物(アーティファクト)が多い、病理医の経験によって判定が大きく異なるなどの問題があるため、診断はそれほど簡単ではありません(
胃腸の組織学的な検査に関してはWSAVAが正常と異常のガイドラインを示しているものの、採取したサンプルが少なくて低質、夾雑物(アーティファクト)が多い、病理医の経験によって判定が大きく異なるなどの問題があるため、診断はそれほど簡単ではありません( :Day, 2008)。また飼い主に経済的な余裕がない場合や患猫が麻酔に耐えられないような場合は、生検自体が不可能となり診断を余計に難しくします。
:Day, 2008)。また飼い主に経済的な余裕がない場合や患猫が麻酔に耐えられないような場合は、生検自体が不可能となり診断を余計に難しくします。
 :Evans, 2006)。診断が遅れるとがん、肥満細胞腫、感染症性腸疾患が悪化するため速やかな検査が必要です。
:Evans, 2006)。診断が遅れるとがん、肥満細胞腫、感染症性腸疾患が悪化するため速やかな検査が必要です。
 :Simpson, 2008)。
:Simpson, 2008)。炎症性腸疾患の確定診断には組織サンプルの採取と病理検査が必要です。共通所見としては炎症性細胞の浸潤と粘膜の構造的劣化が見られます。食欲不振、体重減少、頻回嘔吐、小腸性下痢症などが見られる場合は胃や小腸粘膜の生検、血便や粘液便が見られる場合は大腸粘膜の生検が優先的に行われます。
 胃腸の組織学的な検査に関してはWSAVAが正常と異常のガイドラインを示しているものの、採取したサンプルが少なくて低質、夾雑物(アーティファクト)が多い、病理医の経験によって判定が大きく異なるなどの問題があるため、診断はそれほど簡単ではありません(
胃腸の組織学的な検査に関してはWSAVAが正常と異常のガイドラインを示しているものの、採取したサンプルが少なくて低質、夾雑物(アーティファクト)が多い、病理医の経験によって判定が大きく異なるなどの問題があるため、診断はそれほど簡単ではありません( :Day, 2008)。また飼い主に経済的な余裕がない場合や患猫が麻酔に耐えられないような場合は、生検自体が不可能となり診断を余計に難しくします。
:Day, 2008)。また飼い主に経済的な余裕がない場合や患猫が麻酔に耐えられないような場合は、生検自体が不可能となり診断を余計に難しくします。
消化管組織の生検
- 内視鏡口から消化管に向かってカメラを入れる内視鏡検査では、胃・十二指腸・空腸上部にある病変部の視認と即座の粘膜サンプル採取が可能なため、おなかにメスを入れる検査より優先的に行われます。

- 腹腔鏡おなかに小さな穴をあけてカメラを通す腹腔鏡検査は空腸以下にある組織の全層採取に適しています。しかし一度にあまりにも大きなサンプルを切り取ってしまうと腸管壁の離開や細菌汚染のリスクが発生します。
- 開腹おなかを大きく切り開いて消化管を露出する開腹手術は胃腸以外の消化器から組織サンプルを採取するのに適しています。例えば三重炎によって肝臓や膵臓にも病変が見られる場合などです。
 :Evans, 2006)。診断が遅れるとがん、肥満細胞腫、感染症性腸疾患が悪化するため速やかな検査が必要です。
:Evans, 2006)。診断が遅れるとがん、肥満細胞腫、感染症性腸疾患が悪化するため速やかな検査が必要です。
炎症性腸疾患の鑑別診断
検査を通じて得られた情報を元に、腸の炎症を引き起こしうるさまざまな疾患の可能性を1つ1つ除外していきます。例えば腸管の粘膜固有層にマクロファージや好中球が多く見られる場合は感染症の疑いが高いため培養・染色・FISH法で病原体を確認するとか、好酸球が多く見られる場合は寄生虫症や食物不耐症を疑うなどです。実際、好中球性の炎症性腸疾患(IBD)を発症した猫からはカンピロバクター(C.Coli)が高い確率で検出されることが確認されています。しかし組織生検だけから病理診断できることはまれですので、最終的には複数の検査結果から総合的に判断します。
猫の消化管に発生するリンパ腫としては腸絨毛の根本に発生する小細胞性リンパ腫や、進行が早く転移しやすい大細胞リンパ芽球性リンパ腫などが多く報告されています。結論は出ていないものの、組織学的に見分けることがとてもむずかしいことから、炎症性腸疾患がリンパ腫に進行するのではないかと疑われています。例えば以下はリンパ球・形質細胞性腸炎(LPE)と消化管リンパ腫の特徴を比較した一覧表です( :Tams, 1993)。
:Tams, 1993)。
上記したような診断の目安はあるものの、多くの項目は重なっているため顕微鏡下で診断を下すことは極めて困難です。そのため近年では医学の進歩に合わせた以下のような検査法が登場しています( :Kiupel, 2010)。
:Kiupel, 2010)。
IBDと類似疾患の鑑別
- 肝炎・膵炎との鑑別肝臓酵素値 | fPLI(膵リパーゼ免疫反応検査) | 胆汁酸 | 腹部超音波検査 | 組織生検
- 非消化管疾患との鑑別サイロキシン(T4) | 腹部X線検査 | 腹部超音波検査 | 尿検査(腎臓病を除外) | 便検査(寄生虫を除外) | 感染症検査(FIV・FeLVを除外)
- 食物アレルギーとの鑑別除去食によるフードトライアル最低7日間
- リンパ腫との鑑別回腸粘膜生検 | 開腹手術による複数臓器からの生検 | B細胞やT細胞の免疫組織化学検査 | PCR検査
猫の消化管に発生するリンパ腫としては腸絨毛の根本に発生する小細胞性リンパ腫や、進行が早く転移しやすい大細胞リンパ芽球性リンパ腫などが多く報告されています。結論は出ていないものの、組織学的に見分けることがとてもむずかしいことから、炎症性腸疾患がリンパ腫に進行するのではないかと疑われています。例えば以下はリンパ球・形質細胞性腸炎(LPE)と消化管リンパ腫の特徴を比較した一覧表です(
 :Tams, 1993)。
:Tams, 1993)。
| 所見 | LPE | リンパ腫 |
| 腸管壁の肥厚 | 有/無 | 有/無 |
| 細胞集簇 | 異質細胞 | 同質細胞 |
| 粘膜固有層浸潤 | 有 | 有/無 |
| 粘膜下浸潤 | 有/無 | 有/無 |
| 筋層浸潤 | 無 | 有/無 |
| 漿膜層浸潤 | 無 | 有/無 |
| 他臓器症状 | 無 | 有/無 |
 :Kiupel, 2010)。
:Kiupel, 2010)。
IBDとリンパ腫の鑑別診断検査
- 免疫表現型解析免疫表現型解析とは細胞表面にある抗原やマーカーから細胞の種類を同定する方法。組織学的にリンパ腫と診断された32頭のリンパ細胞に発現しているタンパク質複合体の一種CD3、CD79、BLA-36を調べたところ、うち5頭に関しては炎症性腸疾患という診断が妥当との結論に至っています(
 :Waly, 2009)。
:Waly, 2009)。 - クローナリティ解析クローナリティ解析とは増殖様式を区分することで細胞の種類を同定する技術のこと。反応性過形成では組織の中で種々のリンパ球が増える「ポリクローナル増殖」が見られるのに対し、リンパ腫では腫瘍化したリンパ球が他のリンパ球よりも相対的に多くなり、単一の細胞集団を形成する「モノクローナル増殖」が特徴として見られます(
 :Moore, 2005)。
:Moore, 2005)。 - メタボローム解析メタボローム解析とは酵素などの働きによって体内で作り出された低分子の代謝物質(メタボライト)を明らかにすること。多価不飽和脂肪酸のうちエイコサペンタエン酸、ヘネイコサペンタエン酸、ステアリン酸の3種類で「リンパ腫>IBD」という関係性が確認されています(
 :Marsilio, 2021)。
:Marsilio, 2021)。
炎症性腸疾患の治療・予後
食事療法
炎症性腸疾患(IBD)と食物反応性腸炎(FRE)を顕微鏡下で組織学的に鑑別することは非常に難しいため、診断を兼ねて試験的に行われる食事療法が重要となります。基本的なコンセプトは「食事を変えて症状が消え、食事を元に戻して症状が再び現れたら食物反応性腸炎」というものです。逆に食事によって症状の増減が確認されない場合は消去法的に「炎症性腸疾患」と診断されます。
炎症性腸疾患の食事療法で用いられるのは以下のような特徴を持ったフードです。「手作りフード」で補うことは不可能ではないものの、マクロ栄養素(糖質・脂質・タンパク質)とミクロ栄養素(ビタミン・ミネラル)のバランスを整えることが非常に難しいため推奨されません。 :Makielsk, 2017 |
:Makielsk, 2017 |  :Rudinsky, 2018)。獣医師や専門家の逸話レベルであるグレード4(当ページでは省略)はたくさんあるものの、最も信頼性が高いグレード1の報告は今の所ありません。
:Rudinsky, 2018)。獣医師や専門家の逸話レベルであるグレード4(当ページでは省略)はたくさんあるものの、最も信頼性が高いグレード1の報告は今の所ありません。
炎症性腸疾患の食事療法で用いられるのは以下のような特徴を持ったフードです。「手作りフード」で補うことは不可能ではないものの、マクロ栄養素(糖質・脂質・タンパク質)とミクロ栄養素(ビタミン・ミネラル)のバランスを整えることが非常に難しいため推奨されません。
IBD用のキャットフード
- 除去食特定のタンパク質を成分から省いたフード
- 新奇タンパク鹿肉やアヒル肉など抗原性が異なるタンパク質を用いたフード
- 加水分解タンパク加水分解処理により分子構造を変化させたタンパク質を含むフード
- 療法食胃腸の障害に特化して栄養バランスを調整したフード
 :Makielsk, 2017 |
:Makielsk, 2017 |  :Rudinsky, 2018)。獣医師や専門家の逸話レベルであるグレード4(当ページでは省略)はたくさんあるものの、最も信頼性が高いグレード1の報告は今の所ありません。
:Rudinsky, 2018)。獣医師や専門家の逸話レベルであるグレード4(当ページでは省略)はたくさんあるものの、最も信頼性が高いグレード1の報告は今の所ありません。
療法食/エビデンスグレード2
慢性的な下痢を示す16頭の猫をランダムで2つのグループに分け、ウエットタイプの療法食AもしくはBのどちらか一方だけを4週間に渡って給餌しました( :Laflamme, 2012)。給餌試験期間の最後の1週間で便スコア1(極度に乾いて硬い)~7(極度にゆるく水様)を毎日記録し、その後フードを入れ替えてさらに4週間の試験を設けた結果、最終的に15頭が完了したといいます。
:Laflamme, 2012)。給餌試験期間の最後の1週間で便スコア1(極度に乾いて硬い)~7(極度にゆるく水様)を毎日記録し、その後フードを入れ替えてさらに4週間の試験を設けた結果、最終的に15頭が完了したといいます。
便スコアに関してはどちらのフードも改善を見せましたが、1ポイント以上改善した割合はAが40%でBが67%、スコアが正常(3以上)の割合はAが13.3%でBが46.7%で、総合的にはBの方が有効と判断されました。なお療法食Aはヒルズの「Hill’s Prescription Diet i/d Feline」、Bはピュリナの「Veterinary Diets EN Gastroenteric Feline Formula」です。
 :Laflamme, 2012)。給餌試験期間の最後の1週間で便スコア1(極度に乾いて硬い)~7(極度にゆるく水様)を毎日記録し、その後フードを入れ替えてさらに4週間の試験を設けた結果、最終的に15頭が完了したといいます。
:Laflamme, 2012)。給餌試験期間の最後の1週間で便スコア1(極度に乾いて硬い)~7(極度にゆるく水様)を毎日記録し、その後フードを入れ替えてさらに4週間の試験を設けた結果、最終的に15頭が完了したといいます。便スコアに関してはどちらのフードも改善を見せましたが、1ポイント以上改善した割合はAが40%でBが67%、スコアが正常(3以上)の割合はAが13.3%でBが46.7%で、総合的にはBの方が有効と判断されました。なお療法食Aはヒルズの「Hill’s Prescription Diet i/d Feline」、Bはピュリナの「Veterinary Diets EN Gastroenteric Feline Formula」です。
療法食/エビデンスグレード2
慢性的な嘔吐(25頭)や下痢(3頭)を主症状とする非特異的な胃腸障害を示す28頭の猫たちをランダムで2つのグループに分け、ドライタイプの療法食AもしくはBのどちらか一方だけを4週間に渡って給餌しました( :Perale, 2017)。
:Perale, 2017)。
その結果、嘔吐の週平均回数はどちらのグループも減少し、フード間に違いはなかったといいます。給餌試験前の週平均嘔吐回数が2.5回だった療法食Aグループに関しては、2週目の減少率が69.1%、3週目が73.3%、4週目が63.2%となり、統計的に有意な減少と判断されました。なお療法食Aはアイムスの「Veterinary Formula™ Intestinal Plus Low-Residue™ 」、Bはヒルズの「Prescription Diet® i/d® Feline Gastrointestinal Health」です。
 :Perale, 2017)。
:Perale, 2017)。その結果、嘔吐の週平均回数はどちらのグループも減少し、フード間に違いはなかったといいます。給餌試験前の週平均嘔吐回数が2.5回だった療法食Aグループに関しては、2週目の減少率が69.1%、3週目が73.3%、4週目が63.2%となり、統計的に有意な減少と判断されました。なお療法食Aはアイムスの「Veterinary Formula™ Intestinal Plus Low-Residue™ 」、Bはヒルズの「Prescription Diet® i/d® Feline Gastrointestinal Health」です。
療法食/エビデンスグレード3
炎症性腸疾患(IBD)もしくは食物反応性腸疾患(FRE)と診断された23頭を対象とし、IBDグループ(17頭)には除去食とプレドニゾロン、FREグループ(6頭)には除去食のみを用いて21日の医療的介入を行ない、前後において疾患の活動性指標である「FCEAI」を測定しました( : Jergens, 2010)。
: Jergens, 2010)。
その結果、IBDでは8.2→0.4、FREでは6.7→0と、どちらのグループでも統計的に有意なレベルで低下(=改善)が確認されたといいます。なお使用された除去食はロイヤルカナンの「IVD feline Neutral formula」「IVD feline Sensitivity formula」「IVD feline Green Pea and Duck formula」のいずれかです。
 : Jergens, 2010)。
: Jergens, 2010)。その結果、IBDでは8.2→0.4、FREでは6.7→0と、どちらのグループでも統計的に有意なレベルで低下(=改善)が確認されたといいます。なお使用された除去食はロイヤルカナンの「IVD feline Neutral formula」「IVD feline Sensitivity formula」「IVD feline Green Pea and Duck formula」のいずれかです。
除去食/エビデンスグレード3
特発性の消化器症状を示した55頭を対象とし、市販の除去食を用いた給餌試験を行った結果、16頭(29%)が食物反応性(除去食で改善+従来食で再発)と判断されましたが、別の11頭(20%)では除去食で改善が見られたものの従来食での再発が見られませんでした。また食物反応性を示した16頭のうち50%以上が複数の成分に反応し、25%では消化管症状に皮膚症状が併発するという特徴を有していました。症状としては大腸性下痢症が多く11頭では体重減少がみられたといいます。
投薬治療
投薬治療の目的は体内における抗原性を低下させたり免疫応答を減弱させることです。食事療法がうまく行かない場合や食事療法と並行する形で以下のような薬剤が用いられます。犬においてはたくさんの臨床試験が行われている一方、猫における調査報告は非常に少なく、エビデンスグレードもせいぜい3止まりです。
猫のIBD治療薬
- 抗炎症薬(糖質コルチコイド)プレドニゾロンなど/リンパ球・形質細胞炎や好酸球性炎症が見られる場合
- 免疫抑制剤シクロスポリンなど/T細胞によるIL-2の生成を抑制するが猫におけるエビデンスは弱い。体内に潜在しているヘルペスウイルスやトキソプラズマが免疫抑制によって再活性化するリスクあり
- 抗菌薬・抗原虫薬メトロニダゾールなど/原虫やクロストリジウム属に作用するが苦いので経口投与のコンプライアンスを保ちにくい。長期使用によりげっ歯類において発がん性、人間においてクローン病のリスクが示唆されているので要注意
- 抗がん剤クロラムブシルなど/小細胞性リンパ腫やリンパ腫との鑑別が難しい難治性のリンパ細胞性IBDの場合
便移植
人医学の領域で注目されている「糞便移植」を行ったところ、潰瘍性大腸炎の症状が軽減したという予備的な報告があります。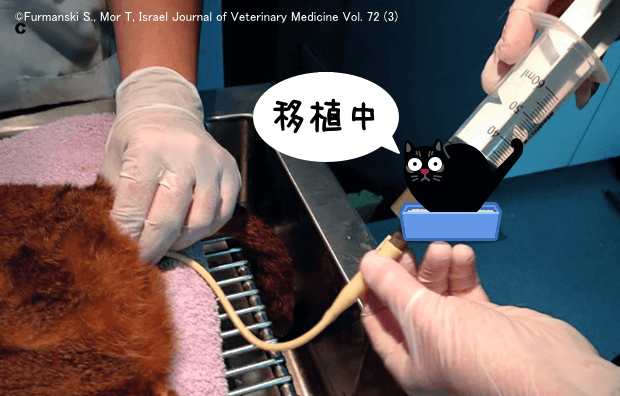 調査を行ったのはイスラエルにあるMedi-Vet Veterinary Hospital。11ヶ月間におよぶ慢性下痢に苦しむアビシニアン(10歳 | 2.9kg | 避妊済)に対して臨床上健康なメスの短毛種(3歳 | 6.2kg | 避妊済)から採取した便をフローラごと移植したところ、食事療法や投薬療法に反応しなかった症状が改善し、固形の便が出るようになったといいます。
調査を行ったのはイスラエルにあるMedi-Vet Veterinary Hospital。11ヶ月間におよぶ慢性下痢に苦しむアビシニアン(10歳 | 2.9kg | 避妊済)に対して臨床上健康なメスの短毛種(3歳 | 6.2kg | 避妊済)から採取した便をフローラごと移植したところ、食事療法や投薬療法に反応しなかった症状が改善し、固形の便が出るようになったといいます。
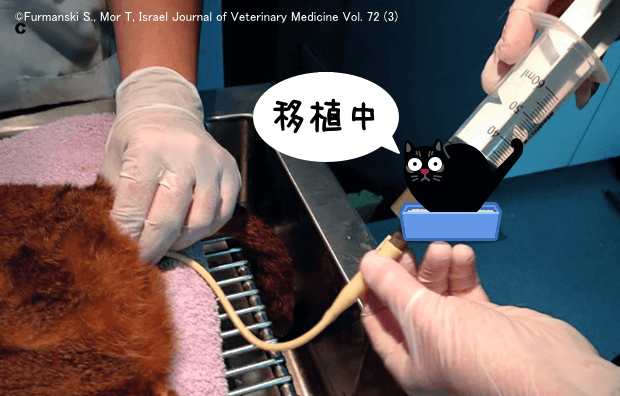 調査を行ったのはイスラエルにあるMedi-Vet Veterinary Hospital。11ヶ月間におよぶ慢性下痢に苦しむアビシニアン(10歳 | 2.9kg | 避妊済)に対して臨床上健康なメスの短毛種(3歳 | 6.2kg | 避妊済)から採取した便をフローラごと移植したところ、食事療法や投薬療法に反応しなかった症状が改善し、固形の便が出るようになったといいます。
調査を行ったのはイスラエルにあるMedi-Vet Veterinary Hospital。11ヶ月間におよぶ慢性下痢に苦しむアビシニアン(10歳 | 2.9kg | 避妊済)に対して臨床上健康なメスの短毛種(3歳 | 6.2kg | 避妊済)から採取した便をフローラごと移植したところ、食事療法や投薬療法に反応しなかった症状が改善し、固形の便が出るようになったといいます。
幹細胞治療
間葉系幹細胞を用いた治療法も試験的に行われています。
調査を行ったのはアメリカにあるコロラド州立大学・医療科学部の研究チーム。慢性腸疾患(IBDもしくは食物反応性腸疾患)を抱えた合計14頭の猫のうち10頭には脂肪細胞由来の幹細胞(100万MSC/kg)を、残りの4頭には偽薬を2週間間隔で2回ずつ注入し、開始から1ヶ月経過した時点で、猫の飼い主に対し糞便の状態に関するアンケート調査を行いました。その結果、治療グループにおいて顕著な改善が確認されたといいます。
調査を行ったのはアメリカにあるコロラド州立大学・医療科学部の研究チーム。慢性腸疾患(IBDもしくは食物反応性腸疾患)を抱えた合計14頭の猫のうち10頭には脂肪細胞由来の幹細胞(100万MSC/kg)を、残りの4頭には偽薬を2週間間隔で2回ずつ注入し、開始から1ヶ月経過した時点で、猫の飼い主に対し糞便の状態に関するアンケート調査を行いました。その結果、治療グループにおいて顕著な改善が確認されたといいます。
炎症性腸疾患(IBD)が長期化する理由は食事療法のコンプライアンス、投薬の失敗、共存症、不顕性疾患、誤診などです。薬に関しては日常的に経口投与する必要がありますので、やり方をしっかりマスターしておきましょう。