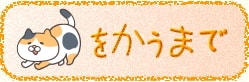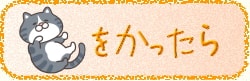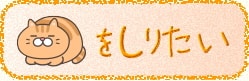尿道閉塞の病態・症状
尿道閉塞の疫学
英国王立獣医大学を中心としたチームは2016年1月1日~12月31日までの1年間、国内866ヶ所の一次診療施設を受診したオス猫237,825頭分のデータを後ろ向きに参照し、調査期間中に部分~全体の尿道閉塞と診断され、実際に排尿障害を示した症例を「ケース」と定義して発生リスク(特定の期間内に特定疾患を発症した総数から再発症例を除いた新規の症例数)を算出しました。その結果、0.54%(1,293症例)だったといいます。また診断時の年齢中央値は5歳で、4.5~9歳の年齢層で最もリスクが高く0.79%だったとも。
別の調査では尿道閉塞を発症した猫の平均月齢が51.7ヶ月齢だったのに対し、発症していない猫のそれは75.5ヶ月齢だったという報告されていることから、好発年齢は4~5歳くらいだと推測されます。これは尿道閉塞症の原因として多い特発性膀胱炎の好発年齢と連動した結果かもしれません( :Segev, 2011
)。
:Segev, 2011
)。
なおアメリカ北東部では4~5月における発生率リスクが高まるとの報告がありますが、同様の発症傾向が日本国内にも当てはまるのかどうかはわかっていません( :Summer, 2017)。
:Summer, 2017)。
 :Segev, 2011
)。
:Segev, 2011
)。なおアメリカ北東部では4~5月における発生率リスクが高まるとの報告がありますが、同様の発症傾向が日本国内にも当てはまるのかどうかはわかっていません(
 :Summer, 2017)。
:Summer, 2017)。
尿道閉塞の症状
尿道閉塞の原因
尿道閉塞を発症した猫45頭を対象とした調査では結石が29%、塞栓子が18%だったのに対し、特発性(=原因不明)が53%と過半数を占めていたと報告されています( :Gerber, 2008)。
:Gerber, 2008)。
 結石で多いのはストルバイト、塞栓子にはタンパク質を含んだ有機物質、血液細胞、結晶性ミネラルなどがあり、ほとんどのケースは尿道以外の尿路(腎臓や膀胱)で発生したものが尿道に流れ着いて目詰まりを起こします。
結石で多いのはストルバイト、塞栓子にはタンパク質を含んだ有機物質、血液細胞、結晶性ミネラルなどがあり、ほとんどのケースは尿道以外の尿路(腎臓や膀胱)で発生したものが尿道に流れ着いて目詰まりを起こします。
過去の文献で尿道閉塞の危険因子と考えられている項目は以下です。
 :Gerber, 2008)。
:Gerber, 2008)。
 結石で多いのはストルバイト、塞栓子にはタンパク質を含んだ有機物質、血液細胞、結晶性ミネラルなどがあり、ほとんどのケースは尿道以外の尿路(腎臓や膀胱)で発生したものが尿道に流れ着いて目詰まりを起こします。
結石で多いのはストルバイト、塞栓子にはタンパク質を含んだ有機物質、血液細胞、結晶性ミネラルなどがあり、ほとんどのケースは尿道以外の尿路(腎臓や膀胱)で発生したものが尿道に流れ着いて目詰まりを起こします。過去の文献で尿道閉塞の危険因子と考えられている項目は以下です。
尿道閉塞の危険因子
- 特発性膀胱炎?膀胱炎がタンパク質の漏出を招き塞栓子の核となる可能性があります。猫においては細菌性膀胱炎が少なく、多くは原因を特定できない特発性膀胱炎です。
- オス猫メスに比べオスの尿道が長いことから閉塞が起こりやすくなります。
- 完全室内飼い?屋外アクセスできる猫の方が発症リスクが低かったという報告があります。理由は定かではありませんが、屋外で排尿する機会が増えて結果として閉塞リスクが下がるからかもしれませんし、特発性膀胱炎の発症率と関わっているからかもしれません。
- 太り過ぎ・肥満2006年から2008年の期間、ヘブライ大学付属獣医教育病院において尿道閉塞症と診断された猫82頭を対象とした調査では、健常猫の平均体重が5.1kgだったのに対し患猫のそれは5.6kgだったといいます(
 :Segev, 2011)。体重が重く太り気味だと活動性が減少し、排尿回数が減ってリスクが上昇しするのかもしれません。またオーストリアで195頭の尿道閉塞猫を対象として行われた調査でも、猫の体重ではなくBCS(肥満度)と発生リスクが連動していたと報告されています(
:Segev, 2011)。体重が重く太り気味だと活動性が減少し、排尿回数が減ってリスクが上昇しするのかもしれません。またオーストリアで195頭の尿道閉塞猫を対象として行われた調査でも、猫の体重ではなくBCS(肥満度)と発生リスクが連動していたと報告されています( :Jukes, 2019)。これは体重が重い(=体格が大きい)こと自体がリスクではなく、標準体重より太っていることがリスクであることを意味しています。
:Jukes, 2019)。これは体重が重い(=体格が大きい)こと自体がリスクではなく、標準体重より太っていることがリスクであることを意味しています。 - フードがドライのみドライフードばかり食べていると飲水量が減り、排尿回数が減ってしまう可能性があります。
尿道閉塞の検査・診断
猫の尿道閉塞症では以下のような検査が行われます。
- 血液検査PCV(ヘマトクリット)、BUN(血清尿素チット)、クレアチニン、血糖、pH、各種電解質濃度などを調べます。主なスクリーニング対象は高カリウム血症、代謝性アシドーシス、高窒素血症、高リン血症、イオン化カルシウム濃度低下、高乳酸血症などです。
- 心電図検査高カリウム血症に伴う徐脈や不整脈をスクリーニングします。
- 尿検査/尿沈渣結晶尿、潜血、膿尿、細菌尿をスクリーニングします。
- エックス線検査腹部や鼠径部の結石の有無を確かめます。
- 膀胱穿刺感染症が強く疑われる場合は膀胱穿刺で尿を採取して培養します。
尿道閉塞の治療
輸液治療
生理食塩水のほかグルコン酸カルシウム(高カリウム血症や徐脈)、デキストロース(長引く高カリウム血症)、重炭酸ナトリウム(高カリウム血症)などを投与し、酸塩基平衡や血中カリウム濃度を調整して安定化を図ります。
膀胱穿刺
閉塞した尿道の開放
オスの性器の先端にまで塞栓子が出てきている場合は軽く補助するだけで自然排出されることがありますが、その他のケースでは部分閉塞であれ完全閉塞であれ、積極的に閉塞を解除して尿道を確保しなければなりません。
結石による閉塞の場合
ACVIM(米国獣医内科学会)が2016年に公開した犬と猫における結石症の治療ガイドラインでは、結石を尿道からいったん膀胱内に押し戻し、バスケット回収術や経皮的膀胱切石術など侵襲性が最小限になるような方法で対処することが推奨されています( :ACVIM, 2016)。
:ACVIM, 2016)。
 結石が頻繁に再発するようなケースでは尿道造瘻術の有効性が示されていますが、尿道に対する外科手術では尿道閉塞、尿漏れ、再発性の尿道感染症、出血など共存性や副作用の報告が数多くあるため、よほど切羽詰まった状況以外では推奨されません。
結石が頻繁に再発するようなケースでは尿道造瘻術の有効性が示されていますが、尿道に対する外科手術では尿道閉塞、尿漏れ、再発性の尿道感染症、出血など共存性や副作用の報告が数多くあるため、よほど切羽詰まった状況以外では推奨されません。
結石の成分がストルバイト(リン+マグネシウム+アンモニア)である場合、溶解成分を含んだ尿と広範囲+長時間に渡って接触させることができれば体内で溶かすことができます。しかし結石が尿道に引っかかっている場合、接触面積も接触時間も不十分となりますので、食事療法では閉塞を解除できません。
 :ACVIM, 2016)。
:ACVIM, 2016)。
 結石が頻繁に再発するようなケースでは尿道造瘻術の有効性が示されていますが、尿道に対する外科手術では尿道閉塞、尿漏れ、再発性の尿道感染症、出血など共存性や副作用の報告が数多くあるため、よほど切羽詰まった状況以外では推奨されません。
結石が頻繁に再発するようなケースでは尿道造瘻術の有効性が示されていますが、尿道に対する外科手術では尿道閉塞、尿漏れ、再発性の尿道感染症、出血など共存性や副作用の報告が数多くあるため、よほど切羽詰まった状況以外では推奨されません。結石の成分がストルバイト(リン+マグネシウム+アンモニア)である場合、溶解成分を含んだ尿と広範囲+長時間に渡って接触させることができれば体内で溶かすことができます。しかし結石が尿道に引っかかっている場合、接触面積も接触時間も不十分となりますので、食事療法では閉塞を解除できません。
閉塞が結石以外の場合
尿道閉塞の原因が結石以外の場合、麻酔を施した上で逆行性もしくは順行性のカテーテル挿入が行われます。具体的な適応例は尿道の悪性腫瘍(移行上皮癌・前立腺がん・平滑筋腫)、骨盤内リンパ節腫脹による外側から尿道への圧力、尿道外傷、手術、反射性協調運動障害、増殖性尿道炎に関連した良性閉塞などです( :M.W.Beal, 2018)。
:M.W.Beal, 2018)。
 カテーテル挿入にはカテーテルで排尿後すぐに外すパターンと、留置型カテーテルを12時間くらい継続的に装着するパターンがあります。英国王立獣医大学が行った調査では、留置型カテーテルを使用した場合、カテーテルを取り除いてから、もしくは退院してから48時間以内の再設置率が低い(10.1%:14.8%)という特徴が報告されています。一方、長時間のカテーテル使用が尿道炎の原因になるという懸念もあることから、どちらの治療パターンがよいのかははっきりとわかっていません。目安としては重度の高窒素血症、重度の膀胱膨張、膀胱結石が見られるときに留置型を用いるというものがあります(
カテーテル挿入にはカテーテルで排尿後すぐに外すパターンと、留置型カテーテルを12時間くらい継続的に装着するパターンがあります。英国王立獣医大学が行った調査では、留置型カテーテルを使用した場合、カテーテルを取り除いてから、もしくは退院してから48時間以内の再設置率が低い(10.1%:14.8%)という特徴が報告されています。一方、長時間のカテーテル使用が尿道炎の原因になるという懸念もあることから、どちらの治療パターンがよいのかははっきりとわかっていません。目安としては重度の高窒素血症、重度の膀胱膨張、膀胱結石が見られるときに留置型を用いるというものがあります( :C.M.George, 2016)。なお尿道閉塞を解除した後、カテーテルを留置した75頭の猫を対象とした調査では、平均42時間で入院期間は3.5日でした(
:C.M.George, 2016)。なお尿道閉塞を解除した後、カテーテルを留置した75頭の猫を対象とした調査では、平均42時間で入院期間は3.5日でした( :Segev, 2010)。
:Segev, 2010)。
 :M.W.Beal, 2018)。
:M.W.Beal, 2018)。
 カテーテル挿入にはカテーテルで排尿後すぐに外すパターンと、留置型カテーテルを12時間くらい継続的に装着するパターンがあります。英国王立獣医大学が行った調査では、留置型カテーテルを使用した場合、カテーテルを取り除いてから、もしくは退院してから48時間以内の再設置率が低い(10.1%:14.8%)という特徴が報告されています。一方、長時間のカテーテル使用が尿道炎の原因になるという懸念もあることから、どちらの治療パターンがよいのかははっきりとわかっていません。目安としては重度の高窒素血症、重度の膀胱膨張、膀胱結石が見られるときに留置型を用いるというものがあります(
カテーテル挿入にはカテーテルで排尿後すぐに外すパターンと、留置型カテーテルを12時間くらい継続的に装着するパターンがあります。英国王立獣医大学が行った調査では、留置型カテーテルを使用した場合、カテーテルを取り除いてから、もしくは退院してから48時間以内の再設置率が低い(10.1%:14.8%)という特徴が報告されています。一方、長時間のカテーテル使用が尿道炎の原因になるという懸念もあることから、どちらの治療パターンがよいのかははっきりとわかっていません。目安としては重度の高窒素血症、重度の膀胱膨張、膀胱結石が見られるときに留置型を用いるというものがあります( :C.M.George, 2016)。なお尿道閉塞を解除した後、カテーテルを留置した75頭の猫を対象とした調査では、平均42時間で入院期間は3.5日でした(
:C.M.George, 2016)。なお尿道閉塞を解除した後、カテーテルを留置した75頭の猫を対象とした調査では、平均42時間で入院期間は3.5日でした( :Segev, 2010)。
:Segev, 2010)。
支持療法
即時タイプであれ留置タイプであれ、カテーテル挿入を行った後は安定した状態を維持するための支持療法が行われます。また何らかの事情(飼い主の経済的事情/尿道を傷つける危険性を回避 etc)でカテーテル治療を見送った場合も、状態の悪化を防ぐために支持療法が行われます。例えば尿道閉塞と診断され、代謝の乱れや尿路結石を抱えていないことが確認されたオス猫15頭を対象とした調査では、神経遮断薬、鎮痛薬、筋弛緩薬、除圧を目的とした膀胱穿刺、輸液を施してストレスを排除した静かな環境においた結果、73%(11/15)で72時間以内の自発的な排尿とそれに続く退院が達せられたといいます( :Cooper, 2010)。
:Cooper, 2010)。
投薬治療の効果に関しては医学的な証拠(エビデンス)が強固に揃っているという状況ではありませんので、獣医師が漫然と何らかの薬を処方するケースも少なくありません。 :Cooper, 2015)。
:Cooper, 2015)。
 :Cooper, 2010)。
:Cooper, 2010)。投薬治療の効果に関しては医学的な証拠(エビデンス)が強固に揃っているという状況ではありませんので、獣医師が漫然と何らかの薬を処方するケースも少なくありません。
尿道閉塞に対する支持療法
- カテーテルの保持
- 術後の尿量増加に対応
- 輸液
- カリウム補液
- 筋弛緩剤
- 鎮痛薬
- 尿培養の結果次第で抗菌剤
 :Cooper, 2015)。
:Cooper, 2015)。
尿道閉塞の再発率
- 24時間以内=11%
- 30日以内=14.7%~24%
- 6ヶ月以内=22%~35%
- 2年以内=24%
- 3年以内=36%
予後
2006年から2008年の期間、ヘブライ大学付属獣医教育病院において尿道閉塞症と診断された猫82頭を対象とした調査では、追跡可能だった71頭のうち死亡症例が6例(8.5%)だけだったといいます( :Segev, 2011)。一方、英国王立獣医大学が1,108症例を対象として行った調査では死亡症例が32.5%(360頭)にも達したと報告されています。具体的には死亡360症例中、329症例(91.4%)では寛解や治癒を見ることのない発症中の死亡で、内訳は安楽死が86.6%(285/329)、自然死が11.9%(39/329)でした。
:Segev, 2011)。一方、英国王立獣医大学が1,108症例を対象として行った調査では死亡症例が32.5%(360頭)にも達したと報告されています。具体的には死亡360症例中、329症例(91.4%)では寛解や治癒を見ることのない発症中の死亡で、内訳は安楽死が86.6%(285/329)、自然死が11.9%(39/329)でした。
こうしたデータから死亡症例の割合には自然死よりも安楽死が大きく関わっていることがうかがえます。決断が獣医師の勧めによって行われたのか、それとも飼い主が自主的に行ったのかはわかりませんが、尿道閉塞(結石)症は「不治の病だから諦めるしかない!」という病気ではありません。情報不足の状態で命に関わる重大な決定を下して後悔しないよう、事前に下調べしておくことを強くお勧めします。
 :Segev, 2011)。一方、英国王立獣医大学が1,108症例を対象として行った調査では死亡症例が32.5%(360頭)にも達したと報告されています。具体的には死亡360症例中、329症例(91.4%)では寛解や治癒を見ることのない発症中の死亡で、内訳は安楽死が86.6%(285/329)、自然死が11.9%(39/329)でした。
:Segev, 2011)。一方、英国王立獣医大学が1,108症例を対象として行った調査では死亡症例が32.5%(360頭)にも達したと報告されています。具体的には死亡360症例中、329症例(91.4%)では寛解や治癒を見ることのない発症中の死亡で、内訳は安楽死が86.6%(285/329)、自然死が11.9%(39/329)でした。こうしたデータから死亡症例の割合には自然死よりも安楽死が大きく関わっていることがうかがえます。決断が獣医師の勧めによって行われたのか、それとも飼い主が自主的に行ったのかはわかりませんが、尿道閉塞(結石)症は「不治の病だから諦めるしかない!」という病気ではありません。情報不足の状態で命に関わる重大な決定を下して後悔しないよう、事前に下調べしておくことを強くお勧めします。
下部尿路症候群の症状をいち早く気づくことができれば早期発見・早期治療に繋がり、尿道閉塞に伴う死亡率も下がります。
 閉塞には尿道の内部に原因(炎症・腫瘍・狭窄)があるパターン、尿道の外から圧迫を受けて管腔が狭くなるパターン、尿道以外の器官から塞栓子が流れ着いて目詰まりを起こすパターンなどがあります。いずれにしても正常な尿の流れがせき止められて
閉塞には尿道の内部に原因(炎症・腫瘍・狭窄)があるパターン、尿道の外から圧迫を受けて管腔が狭くなるパターン、尿道以外の器官から塞栓子が流れ着いて目詰まりを起こすパターンなどがあります。いずれにしても正常な尿の流れがせき止められて