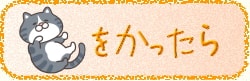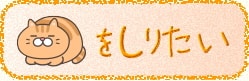詳細
王立獣医大学のチームは、イギリス国内で一次診療を行う獣医師から電子医療データを集め、猫の品種、年齢、性別、保険の加入状態、体重といった統計学データと糖尿病との関連性を精査しました。調査対象となったのは、2009年9月~2014年8月の期間、調査に同意した118の動物病院を受診した合計194,563頭の猫。そのうち糖尿病の有病率は「0.58%」(1,128頭)で、調査前の時点で診断が付いていた症例が「44.7%」(504頭)、調査期間中に新たに診断された症例が「55.3%」(624頭)だったと言います。その他、糖尿病の発症率を高めていると思われる危険因子として、以下のような項目が指摘されました。なおオッズ比とは基準を「1」としたときの危険度のことで、数字が大きいほど危険という意味です。


 上記した他では、「オス猫がメス猫の1.6倍」、「保険加入猫が未加入猫の2倍」というオッズ比が明らかになりました。
Epidemiology of Diabetes Mellitus among 193,435 Cats Attending Primary-Care Veterinary Practices in England
上記した他では、「オス猫がメス猫の1.6倍」、「保険加入猫が未加入猫の2倍」というオッズ比が明らかになりました。
Epidemiology of Diabetes Mellitus among 193,435 Cats Attending Primary-Care Veterinary Practices in England
O'Neill, D.G., Gostelow, R., et al.
品種(オッズ比 | 有病率)
- トンキニーズ=4.1 | 2.17%
- N.フォレストキャット=3.5 | 2.21%
- バーミーズ=3.0 | 2.27%
- ロシアンブルー=2.5 | 0.93%
- オリエンタル=1.8 | 0.96%
- レックス=1.2 | 0.56%
- シャム=1.1 | 0.49%
- ミックス=1.0 | 0.58%
- メインクーン=0.9 | 0.56%
- エキゾチックショートヘア=0.8 | 0%
- バーマン=0.8 | 0.27%
- その他=0.6 | 0.47%
- ブリティシュショートヘア=0.5 | 0.24%
- ペルシャ=0.5 | 0.28%
- ラグドール=0.4 | 0.24%
- ベンガル=0.3 | 0.24%

体重(オッズ比)
- 3kg未満=1
- 3.0~3.9kg=1.4
- 4.0~4.9kg=3.2
- 5.0~5.9kg=5.1
- 6.0~6.9kg=10.2
- 7.0~7.9kg=19.3
- 8.0kg以上=20

年齢(オッズ比)
- 3.0歳未満 =0.4
- 3.0~5.9歳=1
- 6.0~8.9歳=5.6
- 9.0~11.9歳=17.1
- 12.0~14.9歳=31.8
- 15.0歳以上=39.1
 上記した他では、「オス猫がメス猫の1.6倍」、「保険加入猫が未加入猫の2倍」というオッズ比が明らかになりました。
Epidemiology of Diabetes Mellitus among 193,435 Cats Attending Primary-Care Veterinary Practices in England
上記した他では、「オス猫がメス猫の1.6倍」、「保険加入猫が未加入猫の2倍」というオッズ比が明らかになりました。
Epidemiology of Diabetes Mellitus among 193,435 Cats Attending Primary-Care Veterinary Practices in EnglandO'Neill, D.G., Gostelow, R., et al.

解説
今回の調査はイギリスで行われたものですが、日本に暮らしている猫の飼い主にとっても重要な情報がいくつか含まれています。
- 糖尿病を発症しやすい品種がある
- 猫を太らせてはいけない
- 6歳を境に急激に有病率が高まる
品種
過去にイギリス、ヨーロッパ、オーストラリアで行われた調査ではバーミーズの有病率が高いと報告されています。またスウェーデンで行われた別の調査では、ノルウェージャンフォレストキャットやロシアンブルー、アビシニアンで高く、ペルシアで低いと報告されています。今回の調査ではトンキニーズという新しい品種の報告がなされました。この背景には1950年代、発症リスクが高いバーミーズとシャムの血統を用いて作出されたという歴史が関係しているようです。ちなみにバーミーズは、太っているわけではないのに、なぜか体内のアディポカインや脂質代謝物異常が肥満猫と同レベルだったといいます。つまり「やせているのに糖尿病にかかりやすい」という意味です。
遺伝性
人間の2型糖尿病の発症にはおよそ70種類の遺伝子が関わっており、細胞のインスリン抵抗性が変化することで発症のリスクが高まるものと推測されています。一方、肥満猫を対象とした調査では、メラノコルチン4受容体遺伝子における変異(SNP)が糖尿病の発症に関わっているのではないかと推測されています。猫の糖尿病はほとんどが2型であることから、人間の2型発症メカニズムと何らかの共通点があると考えられていますが、詳しい事はまだわかっていません。
体重
体重が増えれば増えるほど発症リスクも高まるという関連性が見いだされました。しかしこのことは「大柄な品種ほど発症しやすい」という事実ではなく、「太った猫ほど発症しやすい」という事実を反映しているものと推測されます。現に、体が大きいことで知られるメインクーンのオッズ比は「0.9」と基準値よりも低いままです。
肥満と糖尿病との因果関係としては、「肥満による脂肪細胞の慢性的な炎症→アディポカインの増減→インスリン抵抗性の変化→糖尿病」といったものが想定されています。「アディポカイン」とは脂肪細胞から産生・分泌される生理活性物質の総称で、代表例は「レプチン」や「アディポネクチン」です。肥満によって「レプチン」が分泌過剰になると、体がレプチンに対して鈍感になり、「エネルギーの利用促進」や「満腹感の増進」といった生理作用が減弱します。また「アディポネクチン」が減少すると、「インスリン抵抗性改善作用」や「抗炎症作用」が減弱します。こうしたメカニズムを通して糖尿病の発症リスクが高まるものと推測されています。
また「先端肥大症」(アクロメガリ)と呼ばれる全く別の病気が体重と糖尿病の関連性に影響を及ぼしている可能性もあります。この病気はインスリンの働きを邪魔する「成長ホルモン」(GH)によって高血糖になってしまうというもので、イギリス国内では糖尿病を発症した猫のうち25%がこの疾患にかかっていると言われています。先端肥大症の特徴として「体が大きくなる」というものがありますので、肥満ではなく当症による病的な体の肥大が「体重増加→糖尿病の有病率増加」というつながりの背景にあるのかもしれません。
肥満と糖尿病との因果関係としては、「肥満による脂肪細胞の慢性的な炎症→アディポカインの増減→インスリン抵抗性の変化→糖尿病」といったものが想定されています。「アディポカイン」とは脂肪細胞から産生・分泌される生理活性物質の総称で、代表例は「レプチン」や「アディポネクチン」です。肥満によって「レプチン」が分泌過剰になると、体がレプチンに対して鈍感になり、「エネルギーの利用促進」や「満腹感の増進」といった生理作用が減弱します。また「アディポネクチン」が減少すると、「インスリン抵抗性改善作用」や「抗炎症作用」が減弱します。こうしたメカニズムを通して糖尿病の発症リスクが高まるものと推測されています。
また「先端肥大症」(アクロメガリ)と呼ばれる全く別の病気が体重と糖尿病の関連性に影響を及ぼしている可能性もあります。この病気はインスリンの働きを邪魔する「成長ホルモン」(GH)によって高血糖になってしまうというもので、イギリス国内では糖尿病を発症した猫のうち25%がこの疾患にかかっていると言われています。先端肥大症の特徴として「体が大きくなる」というものがありますので、肥満ではなく当症による病的な体の肥大が「体重増加→糖尿病の有病率増加」というつながりの背景にあるのかもしれません。
年齢
6歳を超えた猫で発症リスクが高まるという事実は、加齢とともに2型糖尿病の有病率が高まるという人医学における現象と同じです。加齢に伴って細胞のインスリン抵抗性が変化したり(2型の場合)、アミロイドの膵臓蓄積によって膵β細胞の機能が変化したり(1型の場合)することと関係しているのではないかと推測されています。また、特に猫では加齢とともに有病率が高まる先端肥大症や副腎皮質機能亢進症が関係している可能性も否定できません。ちなみに日本の保険会社が行った統計調査でも、6歳を境に急激に有病率が高まります。
保険
保険に加入している猫では2倍発症しやすいという事実が明らかになりました。しかしこのことは「保険に入ったから糖尿病を発症しやすくなった」という因果関係ではなく、保険に入っている飼い主はそもそも猫の健康に対する意識が高く、また経済的に余裕がある人が多いため、病院を受診する機会が多いだけだと推定されています。猫の健康に無頓着で、ブクブクと太らせているような飼い主を統計データに含めると、また違った結果になるでしょう。
性別
オス猫はメス猫よりも1.6倍発症しやすいという事実が明らかになりました。この背景にはオス猫の方が太りやすく、また先端肥大症を発症しやすい(発症例の9割はオス猫)という事実があるようです。ちなみにオス猫の平均体重が4.8kgだったのに対し、メス猫の平均体重は3.8kgでした。