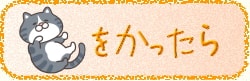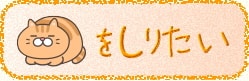猫の原発性アルドステロン症の病態と症状
原発性アルドステロン症とは、腎臓の近くにある副腎と呼ばれる組織の皮質部分からアルドステロン(aldosterone)と呼ばれるホルモンの一種が自律的に分泌されることで引き起こされる内分泌系疾患のことです。
 人医学の領域では1955年にジェローム・コンによって最初に報告されたことから「コン症候群」と呼ばれることもあります。同じく副腎の病気であるクッシング症候群が糖質コルチコイドの過剰分泌であるのに対し、当症は鉱質コルチコイドの過剰分泌という違いがあり、猫における最初の報告は1983年とかなり最近です(
人医学の領域では1955年にジェローム・コンによって最初に報告されたことから「コン症候群」と呼ばれることもあります。同じく副腎の病気であるクッシング症候群が糖質コルチコイドの過剰分泌であるのに対し、当症は鉱質コルチコイドの過剰分泌という違いがあり、猫における最初の報告は1983年とかなり最近です( :Shiel, 2007)。
:Shiel, 2007)。
心不全、腎不全、肝不全など全く別の疾患によってアルドステロンの過剰分泌が引き起こされた状態を「二次性」のアルドステロン症と呼ぶのに対し、副腎皮質自体に病変が生じて過剰分泌が引き起こされた状態を「原発性」のアルドステロン症と呼びます。 アルドステロンは体内において腎臓の遠位尿細管におけるナトリウムの再吸収を促進し、体液を保持するといった役割を担っていますので、このホルモンが過剰に分泌されると体液貯留による高血圧や、カリウムの過剰喪失による低カリウム血症といった病的な変化が引き起こされます。結果として現れる主な症状は以下です( :Laanen, 2011)。
:Laanen, 2011)。
厄介なのは、腎不全が原発性アルドステロン症によって引き起こされた二次的な疾患である場合です。例えばアルドステロン症→慢性高血圧→腎血管の線維化や硬化→慢性腎不全といったメカニズムを通して発症している場合、治療ターゲットは腎不全ではなくアルドステロン症に絞り込まなければなりません。二次的に引き起こされた疾患にアプローチしても根本的な原因は解決しませんので、動脈性の高血圧や低カリウム血症が治療に反応しない場合は、常に原発性のアルドステロン症を疑い、治療方針を適宜変更することが推奨されています( :Fernandez, 2016)。
:Fernandez, 2016)。
 人医学の領域では1955年にジェローム・コンによって最初に報告されたことから「コン症候群」と呼ばれることもあります。同じく副腎の病気であるクッシング症候群が糖質コルチコイドの過剰分泌であるのに対し、当症は鉱質コルチコイドの過剰分泌という違いがあり、猫における最初の報告は1983年とかなり最近です(
人医学の領域では1955年にジェローム・コンによって最初に報告されたことから「コン症候群」と呼ばれることもあります。同じく副腎の病気であるクッシング症候群が糖質コルチコイドの過剰分泌であるのに対し、当症は鉱質コルチコイドの過剰分泌という違いがあり、猫における最初の報告は1983年とかなり最近です( :Shiel, 2007)。
:Shiel, 2007)。心不全、腎不全、肝不全など全く別の疾患によってアルドステロンの過剰分泌が引き起こされた状態を「二次性」のアルドステロン症と呼ぶのに対し、副腎皮質自体に病変が生じて過剰分泌が引き起こされた状態を「原発性」のアルドステロン症と呼びます。 アルドステロンは体内において腎臓の遠位尿細管におけるナトリウムの再吸収を促進し、体液を保持するといった役割を担っていますので、このホルモンが過剰に分泌されると体液貯留による高血圧や、カリウムの過剰喪失による低カリウム血症といった病的な変化が引き起こされます。結果として現れる主な症状は以下です(
 :Laanen, 2011)。
:Laanen, 2011)。
原発性アルドステロン症の症状
- 高血圧による症状眼球内出血・網膜浮腫・網膜剥離・視野の欠損・突然の失明

- 低カリウム血症による症状血漿カリウム濃度が2.5mmol/L付近になると筋細胞の過分極が引き起こされ、正常に収縮できなくなって筋力が低下する。2.0mmol/L未満になると横紋筋融解症や虚血性の筋壊死が引き起こされ、クレアチンキナーゼ濃度が増加する。その結果↓
荷重不全(足がふらふら)・ジャンプができない・うなだれ姿勢・呼吸不全・筋肉の萎縮・食欲不振・慢性の下痢・多尿
厄介なのは、腎不全が原発性アルドステロン症によって引き起こされた二次的な疾患である場合です。例えばアルドステロン症→慢性高血圧→腎血管の線維化や硬化→慢性腎不全といったメカニズムを通して発症している場合、治療ターゲットは腎不全ではなくアルドステロン症に絞り込まなければなりません。二次的に引き起こされた疾患にアプローチしても根本的な原因は解決しませんので、動脈性の高血圧や低カリウム血症が治療に反応しない場合は、常に原発性のアルドステロン症を疑い、治療方針を適宜変更することが推奨されています(
 :Fernandez, 2016)。
:Fernandez, 2016)。
猫の原発性アルドステロン症の原因
原発性アルドステロン症は人間でもよくみられる疾患で、原因としては副腎皮質球状層の両側性過形成が60~65%、腺腫が30~35%で片側性の過形成や副腎皮質ガンはまれとされています。一方、猫においては
副腎皮質ガン>片側~両側性の腺腫>両側性の結節過形成の順で多いとされていますので、人間とは発症メカニズムが少し違うようです。
原発性アルドステロン症と診断された34頭を対象とした調査では、年齢中央値が13歳(平均年齢は12.4歳)で5歳から20歳までと幅広く、性別や品種による発症リスクに偏りはないとされています。基本的にはかなりの高齢猫で発症する疾患ですので、「加齢」が原因とも言えるでしょう。
原発性アルドステロン症と診断された34頭を対象とした調査では、年齢中央値が13歳(平均年齢は12.4歳)で5歳から20歳までと幅広く、性別や品種による発症リスクに偏りはないとされています。基本的にはかなりの高齢猫で発症する疾患ですので、「加齢」が原因とも言えるでしょう。
猫の原発性アルドステロン症の検査・診断
猫におけるアルドステロン症の検査や診断法は確立していません。以下は比較的価値が高いとされる検査法です。
画像診断
猫の副腎に腫瘤ができている場合、腹部の超音波検査、CTスキャン、MRIなどで病変を確認できることがあります。その場合、副腎が肥大して10~46mmになるとされています。
 人間においては右と左の副腎血管から血液を採取し、アルドステロン濃度を比較することで病変部がどちらにあるのかを確定しますが、猫では体が小さすぎて技術的に困難なため、片側性に関しては画像診断に頼るしかありません。しかし腫瘤があってもアルドステロンを分泌していないことがあったり、腫瘤がなくてもアルドステロンの過剰分泌が潜在していることがあるため、100%の精度からは程遠いというのが現状です。
人間においては右と左の副腎血管から血液を採取し、アルドステロン濃度を比較することで病変部がどちらにあるのかを確定しますが、猫では体が小さすぎて技術的に困難なため、片側性に関しては画像診断に頼るしかありません。しかし腫瘤があってもアルドステロンを分泌していないことがあったり、腫瘤がなくてもアルドステロンの過剰分泌が潜在していることがあるため、100%の精度からは程遠いというのが現状です。
 人間においては右と左の副腎血管から血液を採取し、アルドステロン濃度を比較することで病変部がどちらにあるのかを確定しますが、猫では体が小さすぎて技術的に困難なため、片側性に関しては画像診断に頼るしかありません。しかし腫瘤があってもアルドステロンを分泌していないことがあったり、腫瘤がなくてもアルドステロンの過剰分泌が潜在していることがあるため、100%の精度からは程遠いというのが現状です。
人間においては右と左の副腎血管から血液を採取し、アルドステロン濃度を比較することで病変部がどちらにあるのかを確定しますが、猫では体が小さすぎて技術的に困難なため、片側性に関しては画像診断に頼るしかありません。しかし腫瘤があってもアルドステロンを分泌していないことがあったり、腫瘤がなくてもアルドステロンの過剰分泌が潜在していることがあるため、100%の精度からは程遠いというのが現状です。
血液検査
血液検査によって血中アルドステロン濃度やレニン活性を調べることにも診断的な価値があります。原発性の場合、アルドステロンは副腎の病変部から自分勝手に分泌されますので、血中のアルドステロン濃度の上昇は確認されるものの、アルドステロンの放出に関わるレニンと呼ばれる酵素の活性は正常範囲のままです。一方、二次性の場合、アルドステロンの分泌はレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)の調整を受けますので、アルドステロン濃度の上昇とレニン活性の上昇が同時に観察されます( :Javadi, 2005)。
:Javadi, 2005)。
しかし血液検査に際しては、4mLの血液を複数回に分けて採取する必要があり、なおかつ冷却した状態で検査ラボにまで持っていく必要がありますので、お金と時間がかかります。血液検査に代わる方法としては尿検査でアルドステロン:クレアチニン比率を調べるというものがありますが、猫における参照値(正常範囲)が確定しておらず、健常猫との境目がはっきりしないため診断的な価値はそれほどありません。
 :Javadi, 2005)。
:Javadi, 2005)。しかし血液検査に際しては、4mLの血液を複数回に分けて採取する必要があり、なおかつ冷却した状態で検査ラボにまで持っていく必要がありますので、お金と時間がかかります。血液検査に代わる方法としては尿検査でアルドステロン:クレアチニン比率を調べるというものがありますが、猫における参照値(正常範囲)が確定しておらず、健常猫との境目がはっきりしないため診断的な価値はそれほどありません。
投薬試験
アルドステロン症が原発性か二次性かを区別する際は、レニンアンジオテンシン系の働きを抑制する薬を投与するという方法があります。健常猫では尿アルドステロン:クレアチニン比率が44~97%で低下したのに対し、肉腫を原因とする原発性アルドステロン症を抱えた猫では低下しなかったとの予備的な報告があります( :Laanen, 2008)。
:Laanen, 2008)。
しかし経口薬を4日連続で投与する必要がありますので、投薬ストレスは避けられないでしょう。人医学ではカプトプリル負荷試験や高張食塩水負荷試験といった代替試験がありますが、猫においては行われません。
 :Laanen, 2008)。
:Laanen, 2008)。 しかし経口薬を4日連続で投与する必要がありますので、投薬ストレスは避けられないでしょう。人医学ではカプトプリル負荷試験や高張食塩水負荷試験といった代替試験がありますが、猫においては行われません。
原発性アルドステロン症の治療
以下は猫の原発性アルドステロン症に対して行われる代表的な治療法です。
支持療法
症状が重い場合は取り急ぎ体の機能をサポートして悪化を防ぎます。具体的には運動制限と安静を徹底し、低カリウム血症を原因とする虚血性壊死の危険性を回避します。また筋肉の収縮力低下に伴う低体温がある場合は毛布をかけるなどして保温に努め、呼吸筋の弱化に伴う酸欠が見られる場合は酸素吸入などを行います。
外科手術
副腎の片方にだけ原因があると確定している場合は片側性の副腎切除術を行います。しかし17頭中8頭では周術期の副作用や合併症が生じたとされていますので、必ずしも安全なアプローチというわけではありません。特に腹腔内出血による死亡リスクが高いため、事前の血液検査と輸血用血液の用意が推奨されています。一方、17頭中8頭は術後少なくとも1年間は生存したといいますので、ハイリスクハイリターンな選択肢と言えます( :Laanen, 2011)。
:Laanen, 2011)。
別の調査では、副腎切除術を受けた26頭のうち術後2週間生存が確認されたのは20頭(77%)で、死亡した6頭の死因は術後の出血(1頭)、急性腎障害(1頭)、安楽死(4頭)だったと報告されています。また術中の出血により緊急の輸血が必要になった症例が7ケースもあったとのこと。術後に死亡が確認された8頭の猫たちの生存期間中央値は50週間(平均値は61週間)で、残りの6頭に関しては52~530週間生きたそうです( :Daniel, 2015)。
:Daniel, 2015)。
 :Laanen, 2011)。
:Laanen, 2011)。別の調査では、副腎切除術を受けた26頭のうち術後2週間生存が確認されたのは20頭(77%)で、死亡した6頭の死因は術後の出血(1頭)、急性腎障害(1頭)、安楽死(4頭)だったと報告されています。また術中の出血により緊急の輸血が必要になった症例が7ケースもあったとのこと。術後に死亡が確認された8頭の猫たちの生存期間中央値は50週間(平均値は61週間)で、残りの6頭に関しては52~530週間生きたそうです(
 :Daniel, 2015)。
:Daniel, 2015)。