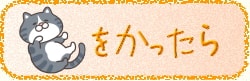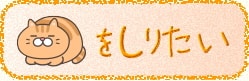動脈血栓塞栓症の病態と症状
動脈血栓塞栓症とは体内のどこかで血液が固まって血栓を形成し、血流に乗って全身をめぐるうちに血管内に詰まってしまった状態のことです。英語の「Feline Arterial Thromboembolism」の頭文字を取って「FATE」などとも呼ばれます。
最も多いパターンは大きな血栓が大動脈の分岐部で塞栓を起こし、両方の後ろ足への血流が途絶えてしまうというものです。腹部大動脈の三叉分岐部がちょうど乗馬に使う鞍(サドル)に見えることから「サドル血栓症」などとも呼ばれます。 猫の動脈血栓塞栓症で見られる症状は以下です。脈なし(pulselessness)、痛み(pain)、蒼白(pallor)、麻痺(paresis)、体温変化(poikilothermia)という英単語の頭文字を取って「5つのP」と呼ばれることもあります。
猫の動脈血栓塞栓症で見られる症状は以下です。脈なし(pulselessness)、痛み(pain)、蒼白(pallor)、麻痺(paresis)、体温変化(poikilothermia)という英単語の頭文字を取って「5つのP」と呼ばれることもあります。

 :Smith, 2003)。「イギリス」の方は2004年から2012年の期間、王立獣医大学が国内にある3つの動物病院(一次診療施設)の医療記録を回顧的に調べた動脈血栓塞栓症250症例が元になっています(
:Smith, 2003)。「イギリス」の方は2004年から2012年の期間、王立獣医大学が国内にある3つの動物病院(一次診療施設)の医療記録を回顧的に調べた動脈血栓塞栓症250症例が元になっています( :Borgeat, 2013)。全体の7割以上が両方の後ろ足に発症することがおわかりいただけるでしょう。
:Borgeat, 2013)。全体の7割以上が両方の後ろ足に発症することがおわかりいただけるでしょう。


最も多いパターンは大きな血栓が大動脈の分岐部で塞栓を起こし、両方の後ろ足への血流が途絶えてしまうというものです。腹部大動脈の三叉分岐部がちょうど乗馬に使う鞍(サドル)に見えることから「サドル血栓症」などとも呼ばれます。
 猫の動脈血栓塞栓症で見られる症状は以下です。脈なし(pulselessness)、痛み(pain)、蒼白(pallor)、麻痺(paresis)、体温変化(poikilothermia)という英単語の頭文字を取って「5つのP」と呼ばれることもあります。
猫の動脈血栓塞栓症で見られる症状は以下です。脈なし(pulselessness)、痛み(pain)、蒼白(pallor)、麻痺(paresis)、体温変化(poikilothermia)という英単語の頭文字を取って「5つのP」と呼ばれることもあります。
動脈血栓塞栓症の症状

- 突然の荷重不全
- 痛みの徴候
- 筋の硬結
- 脈の減弱~触知不能
- 肉球の変色(青白~チアノーゼ)
- 下肢が冷たい
- 直腸温低下
- ストレスに起因する高血糖
- 全身還流不全やショック
- 高窒素血症
猫の対麻痺
以下は塞栓による運動不全が発症しやすい部位です。「アメリカ」の方は1992年1月から2001年10月の期間、ミネソタ大学獣医療教育病院において診察を行った猫の動脈塞栓症127症例が元になっています( :Smith, 2003)。「イギリス」の方は2004年から2012年の期間、王立獣医大学が国内にある3つの動物病院(一次診療施設)の医療記録を回顧的に調べた動脈血栓塞栓症250症例が元になっています(
:Smith, 2003)。「イギリス」の方は2004年から2012年の期間、王立獣医大学が国内にある3つの動物病院(一次診療施設)の医療記録を回顧的に調べた動脈血栓塞栓症250症例が元になっています( :Borgeat, 2013)。全体の7割以上が両方の後ろ足に発症することがおわかりいただけるでしょう。
:Borgeat, 2013)。全体の7割以上が両方の後ろ足に発症することがおわかりいただけるでしょう。
アメリカ(127症例)

- 両後肢=71.7%
- 右前肢=7.1%
- 左後肢=6.3%
- 右後肢=6.3%
- 左前肢=4.7%
- 両後肢+片前肢=2.4%
- 四肢以外=1.6%
イギリス(250症例)

- 両後肢=77.6%
- 左後肢=6.0%
- 右後肢=6.0%
- 右前肢=4.8%
- 左前肢=4.0%
- 両後肢+片前肢=0.8%
- 四肢=0.4%
動脈血栓塞栓症の原因
血流のうっ滞
複数の調査により肥大型心筋症を抱えた猫の12~41%、うっ血性心不全を抱えた猫の40~66%が動脈血栓塞栓症を発症すると報告されています。また肥大型心筋症を患う猫の21%では、死後解剖時に左心室に血栓が見つかることから、血栓の形成場所は心臓の左側ではないかと考えられています。
心臓内で血栓が形成されるメカニズムはよく分かっていませんが、健康な猫と心筋症を抱えた猫の心臓における最高血流速度を計測したところ、それぞれ秒速0.46mと0.31mだったといいます。また左心室内に血栓を持っていたり動脈塞栓症を持つ猫では0.14mとさらに遅くなるとも。こうした事実から、肥大型心筋症によって心臓内でうっ血や心拍タービュランス(乱れ)が発生し、血液の凝固が促進されて血栓が形成されるなどの発症メカニズムが想定されます。
心臓内で血栓が形成されるメカニズムはよく分かっていませんが、健康な猫と心筋症を抱えた猫の心臓における最高血流速度を計測したところ、それぞれ秒速0.46mと0.31mだったといいます。また左心室内に血栓を持っていたり動脈塞栓症を持つ猫では0.14mとさらに遅くなるとも。こうした事実から、肥大型心筋症によって心臓内でうっ血や心拍タービュランス(乱れ)が発生し、血液の凝固が促進されて血栓が形成されるなどの発症メカニズムが想定されます。
血液凝集性の変化
心臓疾患を抱えた猫と臨床上健康な猫を比較したところ、患猫では高いアンチトロンビン濃度と低いプラスミノーゲン活性が確認されたといいます。こうした事実から、血小板の凝集性が複数の要因によって変化することで血栓ができやすくなるという可能性が指摘されています。
また肥大型心筋症の血筋に産まれた猫の75%でATEを発症したという報告があることから、血栓形成を促す何らかの遺伝的な要因があるものと推測されています。例えば人医学で確認されている凝固タンパクや血小板の不全などです( :Baty, 2008)。
:Baty, 2008)。
なお複数の調査において共通して報告されている猫の品種がいくつかあります。具体的にはアビシニアン、バーマン、ラグドールで、オッズ比(標準の発症リスク1としたときの相対リスク)に関しては順に6.03倍、10.52倍、14.4倍という推計が出されています( :Smith, 2003)。ラグドールとバーマンに関しては心疾患の発症リスクがそもそも高いため、連動して動脈血栓塞栓症のリスクも高まっている可能性が大です。アビシニアンにおけるハイリスクの理由はよくわかっていません。
:Smith, 2003)。ラグドールとバーマンに関しては心疾患の発症リスクがそもそも高いため、連動して動脈血栓塞栓症のリスクも高まっている可能性が大です。アビシニアンにおけるハイリスクの理由はよくわかっていません。
また肥大型心筋症の血筋に産まれた猫の75%でATEを発症したという報告があることから、血栓形成を促す何らかの遺伝的な要因があるものと推測されています。例えば人医学で確認されている凝固タンパクや血小板の不全などです(
 :Baty, 2008)。
:Baty, 2008)。なお複数の調査において共通して報告されている猫の品種がいくつかあります。具体的にはアビシニアン、バーマン、ラグドールで、オッズ比(標準の発症リスク1としたときの相対リスク)に関しては順に6.03倍、10.52倍、14.4倍という推計が出されています(
 :Smith, 2003)。ラグドールとバーマンに関しては心疾患の発症リスクがそもそも高いため、連動して動脈血栓塞栓症のリスクも高まっている可能性が大です。アビシニアンにおけるハイリスクの理由はよくわかっていません。
:Smith, 2003)。ラグドールとバーマンに関しては心疾患の発症リスクがそもそも高いため、連動して動脈血栓塞栓症のリスクも高まっている可能性が大です。アビシニアンにおけるハイリスクの理由はよくわかっていません。
血栓からのセロトニン?
腹部大動脈を人為的に結紮(けっさつ=きつく結ぶこと)しても完全に血流を分断することができず、また臨床症状も再現できないことから、動脈血栓塞栓症は何らかの別のメカニズムを通して発現するものと考えられています。セロトニンの投与により血管が収縮(狭窄)して虚血性の神経筋症状が再現され、セロトニン阻害剤によって症状の発現が予防されることから、血栓自体から放出されるセロトニンやトロンボキサンが、塞栓部周辺にある大小すべての血管に作用することで虚血性の症状が引き起こされている可能性が高いと考えられています。
動脈血栓塞栓症の検査・診断
動脈血栓塞栓症の検査・診断に際し、猫の肥満、診察時の暴れ、低血圧などの理由から大腿動脈の脈診は困難ですので、ドップラーを用いた動脈血流評価の方が有用です。
動脈血栓塞栓症の原因が心疾患にある場合、聴診では心雑音、ギャロップ、不整脈、心エコー検査では左心房の拡張終期径が1.7cm以上、左房大動脈比2.0以上、左心房のもやもやエコー(スモーク)など心筋症やうっ血の徴候が確認されます( :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。
塞栓症によって血流の途絶えた筋肉がダメージを受けると、血液検査において血清酵素値の上昇が見られます。例えば血清AST(GOT)値の上昇は83~99%、血清CPK(クレアチンホスホキナーゼ)の上昇は80~100%の割合で見られると言った報告もあります。末梢血では血糖値が低く乳酸値が高くなるという傾向もあるようです。その他、BUN上昇が41~55%、クレアチニン上昇が26~57%で診られ、腎臓血流不全がある場合はBUN/クレアチニン比の上昇が指標となります( :Smith, 2004)。
:Smith, 2004)。
 赤外線サーモグラフィーを用いた簡易検査の方法も開発されています。麻痺が生じていない前足と麻痺が発生した後ろ足の体温を比較し、温度差が2.4℃以上ある場合、8~9割の確率で動脈血栓塞栓症を予見できるとされています。猫を拘束する必要がないので、骨盤骨折など塞栓症以外の麻痺と鑑別診断する際の安全な検査法と言えるでしょう(
赤外線サーモグラフィーを用いた簡易検査の方法も開発されています。麻痺が生じていない前足と麻痺が発生した後ろ足の体温を比較し、温度差が2.4℃以上ある場合、8~9割の確率で動脈血栓塞栓症を予見できるとされています。猫を拘束する必要がないので、骨盤骨折など塞栓症以外の麻痺と鑑別診断する際の安全な検査法と言えるでしょう( :Nevoret, 2017)。
:Nevoret, 2017)。
動脈血栓塞栓症の原因が心疾患にある場合、聴診では心雑音、ギャロップ、不整脈、心エコー検査では左心房の拡張終期径が1.7cm以上、左房大動脈比2.0以上、左心房のもやもやエコー(スモーク)など心筋症やうっ血の徴候が確認されます(
 :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。塞栓症によって血流の途絶えた筋肉がダメージを受けると、血液検査において血清酵素値の上昇が見られます。例えば血清AST(GOT)値の上昇は83~99%、血清CPK(クレアチンホスホキナーゼ)の上昇は80~100%の割合で見られると言った報告もあります。末梢血では血糖値が低く乳酸値が高くなるという傾向もあるようです。その他、BUN上昇が41~55%、クレアチニン上昇が26~57%で診られ、腎臓血流不全がある場合はBUN/クレアチニン比の上昇が指標となります(
 :Smith, 2004)。
:Smith, 2004)。
 赤外線サーモグラフィーを用いた簡易検査の方法も開発されています。麻痺が生じていない前足と麻痺が発生した後ろ足の体温を比較し、温度差が2.4℃以上ある場合、8~9割の確率で動脈血栓塞栓症を予見できるとされています。猫を拘束する必要がないので、骨盤骨折など塞栓症以外の麻痺と鑑別診断する際の安全な検査法と言えるでしょう(
赤外線サーモグラフィーを用いた簡易検査の方法も開発されています。麻痺が生じていない前足と麻痺が発生した後ろ足の体温を比較し、温度差が2.4℃以上ある場合、8~9割の確率で動脈血栓塞栓症を予見できるとされています。猫を拘束する必要がないので、骨盤骨折など塞栓症以外の麻痺と鑑別診断する際の安全な検査法と言えるでしょう( :Nevoret, 2017)。
:Nevoret, 2017)。
動脈血栓塞栓症の治療
猫の動脈血栓塞栓症の治療法には以下のようなものがあります。発症から時間がたてばたつほど症状は悪化しますので、飼い主はなるべく早い段階で動物病院を受診しなければなりません。猫の歩行不全が夜に起こった場合、夜間救急病院に行く必要がありますので事前にリストアップしておきましょう。
まずは安静と鎮痛
全身還流の回復
動脈塞栓症では血栓によって血の巡りが悪化しているため、全身還流の回復が治療のメインテーマとなります。抗凝血剤などを投与して血栓の巨大化を防ぎ、容態が安定するのを待ちます。
輸液治療はリン、梗塞組織から放出される有機酸、血小板から放出される血管作用性物質を取り除く効果はあるものの、逆にうっ血性心不全につながるリスクもあるため慎重に行われます。
「血栓を薬で溶かせば良いじゃないか」というイメージが先行しますが、再灌流障害といって今まで血が流れていなかった部分に急激に血流が回復すると、いろいろな毒性物質が産生されて逆に症状が悪化する危険性があります。血栓溶解や外科的な摘出を行うと再灌流障害が40~70%で起こり、治療自体が死因になることもあるため現時点では推奨されていません。ただし塞栓が脳、腎臓、内臓の場合は放置しても死亡リスクが高まるだけなので積極的な溶解治療が選択されることもあります。その場合、介入から36~72時間は高カリウム血症、高窒素血症、不整脈、アシドーシスなどへの慎重なモニタリングが必要です( :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。
動脈血流に働きかける低血圧用の薬もその効果を証明したものはなく、悪化させる危険性があるため推奨されていません。
輸液治療はリン、梗塞組織から放出される有機酸、血小板から放出される血管作用性物質を取り除く効果はあるものの、逆にうっ血性心不全につながるリスクもあるため慎重に行われます。
「血栓を薬で溶かせば良いじゃないか」というイメージが先行しますが、再灌流障害といって今まで血が流れていなかった部分に急激に血流が回復すると、いろいろな毒性物質が産生されて逆に症状が悪化する危険性があります。血栓溶解や外科的な摘出を行うと再灌流障害が40~70%で起こり、治療自体が死因になることもあるため現時点では推奨されていません。ただし塞栓が脳、腎臓、内臓の場合は放置しても死亡リスクが高まるだけなので積極的な溶解治療が選択されることもあります。その場合、介入から36~72時間は高カリウム血症、高窒素血症、不整脈、アシドーシスなどへの慎重なモニタリングが必要です(
 :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。動脈血流に働きかける低血圧用の薬もその効果を証明したものはなく、悪化させる危険性があるため推奨されていません。
基礎疾患の管理
基礎疾患がある場合はそちらの管理を併せて行います。診察時にうっ血性心不全がない猫の生存中央値が223日だったのに対し、あった猫のそれは77日(最大で254日)だったとの報告があります。また動脈血栓塞栓症を発症した猫のうち、肥大型心筋症を抱えている場合の生存日数中央値は発症から61日で長くとも180日(6ヶ月)との報告もあります( :Atkins, 1992)。
:Atkins, 1992)。
ひとたび退院しても、血栓再発率は24~45%とされていますので、基礎疾患を改善することが再発の予防や生存期間の延長につながるでしょう。例えば右の前足に麻痺が生じた後、自然回復したため飼い主が楽観して治療や予防を行わなかった症例がありました。拘束型の心筋症を抱えていたこの猫はその1ヶ月後、左右の鎖骨下動脈、肺動脈、腹部大動脈サドル部に同時多発的に血栓塞栓症を起こし、4本の足が同時に動かなくなるという最重症例に発展した後、死亡してしまいました( :Bowles, 2010)。最初の麻痺で動物病院を受診して心筋症という持病に気づいていれば、もう少し長生きできていたかもしれません。
:Bowles, 2010)。最初の麻痺で動物病院を受診して心筋症という持病に気づいていれば、もう少し長生きできていたかもしれません。
 :Atkins, 1992)。
:Atkins, 1992)。ひとたび退院しても、血栓再発率は24~45%とされていますので、基礎疾患を改善することが再発の予防や生存期間の延長につながるでしょう。例えば右の前足に麻痺が生じた後、自然回復したため飼い主が楽観して治療や予防を行わなかった症例がありました。拘束型の心筋症を抱えていたこの猫はその1ヶ月後、左右の鎖骨下動脈、肺動脈、腹部大動脈サドル部に同時多発的に血栓塞栓症を起こし、4本の足が同時に動かなくなるという最重症例に発展した後、死亡してしまいました(
 :Bowles, 2010)。最初の麻痺で動物病院を受診して心筋症という持病に気づいていれば、もう少し長生きできていたかもしれません。
:Bowles, 2010)。最初の麻痺で動物病院を受診して心筋症という持病に気づいていれば、もう少し長生きできていたかもしれません。
予後と飼い主の心がけ
麻痺は回復の可能性あり
血流が途絶えて麻痺を起こした後ろ足に関しては腱の拘縮、組織の壊死、断肢を余儀なくされることがあるものの、回復する可能性も十分に残されているため過度に悲観してはいけないとする報告もあります。
たとえばミネソタ大学による調査では、急性の動脈血栓塞栓症を発症した127頭のうち44頭が退院までこぎつけ、そのうち壊死にともなう断肢が2頭(4.5%)、軽度の組織壊死と傷の治療が2頭(4.5%)、下肢の拘縮が1頭(2.3%)だけだったといいます。また血栓が腹部大動脈のサドル部に引っかかって後肢の虚血性神経筋障害を起こしても、周辺血管による補助血流があるのですぐに組織が壊死するというわけではなく、血栓が自己溶解したり移動によって血流が回復することもあるため、少なくとも発症から72時間は安易な安楽死を避けて容態を見守るべきと警告している医学論文もあります( :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。
たとえばミネソタ大学による調査では、急性の動脈血栓塞栓症を発症した127頭のうち44頭が退院までこぎつけ、そのうち壊死にともなう断肢が2頭(4.5%)、軽度の組織壊死と傷の治療が2頭(4.5%)、下肢の拘縮が1頭(2.3%)だけだったといいます。また血栓が腹部大動脈のサドル部に引っかかって後肢の虚血性神経筋障害を起こしても、周辺血管による補助血流があるのですぐに組織が壊死するというわけではなく、血栓が自己溶解したり移動によって血流が回復することもあるため、少なくとも発症から72時間は安易な安楽死を避けて容態を見守るべきと警告している医学論文もあります(
 :Hogan, 2017)。
:Hogan, 2017)。
早急な安楽死は避けて
2004年から2012年の期間、イギリス王立獣医大学が国内にある3つの動物病院(一次診療施設)の医療記録を回顧的に調べたところ、動脈血栓塞栓症が250症例あり、何の治療も試みないまま安楽死を施した割合が61.2%(153頭)にも達したといいます。こうした高い数字の背景には、飼い主が自発的に安楽死を要求したというより獣医師の勧めがあったものと推測されます。しかし何らかの治療を施した97頭のうち30頭に関しては7日以上生存し、30頭のうち6頭は1年以上生存したとのこと。これは治療を行った場合、6%以上の確率で長期の生存が可能になるということでもあります( :Borgeat, 2013)。
:Borgeat, 2013)。
またミネソタ大学が行った報告では、動脈塞栓症と診断された猫127頭における全体生存退院率が35%だったものの、治療を試みることなく安楽死を施した猫たちを除外した場合の退院率は45%に跳ね上がったといいます( :Smith, 2003)。
:Smith, 2003)。
 :Borgeat, 2013)。
:Borgeat, 2013)。またミネソタ大学が行った報告では、動脈塞栓症と診断された猫127頭における全体生存退院率が35%だったものの、治療を試みることなく安楽死を施した猫たちを除外した場合の退院率は45%に跳ね上がったといいます(
 :Smith, 2003)。
:Smith, 2003)。
獣医師が飼い主に対して猫の安楽死を勧める場合は、漠然と「予後が悪い」と伝えるのではなく、少なくともこうした数値データを判断材料として提供しなければなりませんね。