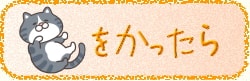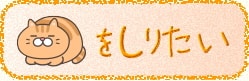詳細
調査を行ったのは、イギリス・王立獣医大学のチーム。2006年1月から2014年6月の期間、イギリス国内にある医療機関を受診した猫の中から甲状腺機能亢進症を発症した患猫をピックアップし、当症を持たない健常猫との比較調査を行いました。調査チームが想定したのは以下のような仮説です。

Crossley, V.J., Debnath, A., Chang, Y.M., Fowkes, R.C., Elliott, J. and Syme, H.M. (2017), J Vet Intern Med. doi:10.1111/jvim.14737
アミノ酸の一種であるチロシンは、甲状腺ホルモン(チロキシン)の前駆物質であると同時に、メラニン色素の前駆物質でもある。もし被毛に含まれるメラニン色素を作り出すのに大量のチロシンが消費されてしまうと、甲状腺ホルモン生成するために回されるチロシンの量が相対的に減少する。その結果、少ない量のチロシンから体を維持するのに十分な量の甲状腺ホルモンを生成しようとして、甲状腺がフル稼働状態になる。この状態に食事を通じてチロシンが補給されると、甲状腺ホルモンの生成量が過剰となり、甲状腺機能亢進症を発症する。つまり、大量のメラニン色素を作り出さなければならない黒猫や長毛猫では、甲状腺機能亢進症を発症しやすくなるはずだという仮説です。この仮説に則って収集したデータ(健常2,625頭+亢進症786頭)を統計的に検証したところ、発症リスクの増減に以下のような項目が関わっていたと言います。数字は「オッズ比」(OR)で、標準の起こりやすさを「1」としたときどの程度起こりやすいかを相対的に示したものです。数字が1よりも小さければリスクが小さいことを、逆に大きければリスクが大きいことを意味しています。

- 15~17歳=1.90
- 13~14歳=1.87
- 11~12歳=1.46
- メス猫=1.40
- 雑種の長毛種=1.31
- 未手術=0.67
- B.ショートヘア=0.47
- 純血種クロス=0.32
- シャム=0.27
- ペルシャ=0.21
- トンキニーズ=0.05
- アビシニアン=0.04
- バーミーズ=0.01
Crossley, V.J., Debnath, A., Chang, Y.M., Fowkes, R.C., Elliott, J. and Syme, H.M. (2017), J Vet Intern Med. doi:10.1111/jvim.14737

解説
過去に行われた調査では、シャム、ヒマラヤン、バーミーズといったカラーポイント品種(四肢末端と鼻先の色が濃い)において甲状腺機能亢進症の発症リスクが低いと報告されています。今回の調査でもシャムのほかペルシャやトンキニーズで同じ傾向が確認されました。また短毛種よりも長毛種の方が3割ほど高い発症率を示しました。これらの事実は、メラニン色素の生成量が少ない猫においては甲状腺の負担が減り、結果として亢進症の発症率が低くなるという仮説を部分的に支持しています。
 もしこの仮説が正しいならば、同じ理屈によって色が濃い猫よりも色が薄い猫の方が発症率が低くなるはずです。ところが、猫たちを被毛色によって分類して発症率を比較したところ、必ずしもこの仮説に当てはまらない事例が出てきたと言います。例えば、黒猫の発症リスクを1としたとき、白猫の発症率が0.7だったのに対し、カラーポイントが0.51、クリームが0.41だったなどです。メラニン色素の生成量が最も少ない白猫では発症リスクが最も低くなるはずですが、実際にはそうなっていません。こうした事実から調査チームは、色素生成とは全く関係のない未知の要因が絡んで数値を変動させているのではないかと推測しています。
甲状腺機能亢進症の正確な発症メカニズムは未だによくわかっていません。キャットフードが市場に出回りだした1980年代初頭から急速に患猫数が増えだしたという事実から考えると、被毛の色やパターンよりも、やはり食事を始めとした外的な要因の方が大きな影響力を持っているのかもしれません。例えば、食事に含まれるフタル酸エステルやヨウ素、壁紙やカーテンなどから被毛に付着した難燃剤のPBDEsなどです。詳しくは以下のページをご参照ください。
もしこの仮説が正しいならば、同じ理屈によって色が濃い猫よりも色が薄い猫の方が発症率が低くなるはずです。ところが、猫たちを被毛色によって分類して発症率を比較したところ、必ずしもこの仮説に当てはまらない事例が出てきたと言います。例えば、黒猫の発症リスクを1としたとき、白猫の発症率が0.7だったのに対し、カラーポイントが0.51、クリームが0.41だったなどです。メラニン色素の生成量が最も少ない白猫では発症リスクが最も低くなるはずですが、実際にはそうなっていません。こうした事実から調査チームは、色素生成とは全く関係のない未知の要因が絡んで数値を変動させているのではないかと推測しています。
甲状腺機能亢進症の正確な発症メカニズムは未だによくわかっていません。キャットフードが市場に出回りだした1980年代初頭から急速に患猫数が増えだしたという事実から考えると、被毛の色やパターンよりも、やはり食事を始めとした外的な要因の方が大きな影響力を持っているのかもしれません。例えば、食事に含まれるフタル酸エステルやヨウ素、壁紙やカーテンなどから被毛に付着した難燃剤のPBDEsなどです。詳しくは以下のページをご参照ください。
 もしこの仮説が正しいならば、同じ理屈によって色が濃い猫よりも色が薄い猫の方が発症率が低くなるはずです。ところが、猫たちを被毛色によって分類して発症率を比較したところ、必ずしもこの仮説に当てはまらない事例が出てきたと言います。例えば、黒猫の発症リスクを1としたとき、白猫の発症率が0.7だったのに対し、カラーポイントが0.51、クリームが0.41だったなどです。メラニン色素の生成量が最も少ない白猫では発症リスクが最も低くなるはずですが、実際にはそうなっていません。こうした事実から調査チームは、色素生成とは全く関係のない未知の要因が絡んで数値を変動させているのではないかと推測しています。
甲状腺機能亢進症の正確な発症メカニズムは未だによくわかっていません。キャットフードが市場に出回りだした1980年代初頭から急速に患猫数が増えだしたという事実から考えると、被毛の色やパターンよりも、やはり食事を始めとした外的な要因の方が大きな影響力を持っているのかもしれません。例えば、食事に含まれるフタル酸エステルやヨウ素、壁紙やカーテンなどから被毛に付着した難燃剤のPBDEsなどです。詳しくは以下のページをご参照ください。
もしこの仮説が正しいならば、同じ理屈によって色が濃い猫よりも色が薄い猫の方が発症率が低くなるはずです。ところが、猫たちを被毛色によって分類して発症率を比較したところ、必ずしもこの仮説に当てはまらない事例が出てきたと言います。例えば、黒猫の発症リスクを1としたとき、白猫の発症率が0.7だったのに対し、カラーポイントが0.51、クリームが0.41だったなどです。メラニン色素の生成量が最も少ない白猫では発症リスクが最も低くなるはずですが、実際にはそうなっていません。こうした事実から調査チームは、色素生成とは全く関係のない未知の要因が絡んで数値を変動させているのではないかと推測しています。
甲状腺機能亢進症の正確な発症メカニズムは未だによくわかっていません。キャットフードが市場に出回りだした1980年代初頭から急速に患猫数が増えだしたという事実から考えると、被毛の色やパターンよりも、やはり食事を始めとした外的な要因の方が大きな影響力を持っているのかもしれません。例えば、食事に含まれるフタル酸エステルやヨウ素、壁紙やカーテンなどから被毛に付着した難燃剤のPBDEsなどです。詳しくは以下のページをご参照ください。