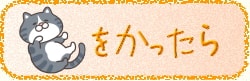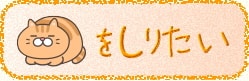伝説の出どころ
「好奇心は猫の命取りになる」(Curiosity killed the cat)という表現は、「過剰な興味を抱いて詮索しすぎると痛い目に合いますよ」という意味合いで使われる欧米のことわざです。
このことわざの起源として有力視されているのは、イギリスの劇作家ベン・ジョンソンが1598年に発表した戯曲「Every Man in His Humour」の中にある以下の一節です。
このことわざの起源として有力視されているのは、イギリスの劇作家ベン・ジョンソンが1598年に発表した戯曲「Every Man in His Humour」の中にある以下の一節です。
Helter skelter, hang sorrow, care will kill a cat, up-tails all, and a pox on the hangman.ここではまだ「curiosity」(好奇心)ではなく、「心配」というニュアンスで「care」が使われています。そしてこの戯曲で役者として舞台に立っていたのが、後に「最も優れた英文学の作家」と呼ばれるようになるウィリアム・シェークスピアでした。劇中のセリフにインスパイアされた彼は、翌1599年に発表した自身の戯曲「から騒ぎ」(Much Ado About Nothing)の中で、猫を再登場させました。
What, courage man! what though care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill careここでもまだ「curiosity」は登場しません。今日使われている完全なフレーズが登場するのは、それからさらに200年も後の事でした。 「Curiosity killed the cat」という言い回しが初めて登場するのは、1902年に出版された「ことわざ:金言と成句」(Proverbs: Maxims and Phrases)だと考えられています。それより少し前の1898年に出された「成句と説話の事典」(Dictionary of Phrase and Fable)の中では、まだ「Care killed the Cat」という表現が記載されているため、「care」から「curiosity」への転換が起こったのは、1898~1902年の間だったことになります。残念ながら、この4年間に何があったのかはよく分かっていません。しかし1902年以降は、「curiosity」の方が怒涛の勢いで英語圏を席巻するようになります。一例としては、アメリカの小説家オー・ヘンリーが1909年に出した短編に見られる「Curiosity can do more things than kill a cat」や、1916年3月4日のワシントンポスト紙に見られる「CURIOSITY KILLED THE CAT」という見出しなどが挙げられます。ちなみにこの見出しに続く記事の内容は、「好奇心に駆られて暖炉から煙突に上がろうとした猫が、途中で落ちて死んでしまった」というものでした。 Curiosity killed the cat
伝説の検証
「好奇心は猫の命取りになる」(curiosity killed the cat)ということわざは、当初「care」だった部分が「curiosity」に入れ替わることで生み出された成句です。この言葉の交代劇の背景には、一体どのような出来事が隠されているのでしょうか?想像を交えながら検証していきたいと思います。
動くものへの好奇心
動くものに対する好奇心が、猫の命取りになってしまう事は、確かにあるようです。
 高い場所から落下することで生じる諸々のケガのことを「高層症候群」(high-rise syndrome)と言います。さまざまな発生要因がありますが、高い場所にいるときに動くものが目に入り、そのままダイブしてしまうというパターンを無視できません。例えば、高層マンションのベランダで日向ぼっこをしている猫の目の前に、トンボや蝶々などヒラヒラと動くものが飛んできたとします。狩猟本能を呼び覚まされた猫は、瞳孔をまん丸にして虫たちの動きを目で追うことでしょう。そしてついには、自分がいる場所忘れ、虫めがけて飛びかかってしまいます。もちろんそこに地面などありません。結果としてフリーフォール状態となり、硬い地面に激突してしまいます。
高い場所から落下することで生じる諸々のケガのことを「高層症候群」(high-rise syndrome)と言います。さまざまな発生要因がありますが、高い場所にいるときに動くものが目に入り、そのままダイブしてしまうというパターンを無視できません。例えば、高層マンションのベランダで日向ぼっこをしている猫の目の前に、トンボや蝶々などヒラヒラと動くものが飛んできたとします。狩猟本能を呼び覚まされた猫は、瞳孔をまん丸にして虫たちの動きを目で追うことでしょう。そしてついには、自分がいる場所忘れ、虫めがけて飛びかかってしまいます。もちろんそこに地面などありません。結果としてフリーフォール状態となり、硬い地面に激突してしまいます。
このようにして発生するのが「高層症候群」です。言い換えれば、「動くものへの好奇心が猫の命取りになる」となるでしょう。
 高い場所から落下することで生じる諸々のケガのことを「高層症候群」(high-rise syndrome)と言います。さまざまな発生要因がありますが、高い場所にいるときに動くものが目に入り、そのままダイブしてしまうというパターンを無視できません。例えば、高層マンションのベランダで日向ぼっこをしている猫の目の前に、トンボや蝶々などヒラヒラと動くものが飛んできたとします。狩猟本能を呼び覚まされた猫は、瞳孔をまん丸にして虫たちの動きを目で追うことでしょう。そしてついには、自分がいる場所忘れ、虫めがけて飛びかかってしまいます。もちろんそこに地面などありません。結果としてフリーフォール状態となり、硬い地面に激突してしまいます。
高い場所から落下することで生じる諸々のケガのことを「高層症候群」(high-rise syndrome)と言います。さまざまな発生要因がありますが、高い場所にいるときに動くものが目に入り、そのままダイブしてしまうというパターンを無視できません。例えば、高層マンションのベランダで日向ぼっこをしている猫の目の前に、トンボや蝶々などヒラヒラと動くものが飛んできたとします。狩猟本能を呼び覚まされた猫は、瞳孔をまん丸にして虫たちの動きを目で追うことでしょう。そしてついには、自分がいる場所忘れ、虫めがけて飛びかかってしまいます。もちろんそこに地面などありません。結果としてフリーフォール状態となり、硬い地面に激突してしまいます。このようにして発生するのが「高層症候群」です。言い換えれば、「動くものへの好奇心が猫の命取りになる」となるでしょう。
暗がりに対する好奇心
暗がりに対する好奇心が猫の命取りになってしまう事もあるようです。
 猫の目から見た小さくて暗い穴は、甘美な魅力をもっています。なぜなら、その中には美味しい獲物がいるかもしれないし、また自分にとっての隠れ家になってくれるかもしれないからです。結果として猫は、こじんまりした暗がりを見つけると、本能的にその中に入り込もうとします。それが買い物袋や、わずかに開いたタンスの隙間であれば、笑い話で終わるでしょう。しかし野生環境においては、同じような行動でも猫の命を奪ってしまうことがあるようです。
猫の目から見た小さくて暗い穴は、甘美な魅力をもっています。なぜなら、その中には美味しい獲物がいるかもしれないし、また自分にとっての隠れ家になってくれるかもしれないからです。結果として猫は、こじんまりした暗がりを見つけると、本能的にその中に入り込もうとします。それが買い物袋や、わずかに開いたタンスの隙間であれば、笑い話で終わるでしょう。しかし野生環境においては、同じような行動でも猫の命を奪ってしまうことがあるようです。
1998年、ニュージーランドで行われた野生猫の観察では、ウサギの巣穴に強引に頭を突っ込んだ猫2頭が、そのまま動けなくなって死んでしまったという事例が報告されています。おそらくこの猫たちは、ウサギを捕まえようとしたか、あるいは風雨をしのぐために寝床を間借りしようとしたのでしょう。いずれにしても、「暗がりに対する好奇心が猫の命取りになる」というパターンは、確かにあるようです。 Space use and denning behaviour of wild ferrets
 猫の目から見た小さくて暗い穴は、甘美な魅力をもっています。なぜなら、その中には美味しい獲物がいるかもしれないし、また自分にとっての隠れ家になってくれるかもしれないからです。結果として猫は、こじんまりした暗がりを見つけると、本能的にその中に入り込もうとします。それが買い物袋や、わずかに開いたタンスの隙間であれば、笑い話で終わるでしょう。しかし野生環境においては、同じような行動でも猫の命を奪ってしまうことがあるようです。
猫の目から見た小さくて暗い穴は、甘美な魅力をもっています。なぜなら、その中には美味しい獲物がいるかもしれないし、また自分にとっての隠れ家になってくれるかもしれないからです。結果として猫は、こじんまりした暗がりを見つけると、本能的にその中に入り込もうとします。それが買い物袋や、わずかに開いたタンスの隙間であれば、笑い話で終わるでしょう。しかし野生環境においては、同じような行動でも猫の命を奪ってしまうことがあるようです。1998年、ニュージーランドで行われた野生猫の観察では、ウサギの巣穴に強引に頭を突っ込んだ猫2頭が、そのまま動けなくなって死んでしまったという事例が報告されています。おそらくこの猫たちは、ウサギを捕まえようとしたか、あるいは風雨をしのぐために寝床を間借りしようとしたのでしょう。いずれにしても、「暗がりに対する好奇心が猫の命取りになる」というパターンは、確かにあるようです。 Space use and denning behaviour of wild ferrets
新しいものへの好奇心
新しいものに対する好奇心が、猫の寿命を縮めてしまうこともあります。
「人間と動物の病気を一緒にみる」(インターシフト)の著者、B.N.ホロウィッツ女史によると、動物が持つ新規探索傾向は、ある一定時期に急激な高まりを見せるといいます。これは人間においても例外ではなく、具体的に以下のような事例が報告されています。
 こうした「一時的な好奇心の高まり」は、犬や猫でも観察されます。それが「社会化期」であり、犬では生後4~13週齢、猫では生後2~7週齢と推定されています。この時期にある犬や猫は、環境に対する恐怖心よりも好奇心が上回っているため、非常に熱心に外界の情報を吸収しようとします。しかし好奇心を満たす代償として、「外敵や危険に遭遇する」というリスクを取らなければなりません。その結果が、野生環境における子猫の死亡率に反映されているように思われます。
こうした「一時的な好奇心の高まり」は、犬や猫でも観察されます。それが「社会化期」であり、犬では生後4~13週齢、猫では生後2~7週齢と推定されています。この時期にある犬や猫は、環境に対する恐怖心よりも好奇心が上回っているため、非常に熱心に外界の情報を吸収しようとします。しかし好奇心を満たす代償として、「外敵や危険に遭遇する」というリスクを取らなければなりません。その結果が、野生環境における子猫の死亡率に反映されているように思われます。
「人間と動物の病気を一緒にみる」(インターシフト)の著者、B.N.ホロウィッツ女史によると、動物が持つ新規探索傾向は、ある一定時期に急激な高まりを見せるといいます。これは人間においても例外ではなく、具体的に以下のような事例が報告されています。
動物における好奇心
- ラッコ サンフランシスコ南部からファラロン諸島までの海域には、ホホジロザメがうようよ生息しており、「死の三角地帯」と呼ばれている。近くに暮らすラッコたちも、あえてその地帯に入ることはない。しかしあるタイプのラッコだけは、危険をかえりみずその三角地帯に出向こうとする。それはたいてい「若いオス」である。
- ラット 新しい環境に置かれた場合、年長のグループよりも、若いグループの方が不安を感じにくい。見慣れない物体に衝動的に近づく姿は、まるで真新しいものを常に探しているようだ。
- ベルベットモンキー 変わった品物を置くと、真っ先にやってきて調べるのは若手のサルである。単に中立的な物だろうと、初めて見るけれど恐ろしくない物だろうと、危険な雰囲気を漂わせる物だろうと、若手たちは熱心に近づき、忙しく身振り手振りし、警戒の声を上げ、そして触ってみようとする。
- 人間 アメリカ疾病予防管理センターの統計によると、子供の死亡率は13歳を境にして突如高くなる。その後19歳までの間、死亡率は年齢が上がるほど高くなっていき、特に男の子でその傾向が強い。ところが25歳を過ぎるころになると、10代の頃はあれほどよく見られた外傷による死亡事故が、尻つぼみになっていく。
 こうした「一時的な好奇心の高まり」は、犬や猫でも観察されます。それが「社会化期」であり、犬では生後4~13週齢、猫では生後2~7週齢と推定されています。この時期にある犬や猫は、環境に対する恐怖心よりも好奇心が上回っているため、非常に熱心に外界の情報を吸収しようとします。しかし好奇心を満たす代償として、「外敵や危険に遭遇する」というリスクを取らなければなりません。その結果が、野生環境における子猫の死亡率に反映されているように思われます。
こうした「一時的な好奇心の高まり」は、犬や猫でも観察されます。それが「社会化期」であり、犬では生後4~13週齢、猫では生後2~7週齢と推定されています。この時期にある犬や猫は、環境に対する恐怖心よりも好奇心が上回っているため、非常に熱心に外界の情報を吸収しようとします。しかし好奇心を満たす代償として、「外敵や危険に遭遇する」というリスクを取らなければなりません。その結果が、野生環境における子猫の死亡率に反映されているように思われます。
野良の子猫の死亡率
- アメリカ=75% 生まれてきた子猫169匹のうち、75%に相当する127匹までもが生後6ヶ月齢になるまでに死んでしまった。また死因が判明した87匹の子猫に関して調査を行ったところ、90%近くが「外傷」が理由で命を落とした。Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate
- 日本=80% メスは毎年繁殖するものの、生まれてきた子猫の中で1歳まで生き残れるのは、数年で1~2匹程度だった。比較的環境の良い福岡県相島(あいのしま)でも、子猫が1歳まで生き残る可能性は20%前後だと思われる。ねこの秘密(文春新書, P96)
伝説の結論
「care」から「curiosity」に入れ替わり「Curiosity killed the cat」(好奇心が猫の命取りになる)という成句が生み出された背景については想像するしかありません。しかし猫が持つ「動くもの」、「暗いもの」、「新しいもの」に対する好奇心が、猫の命を奪ってしまうという状況は、実際に起こり得ることのように思います。
猫が身をもって残してくれた教訓を生かすため、私たち人間にできることは、「他人のプライベートを根掘り葉掘り聞かないようにする」ことと、「猫が事故に遭わないように気を付ける」ことです。以下のような注意を念頭に置いておけば、少なくとも好奇心が猫の命を奪ってしまうことはないでしょう。
猫が身をもって残してくれた教訓を生かすため、私たち人間にできることは、「他人のプライベートを根掘り葉掘り聞かないようにする」ことと、「猫が事故に遭わないように気を付ける」ことです。以下のような注意を念頭に置いておけば、少なくとも好奇心が猫の命を奪ってしまうことはないでしょう。
「好奇心」から猫を守る
- 家の中にある、猫が通れそうな抜け道をふさぐ
- 猫をベランダに出さない
- 交通量の多い外に出さない
- 首輪はイージーロック式を
- 誤飲誤食に気を付ける