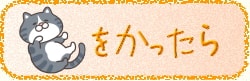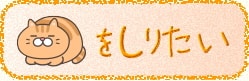伝説の出どころ
日本には古くから「猫は年をとると猫股になる」という都市伝説があります。「猫股」(ねこまた, 猫又とも)とは、不思議な妖力を持ち、人の言葉を理解できる猫の化け物のことです。この伝説の出所として最もしっくりくるのは、「日本の各時代における猫股が長い時間の中で自然融合してできた」とする考え方です。
 典型的な猫股の像は、江戸時代の後期には既に成立していたものと推測されます。例えば、1780年から1825年頃の成立と考えられる江戸時代の随筆「耳嚢」(みみぶくろ, 耳袋とも)の中では、長く寺で飼われていた老猫が和尚に向かい「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」と語るエピソードが記されており、この頃には既に猫股の固定概念のようなものがあったことがうかがえます。
江戸時代における猫股の特徴を簡単にまとめると、以下のようになるでしょう。
典型的な猫股の像は、江戸時代の後期には既に成立していたものと推測されます。例えば、1780年から1825年頃の成立と考えられる江戸時代の随筆「耳嚢」(みみぶくろ, 耳袋とも)の中では、長く寺で飼われていた老猫が和尚に向かい「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」と語るエピソードが記されており、この頃には既に猫股の固定概念のようなものがあったことがうかがえます。
江戸時代における猫股の特徴を簡単にまとめると、以下のようになるでしょう。

 典型的な猫股の像は、江戸時代の後期には既に成立していたものと推測されます。例えば、1780年から1825年頃の成立と考えられる江戸時代の随筆「耳嚢」(みみぶくろ, 耳袋とも)の中では、長く寺で飼われていた老猫が和尚に向かい「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」と語るエピソードが記されており、この頃には既に猫股の固定概念のようなものがあったことがうかがえます。
江戸時代における猫股の特徴を簡単にまとめると、以下のようになるでしょう。
典型的な猫股の像は、江戸時代の後期には既に成立していたものと推測されます。例えば、1780年から1825年頃の成立と考えられる江戸時代の随筆「耳嚢」(みみぶくろ, 耳袋とも)の中では、長く寺で飼われていた老猫が和尚に向かい「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」と語るエピソードが記されており、この頃には既に猫股の固定概念のようなものがあったことがうかがえます。
江戸時代における猫股の特徴を簡単にまとめると、以下のようになるでしょう。
典型的な「猫股」像
- 歳をとると化ける
- しっぽが二股に分かれる
- 毛色は黄色~黒
- 人を襲う
- 体が大きい
- オスである
- 人間の言葉を理解する
- 踊る
- 人(老婆が多い)に変身する

伝説の検証
猫股のイメージは、江戸時代の後期に当たる1800年代頃には既に成立していたと考えらます。以下では、日本の各時代における「猫」のイメージが、一体どのようにして後の「猫股」に影響を及ぼすようになったのかを概観していきたいと思います。
平安時代(794年~1185年)
「猫が化ける」という図式が登場し始めたのは、おそらく平安後期の頃だろうと推測されます。
平安中期
花山天皇(かざんてんのう, 968~1008)が「敷島の大和にはあらぬ唐猫の君がためにぞもとめ出たる」と詠んでいることから、平安中期にはすでに中国から輸入された「唐猫」が日本の宮中にいたものと推測されます。
平安後期
平安後期に記された「本朝世紀」(ほんちょうせいき)の中では、「山猫」と呼ばれる化け物が近江(おうみ=現在の滋賀県)と美濃(みの=現在の岐阜県)の山中に出現し、村に入って人々を襲ったという記述があります。
この「山猫」が、種としての「ヤマネコ」なのか、宮中にいる「唐猫」と区別するための「山猫」なのか、それとも山犬をただ単に「山猫」と呼んだのかに関しては定かではありません。しかし、平安初期においては宮中で高い地位を占めていたはずの「唐猫」が、時と共に身近な存在となり、平安後期になると「化け猫」扱いされるようになったという経緯がうっすらと見て取れます。
この「山猫」が、種としての「ヤマネコ」なのか、宮中にいる「唐猫」と区別するための「山猫」なのか、それとも山犬をただ単に「山猫」と呼んだのかに関しては定かではありません。しかし、平安初期においては宮中で高い地位を占めていたはずの「唐猫」が、時と共に身近な存在となり、平安後期になると「化け猫」扱いされるようになったという経緯がうっすらと見て取れます。
鎌倉時代(1185年~1333年)
平安後期に成立したと思われる「猫が化ける」というイメージは、鎌倉時代に入ると「猫が化けて人を襲う」という悪役のイメージへと進化していったようです。
鎌倉初期
藤原定家(ふじわらのていか)が残した日記「明月記」(めいげつき, 1180~1235)の中では、「猫股と言う獣が出て一晩で七、八人の被害者が出ました。目は猫のようで体は犬のようでした」という奈良からやってきた使者の話が登場します。またこの話を聞いた定家が、二条院の時代、京の都に「猫股病」と呼ばれる疫病が流行ったことを思い出します。前者では「怪物」と猫股がリンクし、後者では「疫病」と猫股がリンクしているようです。猫股と病気が結びつくようになったのは、「猫鬼」(びょうき)のイメージが影響を及ぼしたのかもしれません。「猫鬼」とは伝染病を媒介する鬼神の一種で、この頃中国から輸入されたと考えられています。
鎌倉末期
鎌倉末期、1330年頃の成立と伝えられる兼好法師の随筆「徒然草」(つれづれぐさ)の中では、「山の奥に猫またと言うものがいて、人を食うそうだ」、「いや山だけではない。このへんでも長生きした猫が猫またという怪物になって人を取ることはあるだろう」という表現があります。山であれ市中であれ「猫股=人を襲う化け物」という扱いになっており、当時の人々にとっての「猫股」がどういう存在だったかを知る手がかりを与えてくれます。
室町時代(1336~1573年)
室町時代において特筆すべきは、「玉藻前」(たまものまえ)のお話です。これは平安時代末期、鳥羽上皇に仕えた絶世の美女が登場する物語で、彼女は二尾あるいは九尾の狐が化けたものとされていました。彼女のイメージは後に、猫股がもつ「2つに分かれたしっぽ」に影響を及ぼしたと考えられます。
江戸時代(1603年~1868年)
江戸時代に起こった大きな変化は、「中国の金花猫と日本の猫股が融合したこと」と、「猫股のしっぽが二つに分かれ始めたこと」、そして「猫が躍り出したこと」です。
金花猫と猫股の融合
中国の明(みん)で1600年代初頭に出された「五雑組」(ござっそ)の中では、「金花の家猫は3年以上飼っていると必ず人を迷わすことができる」と記されています。この「金花猫」(きんかびょう)とは、金花と呼ばれる地域に出没する中国版の化け猫のことです。
一方、江戸前期の注釈書「徒然草文段抄」(つれづれぐさもんだんしょう, 1667年)の中では、「金花猫は黄色の猫で化けて婦女に煩いを成す」とあり、さらに「徒然草諸抄大成」(1700年ころ)の中では「金花猫は黄色の猫である。化けて婦女に煩いを成す」との記述があります。このことから、1600年代初頭に中国から輸入された「金花猫」という化け物のイメージが、その後約100年かけて日本文化の中に浸透していった流れがうかがえます。そしてこの流れは、日本版の化け猫である「猫股」に影響を及ぼし、ただ単に「猫が化ける」という従来の図式から、「年を取った猫が化ける」という新たな図式への変遷に拍車をかけたものと推測されます。
中国の「金花猫」と日本の「猫股」の融合を示す具体例も散見されます。例えば「本朝食鑑」((ほんちょうしょっかん, 1697年)の「おおよそ雄の老猫は妖怪となる。その変化の仕方は狐狸と変わらず、よく人を取って食う。俗にこれをねこまたという」という一節や、「和漢三才図会」(1712年)の「おおよそ十年以上生きた雄猫には、化けて人に害をなすものがある。言い伝えによれば、黄赤の毛色の猫は妖をなすことが多い」という一節などです。ちなみに「雄猫」という条件が追加された理由は、遺伝的にオス猫の方が金色(オレンジ~茶色)の毛色を発現しやすいからかもしれません。
一方、江戸前期の注釈書「徒然草文段抄」(つれづれぐさもんだんしょう, 1667年)の中では、「金花猫は黄色の猫で化けて婦女に煩いを成す」とあり、さらに「徒然草諸抄大成」(1700年ころ)の中では「金花猫は黄色の猫である。化けて婦女に煩いを成す」との記述があります。このことから、1600年代初頭に中国から輸入された「金花猫」という化け物のイメージが、その後約100年かけて日本文化の中に浸透していった流れがうかがえます。そしてこの流れは、日本版の化け猫である「猫股」に影響を及ぼし、ただ単に「猫が化ける」という従来の図式から、「年を取った猫が化ける」という新たな図式への変遷に拍車をかけたものと推測されます。
中国の「金花猫」と日本の「猫股」の融合を示す具体例も散見されます。例えば「本朝食鑑」((ほんちょうしょっかん, 1697年)の「おおよそ雄の老猫は妖怪となる。その変化の仕方は狐狸と変わらず、よく人を取って食う。俗にこれをねこまたという」という一節や、「和漢三才図会」(1712年)の「おおよそ十年以上生きた雄猫には、化けて人に害をなすものがある。言い伝えによれば、黄赤の毛色の猫は妖をなすことが多い」という一節などです。ちなみに「雄猫」という条件が追加された理由は、遺伝的にオス猫の方が金色(オレンジ~茶色)の毛色を発現しやすいからかもしれません。
しっぽの分裂
江戸中期の成立と伝えられる辞書「安斎随筆」(あんざいずいひつ)の中には、「数年の老猫は形が大きくなり、しっぽが二股になって災いを成す。これをねこまたともいう。しっぽが分かれているからいうのだろう」という解説が記載されています。また江戸後期の博物学書「重訂本草綱目啓蒙」(1803年)の中には「俗に老猫でしっぽが二股に分かれ、人をたぶらかすのをまたねこという」との一説が見て取れます。このことから、江戸中期~後期の頃にはすでに、「猫股のしっぽは2つに分かれている」というイメージが完成していたものと推測されます。このことは、妖怪画で有名な江戸後期の画家・鳥山石燕(とりやませきえん)の「画図百鬼夜行」(1776年)中にある「猫また」という絵からも明らかです。
 猫股の尻尾が分裂し始めた理由については定かではありません。考えられるのは、九尾の狐が登場する「玉藻前」の話と、猫と狐が共通して持っている「化ける」というイメージが混じり合い、猫と狐が合体していつの間にか猫のしっぽが分かれてしまった、という仮説です。江戸末期の随筆集「燕石十種」(えんせきじっしゅ, 1860年頃)の中には、「猫と狐が番(つが)え、狐の体に猫のような白黒まだら模様を持った子が生まれた」という話があります。このことからも、当時の人々にとって猫と狐がイメージ的に近いもので、いつ合体が起こっても不思議ではないことが見て取れます。
猫股の尻尾が分裂し始めた理由については定かではありません。考えられるのは、九尾の狐が登場する「玉藻前」の話と、猫と狐が共通して持っている「化ける」というイメージが混じり合い、猫と狐が合体していつの間にか猫のしっぽが分かれてしまった、という仮説です。江戸末期の随筆集「燕石十種」(えんせきじっしゅ, 1860年頃)の中には、「猫と狐が番(つが)え、狐の体に猫のような白黒まだら模様を持った子が生まれた」という話があります。このことからも、当時の人々にとって猫と狐がイメージ的に近いもので、いつ合体が起こっても不思議ではないことが見て取れます。
 猫股の尻尾が分裂し始めた理由については定かではありません。考えられるのは、九尾の狐が登場する「玉藻前」の話と、猫と狐が共通して持っている「化ける」というイメージが混じり合い、猫と狐が合体していつの間にか猫のしっぽが分かれてしまった、という仮説です。江戸末期の随筆集「燕石十種」(えんせきじっしゅ, 1860年頃)の中には、「猫と狐が番(つが)え、狐の体に猫のような白黒まだら模様を持った子が生まれた」という話があります。このことからも、当時の人々にとって猫と狐がイメージ的に近いもので、いつ合体が起こっても不思議ではないことが見て取れます。
猫股の尻尾が分裂し始めた理由については定かではありません。考えられるのは、九尾の狐が登場する「玉藻前」の話と、猫と狐が共通して持っている「化ける」というイメージが混じり合い、猫と狐が合体していつの間にか猫のしっぽが分かれてしまった、という仮説です。江戸末期の随筆集「燕石十種」(えんせきじっしゅ, 1860年頃)の中には、「猫と狐が番(つが)え、狐の体に猫のような白黒まだら模様を持った子が生まれた」という話があります。このことからも、当時の人々にとって猫と狐がイメージ的に近いもので、いつ合体が起こっても不思議ではないことが見て取れます。
猫股のダンス
先述した鳥山石燕(とりやませきえん)の「画図百鬼夜行」(1776年)の「猫また」を始め、猫股をモチーフとした絵画や浮世絵では、頭に手拭いを乗せて踊っている姿を多く見かけます。その端緒とでもいうべき逸話は、江戸中期、1708年刊の「大和怪異記」の中に早くも登場していました。
こうしたことから、1700年代初頭に現れ出した「猫股は踊る」というイメージが、100年以上の時を経て徐々に固定化されていった流れを確認することができます。
筑後国(現在の福岡県)に暮らすとある侍の家では、夜になると手鞠ほどの大きさもある火の玉が現れ、家人に怪をなしていた。ある日主人が何気なく屋根の上を見ると、一体何年生きているのかわからないようなすさまじい猫が、下女の赤い手拭いを頭にかぶり、しっぽと後ろ足で立ち上がって手をかざして四方を眺めているではないか。すかさず矢を射ると見事に命中し、怪猫は体に刺さった矢を噛み砕きながら死んでしまった。屋根から引き落としてみると、そのしっぽは二つに裂け、体長は五尺(1.5m)ほどもあった。このように1700年代初頭の時点ですでに、「猫股が人間のように立ち上がる」という擬人化が進んでいたと考えられます。さらに、それから100年以上後の1821年に刊行された「甲子夜話」の中では、下総佐倉(現在の千葉県佐倉市)の高木伯仙という人物が体験した「ある夜寝ていると、枕元で何か音がする。目を開けて見てみると、長らく飼っていた猫が手拭いをかぶって立ち上がり、手を招く仕草を見せ、子供のように舞い踊る姿があった」というエピソードや、角筈(現在の東京都新宿区)に暮らしていた光照という女性が体験した「飼っていた黒毛の老猫が侍女の枕元で踊りだしたので布団をかぶって寝た振りをした」といったエピソードが紹介されています。
こうしたことから、1700年代初頭に現れ出した「猫股は踊る」というイメージが、100年以上の時を経て徐々に固定化されていった流れを確認することができます。
伝説の結論
「猫は年をとると猫股になる」という都市伝説は、平安時代から江戸時代に至る数百年の歴史の中で、猫にまつわる様々な逸話がブレンドされて完成したと考えるのが妥当なようです。
 こうした流れの中で固定化された猫股の悪役としてのイメージは、当時の猫たちにとって決して歓迎されるタイプのものではありませんでした。例えば江戸時代の百科事典「和漢三才図会」(1713年)の中では、三味線について「その皮みな猫の革を以てす、八乳の者を良しとす、狗子の皮を下となす」と記載されています。永禄年間(1558~70年)では海ヘビだったはずの三味線の皮が、わずか70年ほどの間に猫の皮に入れ替わっています。この背景には「海ヘビの皮を入手しにくい」という物流的な問題のほか、「邪悪な存在である猫なら殺しても心が痛まない」といった文化的な後押しがあったように思えてなりません。また「長いしっぽの猫はそのうち2つに分かれ猫股に変化する」という都市伝説を信じていた人々は、特に虎毛や黒毛の子猫のしっぽを縛って血液を分断させ、意図的に壊疽させていたようです。これは現代でいう犬の断尾と同じ風潮です。猫からするとたまったものではないでしょう。
幸い、猫のしっぽを短くするという慣習は、明治と大正を経る間に風化していきました。また、社会的ステータスの上昇と共に平均寿命も大きく伸び、2014年の時点で、外に自由に出られる猫が13.19歳、完全に室内で飼われている猫が15.69歳程度と推計されています(ペットフード協会)。1800年頃の「耳嚢」(みみぶくろ)では「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」とされていましたので、今の日本に暮らしている猫たちは、そのほとんどが「スーパーネコマタ」と言っても過言ではないでしょう。
こうした流れの中で固定化された猫股の悪役としてのイメージは、当時の猫たちにとって決して歓迎されるタイプのものではありませんでした。例えば江戸時代の百科事典「和漢三才図会」(1713年)の中では、三味線について「その皮みな猫の革を以てす、八乳の者を良しとす、狗子の皮を下となす」と記載されています。永禄年間(1558~70年)では海ヘビだったはずの三味線の皮が、わずか70年ほどの間に猫の皮に入れ替わっています。この背景には「海ヘビの皮を入手しにくい」という物流的な問題のほか、「邪悪な存在である猫なら殺しても心が痛まない」といった文化的な後押しがあったように思えてなりません。また「長いしっぽの猫はそのうち2つに分かれ猫股に変化する」という都市伝説を信じていた人々は、特に虎毛や黒毛の子猫のしっぽを縛って血液を分断させ、意図的に壊疽させていたようです。これは現代でいう犬の断尾と同じ風潮です。猫からするとたまったものではないでしょう。
幸い、猫のしっぽを短くするという慣習は、明治と大正を経る間に風化していきました。また、社会的ステータスの上昇と共に平均寿命も大きく伸び、2014年の時点で、外に自由に出られる猫が13.19歳、完全に室内で飼われている猫が15.69歳程度と推計されています(ペットフード協会)。1800年頃の「耳嚢」(みみぶくろ)では「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」とされていましたので、今の日本に暮らしている猫たちは、そのほとんどが「スーパーネコマタ」と言っても過言ではないでしょう。
最後に、現代に生きる「猫股」をご紹介します。ただしこちらは妖怪変化でも何でもなく、単なる遺伝子の気まぐれですが…。
 こうした流れの中で固定化された猫股の悪役としてのイメージは、当時の猫たちにとって決して歓迎されるタイプのものではありませんでした。例えば江戸時代の百科事典「和漢三才図会」(1713年)の中では、三味線について「その皮みな猫の革を以てす、八乳の者を良しとす、狗子の皮を下となす」と記載されています。永禄年間(1558~70年)では海ヘビだったはずの三味線の皮が、わずか70年ほどの間に猫の皮に入れ替わっています。この背景には「海ヘビの皮を入手しにくい」という物流的な問題のほか、「邪悪な存在である猫なら殺しても心が痛まない」といった文化的な後押しがあったように思えてなりません。また「長いしっぽの猫はそのうち2つに分かれ猫股に変化する」という都市伝説を信じていた人々は、特に虎毛や黒毛の子猫のしっぽを縛って血液を分断させ、意図的に壊疽させていたようです。これは現代でいう犬の断尾と同じ風潮です。猫からするとたまったものではないでしょう。
幸い、猫のしっぽを短くするという慣習は、明治と大正を経る間に風化していきました。また、社会的ステータスの上昇と共に平均寿命も大きく伸び、2014年の時点で、外に自由に出られる猫が13.19歳、完全に室内で飼われている猫が15.69歳程度と推計されています(ペットフード協会)。1800年頃の「耳嚢」(みみぶくろ)では「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」とされていましたので、今の日本に暮らしている猫たちは、そのほとんどが「スーパーネコマタ」と言っても過言ではないでしょう。
こうした流れの中で固定化された猫股の悪役としてのイメージは、当時の猫たちにとって決して歓迎されるタイプのものではありませんでした。例えば江戸時代の百科事典「和漢三才図会」(1713年)の中では、三味線について「その皮みな猫の革を以てす、八乳の者を良しとす、狗子の皮を下となす」と記載されています。永禄年間(1558~70年)では海ヘビだったはずの三味線の皮が、わずか70年ほどの間に猫の皮に入れ替わっています。この背景には「海ヘビの皮を入手しにくい」という物流的な問題のほか、「邪悪な存在である猫なら殺しても心が痛まない」といった文化的な後押しがあったように思えてなりません。また「長いしっぽの猫はそのうち2つに分かれ猫股に変化する」という都市伝説を信じていた人々は、特に虎毛や黒毛の子猫のしっぽを縛って血液を分断させ、意図的に壊疽させていたようです。これは現代でいう犬の断尾と同じ風潮です。猫からするとたまったものではないでしょう。
幸い、猫のしっぽを短くするという慣習は、明治と大正を経る間に風化していきました。また、社会的ステータスの上昇と共に平均寿命も大きく伸び、2014年の時点で、外に自由に出られる猫が13.19歳、完全に室内で飼われている猫が15.69歳程度と推計されています(ペットフード協会)。1800年頃の「耳嚢」(みみぶくろ)では「十年あまりも生きた猫だったらすべて言葉をしゃべれるようになります。さらにそれから四、五年もすると、不思議な能力を身に付けます。しかしそこまで長生きする猫はほとんどいません」とされていましたので、今の日本に暮らしている猫たちは、そのほとんどが「スーパーネコマタ」と言っても過言ではないでしょう。最後に、現代に生きる「猫股」をご紹介します。ただしこちらは妖怪変化でも何でもなく、単なる遺伝子の気まぐれですが…。
現代の猫股「多尾猫」