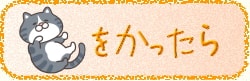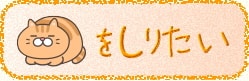猫の舌が感じる甘さ
猫の味覚のうち「甘味」に関しては、どんな濃度にしてもショ糖(砂糖の構成成分)を感じ分けることができず、電気生理学的な調査でもショ糖を感じる神経線維が見つからなかった(Carpenter, 1956)という報告がある一方、ミルクにショ糖(0.5M)を溶かした溶液が好まれたという矛盾した報告もあります(Frings, 1951)。
 そこでアメリカにあるモネル化学感覚研究所の調査チームは、猫がそもそも「Tas1r2」と「Tas1r3」遺伝子を保有しているかどうかをDNAレベルで調べることにしました。この2つの遺伝子は、甘味を感じることができる犬、人間、マウス、ラットなどの動物種が共通して保有している遺伝子で、甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」の形成(エンコード)に関わっています。
そこでアメリカにあるモネル化学感覚研究所の調査チームは、猫がそもそも「Tas1r2」と「Tas1r3」遺伝子を保有しているかどうかをDNAレベルで調べることにしました。この2つの遺伝子は、甘味を感じることができる犬、人間、マウス、ラットなどの動物種が共通して保有している遺伝子で、甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」の形成(エンコード)に関わっています。
 そこでアメリカにあるモネル化学感覚研究所の調査チームは、猫がそもそも「Tas1r2」と「Tas1r3」遺伝子を保有しているかどうかをDNAレベルで調べることにしました。この2つの遺伝子は、甘味を感じることができる犬、人間、マウス、ラットなどの動物種が共通して保有している遺伝子で、甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」の形成(エンコード)に関わっています。
そこでアメリカにあるモネル化学感覚研究所の調査チームは、猫がそもそも「Tas1r2」と「Tas1r3」遺伝子を保有しているかどうかをDNAレベルで調べることにしました。この2つの遺伝子は、甘味を感じることができる犬、人間、マウス、ラットなどの動物種が共通して保有している遺伝子で、甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」の形成(エンコード)に関わっています。
- T1R2/T1R3ヘテロマー
- T1R2とT1R3がヘテロ2量体を形成した味覚受容体で、糖、グリシン、甘味を持つタンパク質(モネリンやソーマチン)などを感知する。

猫のTas1r3遺伝子
猫の「Tas1r3」遺伝子は犬、人間、マウス、ラットのそれと近似しており、相補的DNAレベルでは74~87%、推定アミノ酸配列では72~85%の近似性を有していたといいます。
また猫の舌にある茸状乳頭と有郭乳頭から採った相補的DNAを調べた所、犬と同様、猫でも「Tas1r3」遺伝子は同サイズの6つのエクソンと5つのイントロンから構成されていたとも。また犬と猫の遺伝子を比較しても明白な違いは見られなかったそうです。
また猫の舌にある茸状乳頭と有郭乳頭から採った相補的DNAを調べた所、犬と同様、猫でも「Tas1r3」遺伝子は同サイズの6つのエクソンと5つのイントロンから構成されていたとも。また犬と猫の遺伝子を比較しても明白な違いは見られなかったそうです。
猫のTas1r2遺伝子
猫の「Tas1r2」に関しては終結コドンを複数箇所含んでいることから偽遺伝子であると推定されました。「終結コドン」とはタンパク質の生合成を停止させるために使われているコドンのこと、「偽遺伝子」とはかつてはタンパク質などの遺伝子産物をコードしていたと考えられるものの、現在はその機能を失っている遺伝子のことです。
こうした事実から、猫の舌の上にある茸状乳頭でも有郭乳頭でも「Tas1r2」は機能していないと考えられました。
こうした事実から、猫の舌の上にある茸状乳頭でも有郭乳頭でも「Tas1r2」は機能していないと考えられました。
タンパク質のコーディング
猫の舌にある茸状乳頭と有郭乳頭のタンパク質を調べた所、「Tas1r3」遺伝子がコードするT1R3タンパク質が確認されたのに対し、「Tas1r2」遺伝子がコードするT1R2タンパク質は一切確認されませんでした。「Tas1r2」遺伝子が転写されていないか、もしくは転写された後でナンセンス変異依存mRNA分解機構を通じてすぐに劣化し、T1R2タンパク質が正常に形成されていないかのどちらかだろうと推測されています。
猫には甘味受容器がない!
遺伝子および舌の乳頭におけるタンパク質を調べた結果、猫では「Tas1r3」遺伝子がコードするT1R3タンパク質しか保有しておらず、「Tas1r2」遺伝子がコードするT1R2タンパク質は存在していない事実が判明しました。すなわち甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」が形成されないため、糖の存在を検知できないということです。犬では感知できる0.5mol/L濃度のスクロース(ショ糖)を猫が弁別できない理由もこれで説明できます。
 ちなみに別の猫6頭とトラ1頭およびチーター1頭のDNAを調べた所、「Tas1r2」遺伝子自体は確認されたものの、エクソン3内では247-bpの欠失変異、エクソン4内では同じ箇所に終止コドンが確認されたといいます。おそらくトラもチーターも猫と同様、受容器が形成されず甘味を感じることができないものと推測されます。
Pseudogenization of a sweet-receptor gene accounts for cats’ indifference toward sugar.
ちなみに別の猫6頭とトラ1頭およびチーター1頭のDNAを調べた所、「Tas1r2」遺伝子自体は確認されたものの、エクソン3内では247-bpの欠失変異、エクソン4内では同じ箇所に終止コドンが確認されたといいます。おそらくトラもチーターも猫と同様、受容器が形成されず甘味を感じることができないものと推測されます。
Pseudogenization of a sweet-receptor gene accounts for cats’ indifference toward sugar.
Li X, Li W, Wang H, Cao J, Maehashi K, et al. (2005) PLoS Genet 1(1): e3., DOI.org/10.1371/journal.pgen.0010003
 ちなみに別の猫6頭とトラ1頭およびチーター1頭のDNAを調べた所、「Tas1r2」遺伝子自体は確認されたものの、エクソン3内では247-bpの欠失変異、エクソン4内では同じ箇所に終止コドンが確認されたといいます。おそらくトラもチーターも猫と同様、受容器が形成されず甘味を感じることができないものと推測されます。
Pseudogenization of a sweet-receptor gene accounts for cats’ indifference toward sugar.
ちなみに別の猫6頭とトラ1頭およびチーター1頭のDNAを調べた所、「Tas1r2」遺伝子自体は確認されたものの、エクソン3内では247-bpの欠失変異、エクソン4内では同じ箇所に終止コドンが確認されたといいます。おそらくトラもチーターも猫と同様、受容器が形成されず甘味を感じることができないものと推測されます。
Pseudogenization of a sweet-receptor gene accounts for cats’ indifference toward sugar.Li X, Li W, Wang H, Cao J, Maehashi K, et al. (2005) PLoS Genet 1(1): e3., DOI.org/10.1371/journal.pgen.0010003

猫の小腸が感じる甘さ
甘味受容器は舌の上だけでなく、消化管の内腔にも存在しています。例えば犬の小腸上皮細胞においては「T1R2」および「T1R3」タンパク質の両方が発現しており、舌と同じく「T1R2/T1R3ヘテロマー」を形成して糖の感知に関わっています。一方、猫の小腸においては「T1R3」タンパク質しか発現していません。つまり甘味受容器である「T1R2/T1R3ヘテロマー」が正常に形成されず、腸管内に入ってきた糖質を認識できないということです( :Batchelor, 2011)。
:Batchelor, 2011)。
 :Batchelor, 2011)。
:Batchelor, 2011)。
猫は甘いものが嫌い?
舌および消化管におけるT1R2とT1R3遺伝子を調べた結果、猫においてはどちらの部位においてもT1R2遺伝子が発現しておらず、糖を検知する「T1R2/T1R3ヘテロマー」が形成されていないことが判明しました。
猫は甘いもので下痢をしやすい
犬では舌においてT1R2とT1R3両方の遺伝子が発現して「T1R2/T1R3ヘテロマー」が形成されており、甘味を感知することができると考えられます。また消化管においても「T1R2」および「T1R3」タンパク質の両方が確認されていることから、糖質(炭水化物のうちカロリーを有するもの)の増大を敏感に感知して輸送器であるSGLT1の発現量を増やし、下痢を起こさずに消化吸収できると考えられます。
さらに小腸の近位および中間部における糖質の分解に関わる酵素活性を調べた所、犬と猫では以下のような格差が見られたといいます。酵素活性の違いから、猫に比べて犬の方が炭水化物の消化吸収能力に優れていると推測されます( :Batchelor, 2011)。
:Batchelor, 2011)。
- SGLT1
- 「グルコース共輸送体タンパク」のこと。小腸の近位、中間、遠位部に分布してグルコース(ブドウ糖)を吸収するという重要な役割を担っている。犬と猫を比較した場合、SGLT1の機能は猫に比べて犬のほうが1.9~2.3倍も高く、また検出されるSGLT1タンパクの含有量も多いことが知られている。
さらに小腸の近位および中間部における糖質の分解に関わる酵素活性を調べた所、犬と猫では以下のような格差が見られたといいます。酵素活性の違いから、猫に比べて犬の方が炭水化物の消化吸収能力に優れていると推測されます(
 :Batchelor, 2011)。
:Batchelor, 2011)。
糖質関連の酵素活性値
- ラクターゼ→犬3.1>猫1.6
- スクラーゼ→犬4.4>猫2.9
- マルターゼ→犬4.6>猫3.1
キャットフードは炭水化物が過剰?
猫が自由にエサを食べることができるとき、重量ベースで見た時の各栄養素の摂取比率がタンパク質26g、脂質9g、炭水化物8gになるよう自発的に食べる比率を調整するといいます。また別の報告では、炭水化物の摂取量に関して1日あたり70kcal(300kJ)が上限だったとも。この上限を超えると、たとえ空腹でもそれ以上のエサを食べなくなったそうです。さらに炭水化物の摂取量が体重1kg当たり3gという上限を超えるような食餌しかない場合、猫は潔く空腹を選ぶという報告もあります。
上記したように猫は炭水化物(糖質)がそれほど好きではなく、自発的に摂取比率を調整してしまうようです。腸内における消化吸収が苦手で本能的に避けるといった先天的な理由のほか、「大量に食べて下痢を起こした」と言う後天的な理由もあることでしょう。
一方、現代のキャットフードは炭水化物の含有比率が30~40%と非常に高い値になっています。舌や小腸における甘味受容器の欠落や消化管内における酵素活性の低さから考えると、猫たちに少し無理をかけているような気がしますね。糖尿病の比率に関し、犬では「I型:II型=4:1」なのに対し、猫では「1:4」とちょうど真逆の関係になっていることと無関係ではないでしょう。 猫たちがどのようにして高炭水化物の食事内容に適応しているのかはわかりませんが、ひょっとすると犬で見られるような収斂進化の途上にあるのかもしれません。犬においては狼から分岐した後、デンプンの消化に関わる遺伝子に変異が起こり大量の炭水化物でも難なく消化吸収することができるよう進化しました。 猫の体内においても同じような遺伝子変異が起こると、そのうち「完全肉食」から「雑食」の動物に進化していくかもしれません。
猫たちがどのようにして高炭水化物の食事内容に適応しているのかはわかりませんが、ひょっとすると犬で見られるような収斂進化の途上にあるのかもしれません。犬においては狼から分岐した後、デンプンの消化に関わる遺伝子に変異が起こり大量の炭水化物でも難なく消化吸収することができるよう進化しました。 猫の体内においても同じような遺伝子変異が起こると、そのうち「完全肉食」から「雑食」の動物に進化していくかもしれません。
一方、現代のキャットフードは炭水化物の含有比率が30~40%と非常に高い値になっています。舌や小腸における甘味受容器の欠落や消化管内における酵素活性の低さから考えると、猫たちに少し無理をかけているような気がしますね。糖尿病の比率に関し、犬では「I型:II型=4:1」なのに対し、猫では「1:4」とちょうど真逆の関係になっていることと無関係ではないでしょう。
 猫たちがどのようにして高炭水化物の食事内容に適応しているのかはわかりませんが、ひょっとすると犬で見られるような収斂進化の途上にあるのかもしれません。犬においては狼から分岐した後、デンプンの消化に関わる遺伝子に変異が起こり大量の炭水化物でも難なく消化吸収することができるよう進化しました。 猫の体内においても同じような遺伝子変異が起こると、そのうち「完全肉食」から「雑食」の動物に進化していくかもしれません。
猫たちがどのようにして高炭水化物の食事内容に適応しているのかはわかりませんが、ひょっとすると犬で見られるような収斂進化の途上にあるのかもしれません。犬においては狼から分岐した後、デンプンの消化に関わる遺伝子に変異が起こり大量の炭水化物でも難なく消化吸収することができるよう進化しました。 猫の体内においても同じような遺伝子変異が起こると、そのうち「完全肉食」から「雑食」の動物に進化していくかもしれません。