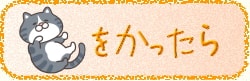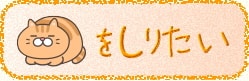猫の食事と甲状腺機能亢進症
猫の甲状腺機能亢進症の原因はよくわかっていません。過去に行われた様々な調査の結果から、キャットフードに含まれる大豆、および大豆由来のイソフラボンが発症に関わっている可能性が指摘されています。
猫に多い甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症とは、猫ののど元にある甲状腺と呼ばれる内分泌器官がおかしくなり、甲状腺ホルモンの分泌が過剰になった状態のこと。甲状腺ホルモンは代謝を司っていますので、呼吸数の増加、体温の上昇、エネルギー消費量の増加、食事量の増加、体重減少といった臨床症状として現れます。ちょうど全く必要ないのに体の中でターボエンジンがかかったような状態です。
 犬では極めて珍しい疾患であるのに対し猫では非常に頻繁に見られ、およそ300頭に1頭が罹患しているという疫学調査もあるくらいです(Broussard et al., 1995)。発症メカニズムに関してはよくわかっておらず、これまで感染症、重金属、環境因子といった原因が想定されてきましたがすっきりとした解明には至りませんでした。キャットフードが登場した1980年代以降に症例数が急増していることから、現在では食事に原因があるのではないかと考えられています。中でも有力視されているのが、大豆などに多く含まれる「イソフラボン」と呼ばれる成分です。
犬では極めて珍しい疾患であるのに対し猫では非常に頻繁に見られ、およそ300頭に1頭が罹患しているという疫学調査もあるくらいです(Broussard et al., 1995)。発症メカニズムに関してはよくわかっておらず、これまで感染症、重金属、環境因子といった原因が想定されてきましたがすっきりとした解明には至りませんでした。キャットフードが登場した1980年代以降に症例数が急増していることから、現在では食事に原因があるのではないかと考えられています。中でも有力視されているのが、大豆などに多く含まれる「イソフラボン」と呼ばれる成分です。
 犬では極めて珍しい疾患であるのに対し猫では非常に頻繁に見られ、およそ300頭に1頭が罹患しているという疫学調査もあるくらいです(Broussard et al., 1995)。発症メカニズムに関してはよくわかっておらず、これまで感染症、重金属、環境因子といった原因が想定されてきましたがすっきりとした解明には至りませんでした。キャットフードが登場した1980年代以降に症例数が急増していることから、現在では食事に原因があるのではないかと考えられています。中でも有力視されているのが、大豆などに多く含まれる「イソフラボン」と呼ばれる成分です。
犬では極めて珍しい疾患であるのに対し猫では非常に頻繁に見られ、およそ300頭に1頭が罹患しているという疫学調査もあるくらいです(Broussard et al., 1995)。発症メカニズムに関してはよくわかっておらず、これまで感染症、重金属、環境因子といった原因が想定されてきましたがすっきりとした解明には至りませんでした。キャットフードが登場した1980年代以降に症例数が急増していることから、現在では食事に原因があるのではないかと考えられています。中でも有力視されているのが、大豆などに多く含まれる「イソフラボン」と呼ばれる成分です。
イソフラボンの種類と作用
健康食品の成分としてよく耳にする「イソフラボン」。この成分には「甲状腺へのヨウ素の取り込みを阻害する」という作用があることから、機能亢進症との関連性が疑われています。
イソフラボンとは大豆、レッドクローバー、クズ、カンゾウなどのマメ科の植物に多く含まれているフラボノイドの一種。大豆に含まれるものは特に大豆イソフラボンと呼ばれます。イソフラボンには配糖体(糖がグリコシド結合により様々な原子と結合した化合物)と配糖体から糖が外れたアグリコンという形態があり、以下のような種類に細分されます。メインは「ゲニステイン」(genistein)、「ダイゼイン」(daidzein)、「グリシテイン」(glycitein)の3種で、「エクオール」(equol)以下は腸内細菌によって生成される代謝産物です。
過去に猫を対象として行われた様々な調査により、キャットフードに含まれる大豆、および大豆に含まれるイソフラボンが、猫の甲状腺機能亢進症に関わっている可能性が浮上してきました。現在わかっている事実は以下です。
イソフラボンとは大豆、レッドクローバー、クズ、カンゾウなどのマメ科の植物に多く含まれているフラボノイドの一種。大豆に含まれるものは特に大豆イソフラボンと呼ばれます。イソフラボンには配糖体(糖がグリコシド結合により様々な原子と結合した化合物)と配糖体から糖が外れたアグリコンという形態があり、以下のような種類に細分されます。メインは「ゲニステイン」(genistein)、「ダイゼイン」(daidzein)、「グリシテイン」(glycitein)の3種で、「エクオール」(equol)以下は腸内細菌によって生成される代謝産物です。
イソフラボンの種類
- ゲニステイン
- ダイゼイン
- グリシテイン
- バイオカニンA
- ホルモノネチン
- エクオール
- ジヒドロダイゼイン
- ジヒドロゲニステイン
- O-デスメチルアンゴレンシン
過去に猫を対象として行われた様々な調査により、キャットフードに含まれる大豆、および大豆に含まれるイソフラボンが、猫の甲状腺機能亢進症に関わっている可能性が浮上してきました。現在わかっている事実は以下です。
- 大豆原料のキャットフードには高濃度でイソフラボンが含まれている
- イソフラボンを摂取した猫の体内では甲状腺ホルモン(T4)濃度が高まる
- 猫の体内では犬よりもエクオールが生成されやすい
- イソフラボンの抱合代謝に関し犬ではグルクロン酸がメイン、猫では硫酸がメイン
- 猫の体内では「UGT1A6」と呼ばれる酵素が欠落している
- 猫の体内ではイソフラボン代謝のバックアップシステムがない
猫と大豆イソフラボン
タンパク質の安価な供給源として大豆は多くのキャットフードに含まれています。しかし「ヘルシー」というイメージとは裏腹に、猫が大量に摂取したり長期的に摂取しつづけると、中に含まれるイソフラボンによって思わぬ健康被害が引き起こされる危険性があります。
大豆含有のキャットフード
キャットフードの原料としてラベルに大豆と記載されている場合、ほぼ確実に大豆イソフラボンも含まれています。
ニュージーランド・マッセー大学を中心としたチームは大豆を原料として使った市販のキャットフードを合計138種類を購入し、中に含まれるイソフラボンの濃度を分析しました。その結果、ドライやウエットに関わらずすべての商品カテゴリからイソフラボンがまんべんなく検出されたといいます。イソフラボンの中で最も多く含まれていたのはダイゼイン(70%)で、次がゲニステイン(48%)という順でした。1日における摂取量の中央値を推測した所、猫の体重1kg当たり「0.03mg~1.47mg」となり、人間において設定されている摂取上限値2mg/kgを超えていた商品の割合は19%(26/138)に達したと言います。
またアメリカ・タフツ大学の調査チームは2000年1月から3月の期間、12のメーカーが製造している42のキャットフードを対象とし、中に含まれるイソフラボン濃度を分析しました。その結果、ゲニステインとダイゼインが57%(1~163μg/g)の割合で検出されたと言います。また大豆フードを猫が食べ続けた場合の1日摂取量は、体重1kg当たり0.6~4.5mgと推計されました。この値は、人間においてステロイドホルモンや甲状腺ホルモンの血清濃度に影響を及ぼす2mg/kgに近いレベルです。
ニュージーランド・マッセー大学を中心としたチームは大豆を原料として使った市販のキャットフードを合計138種類を購入し、中に含まれるイソフラボンの濃度を分析しました。その結果、ドライやウエットに関わらずすべての商品カテゴリからイソフラボンがまんべんなく検出されたといいます。イソフラボンの中で最も多く含まれていたのはダイゼイン(70%)で、次がゲニステイン(48%)という順でした。1日における摂取量の中央値を推測した所、猫の体重1kg当たり「0.03mg~1.47mg」となり、人間において設定されている摂取上限値2mg/kgを超えていた商品の割合は19%(26/138)に達したと言います。
またアメリカ・タフツ大学の調査チームは2000年1月から3月の期間、12のメーカーが製造している42のキャットフードを対象とし、中に含まれるイソフラボン濃度を分析しました。その結果、ゲニステインとダイゼインが57%(1~163μg/g)の割合で検出されたと言います。また大豆フードを猫が食べ続けた場合の1日摂取量は、体重1kg当たり0.6~4.5mgと推計されました。この値は、人間においてステロイドホルモンや甲状腺ホルモンの血清濃度に影響を及ぼす2mg/kgに近いレベルです。
大豆フードと甲状腺ホルモン
大豆を原料としたフードを食べた猫の体内では、甲状腺ホルモンの一種であるサイロキシン(T4)の濃度が上昇するようです。
アメリカ・タフツ大学の調査チームは18頭の臨床上健康な猫を対象とし、大豆含有フードと大豆を含有しないフードを3ヶ月ずつ給餌したとき、血清甲状腺ホルモン濃度や尿中イソフラボン濃度がどのように変化するのかを検証しました。その結果、大豆含有食品を給餌されていた期間においてはT3(トリヨードサイロニン)値がそのままでT4(サイロキシン)値だけが増えるという現象が確認されたと言います。こうした事実から、イソフラボンを摂取した猫の体内ではT4からT3に変換する酵素が阻害されたか、もしくはT3クリアランスが促進されたのではないかと推測されています。
アメリカ・タフツ大学の調査チームは18頭の臨床上健康な猫を対象とし、大豆含有フードと大豆を含有しないフードを3ヶ月ずつ給餌したとき、血清甲状腺ホルモン濃度や尿中イソフラボン濃度がどのように変化するのかを検証しました。その結果、大豆含有食品を給餌されていた期間においてはT3(トリヨードサイロニン)値がそのままでT4(サイロキシン)値だけが増えるという現象が確認されたと言います。こうした事実から、イソフラボンを摂取した猫の体内ではT4からT3に変換する酵素が阻害されたか、もしくはT3クリアランスが促進されたのではないかと推測されています。
猫のイソフラボン代謝
犬と猫が同じ大豆原料の食事を食べても、猫でだけ甲状腺機能亢進症の発症が見られることから、体内における何らかの代謝経路が疾患の発症に関わっているものと推測されています。具体的には、イソフラボンの代謝を司る「グルクロン酸抱合」と呼ばれる経路です。
アメリカ・ワシントン州立大学の調査チームは、犬と猫を含む13種類の動物を対象とし、動物間で見られるイソフラボン代謝能力の違いを検証しました。その結果、大豆由来のイソフラボンを代謝する際、猫の体内ではグルクロン酸抱合がメインの代謝回路ではなく、硫酸抱合などその他の回路が機能している可能性が浮上してきたと言います。
犬ではグルクロン酸抱合と硫酸抱合の両方でイソフラボンを代謝できるのに対し、猫では硫酸抱合でしか代謝できません。要するに硫酸化による代謝に不具合が生じたときのバックアップシステムがないということです。猫特有のこの体質が、体内におけるイソフラボン濃度の上昇、およびその結果としての甲状腺機能亢進症に関わっているのではないかと推測されています。
アメリカ・ワシントン州立大学の調査チームは、犬と猫を含む13種類の動物を対象とし、動物間で見られるイソフラボン代謝能力の違いを検証しました。その結果、大豆由来のイソフラボンを代謝する際、猫の体内ではグルクロン酸抱合がメインの代謝回路ではなく、硫酸抱合などその他の回路が機能している可能性が浮上してきたと言います。
犬ではグルクロン酸抱合と硫酸抱合の両方でイソフラボンを代謝できるのに対し、猫では硫酸抱合でしか代謝できません。要するに硫酸化による代謝に不具合が生じたときのバックアップシステムがないということです。猫特有のこの体質が、体内におけるイソフラボン濃度の上昇、およびその結果としての甲状腺機能亢進症に関わっているのではないかと推測されています。
イソフラボン代謝遺伝子
完全肉食動物である猫の体は、そもそも遺伝子レベルで大豆を食べるようにはできていないのかもしれません。
猫およびネコ科動物においては「UGT1A6遺伝子」が偽遺伝子になっており、「UGT1A6」が全く生成されないことが確認されています。「UGT1A6」とはフェノール類のグルクロン酸抱合を促す酵素のことであり、イソフラボンを代謝するときに重要となる分子のことです。また「UGT1A9」と呼ばれるグルクロン酸転移酵素が肝細胞から完全に欠落していることも確認されています。
こうした生理学・遺伝学的な事実から考えると、イソフラボンを摂取した猫は人間や犬のようにグルクロン酸抱合という経路では代謝できないことが見えてきます。その代わりに猫が使っているのが硫酸化という代謝経路です。しかしこの経路はグルクロン酸抱合に比べて枯渇しやすく、すぐに限界が来てしまいます。
ニュージーランド・マッセー大学の調査チームは、猫が大量のイソフラボンを摂取すると代謝が追いつかず、非抱合型のイソフラボンが体内に蓄積し、生理活性を示す可能性があると指摘しています。要するに、日常的に大豆含有のキャットフードを食べている猫では、慢性的にイソフラボン濃度が高くなり、人間や犬の体内では見られないような悪影響(代償性の甲状腺機能亢進症など)が現れる可能性があるということです。
猫およびネコ科動物においては「UGT1A6遺伝子」が偽遺伝子になっており、「UGT1A6」が全く生成されないことが確認されています。「UGT1A6」とはフェノール類のグルクロン酸抱合を促す酵素のことであり、イソフラボンを代謝するときに重要となる分子のことです。また「UGT1A9」と呼ばれるグルクロン酸転移酵素が肝細胞から完全に欠落していることも確認されています。
こうした生理学・遺伝学的な事実から考えると、イソフラボンを摂取した猫は人間や犬のようにグルクロン酸抱合という経路では代謝できないことが見えてきます。その代わりに猫が使っているのが硫酸化という代謝経路です。しかしこの経路はグルクロン酸抱合に比べて枯渇しやすく、すぐに限界が来てしまいます。
ニュージーランド・マッセー大学の調査チームは、猫が大量のイソフラボンを摂取すると代謝が追いつかず、非抱合型のイソフラボンが体内に蓄積し、生理活性を示す可能性があると指摘しています。要するに、日常的に大豆含有のキャットフードを食べている猫では、慢性的にイソフラボン濃度が高くなり、人間や犬の体内では見られないような悪影響(代償性の甲状腺機能亢進症など)が現れる可能性があるということです。
飼い主の注意・心がけ
大豆を原料としたキャットフードにはほぼ確実にイソフラボンが含まれているため、フードを食べた猫はこの物質を体内で代謝する必要が生じます。犬ではグルクロン酸抱合と硫酸抱合の二重体制で代謝に当たっていますが、猫の体内には硫酸化経路しかありません。その結果、大豆含有フードを大量に食べたり長期的に食べ続けると、代謝しきれなかった非抱合型イソフラボンの体内濃度が高くなり、甲状腺機能亢進症を発症する危険性が生じます。完全に解明されたわけではありませんが、「大豆=ヘルシー」という固定観念は猫には当てはまらないと考えたほうが無難でしょう。
グレインフリーに注意!
近年、欧米を中心として「グレインフリー」と呼ばれるペットフードが人気を博しています。これは小麦やトウモロコシなど特定の穀物を原料から取り除いたフードのことで、背景にあるのは「小麦アレルギーを避ける」という体質上の理由や、「野生環境に近い食事が1番良い!」という思い込みです。
しかし2018年7月、アメリカのFDA(食品医薬品局)が「グレインフリーのドッグフードと犬の拡張型心筋症との間に因果関係があるかもしれない」という注意喚起を行ったことから、ちょっとした騒動を引き起こしました(→詳しくは姉妹サイト内「グレインフリーのドッグフードと犬の拡張型心筋症の関係」をご参照ください)。この因果関係は猫においては確認されていないものの、グレインフリーのキャットフードには豆類やいも類が原料として多く用いられています。ラベルの先頭や前の方に「大豆」と記載されている場合、含有量が多いということです。キャットフードにはタウリンが添加されているため拡張型心筋症を引き起こす事はないでしょうが、大豆に含まれるイソフラボンによって甲状腺機能亢進症を発症してしまうかもしれません。
「グレインフリー=健康」という安直な思い込みは捨てた方が賢明だと思われます。
しかし2018年7月、アメリカのFDA(食品医薬品局)が「グレインフリーのドッグフードと犬の拡張型心筋症との間に因果関係があるかもしれない」という注意喚起を行ったことから、ちょっとした騒動を引き起こしました(→詳しくは姉妹サイト内「グレインフリーのドッグフードと犬の拡張型心筋症の関係」をご参照ください)。この因果関係は猫においては確認されていないものの、グレインフリーのキャットフードには豆類やいも類が原料として多く用いられています。ラベルの先頭や前の方に「大豆」と記載されている場合、含有量が多いということです。キャットフードにはタウリンが添加されているため拡張型心筋症を引き起こす事はないでしょうが、大豆に含まれるイソフラボンによって甲状腺機能亢進症を発症してしまうかもしれません。
「グレインフリー=健康」という安直な思い込みは捨てた方が賢明だと思われます。
ベジタリアンフードに注意!
宗教的もしくは道徳的な信念から、自分のペットに動物の肉を食べさせたくないという飼い主が一部にいます。そういう人たちが選ぶのが、ペット向けのベジタリアンフードやビーガンフードです。
こうしたフードには植物由来のタンパク質が含まれており、大豆が原料となっていることもしばしばあります。「ベジタリアンフードに切り替えてペットの体調が良くなった」といった飼い主の逸話的な報告がある一方、長期的に給餌した時の影響に関してはよくわかっていないという現実があります。 大豆を原料としたベジタリアンフードを猫に与えたとき、硫酸化による抱合代謝がありますので1週間くらいは何の問題もないかもしれません。しかし半年~1年と同じキャットフードを与え続けたらどうでしょう?慢性的なイソフラボンの刺激により甲状腺が変調をきたし、機能亢進症に陥ってしまう可能性は否定できないでしょう。
こうしたフードには植物由来のタンパク質が含まれており、大豆が原料となっていることもしばしばあります。「ベジタリアンフードに切り替えてペットの体調が良くなった」といった飼い主の逸話的な報告がある一方、長期的に給餌した時の影響に関してはよくわかっていないという現実があります。 大豆を原料としたベジタリアンフードを猫に与えたとき、硫酸化による抱合代謝がありますので1週間くらいは何の問題もないかもしれません。しかし半年~1年と同じキャットフードを与え続けたらどうでしょう?慢性的なイソフラボンの刺激により甲状腺が変調をきたし、機能亢進症に陥ってしまう可能性は否定できないでしょう。
猫の体質を考慮して
猫のグルクロン酸抱合代謝能力は、遺伝子レベルで極めて低い状態に抑えられています。キャットフードの中にこの経路を使わなければ代謝できないような成分が含まれている場合、代謝しきれなかった分が体内に蓄積し、何らかの影響を及ぼしてしまう危険性が常にあります。例えばかつお節に含まれる発ガン性物質ベンゾ[a]ピレンや、魚介類に含まれるPBDEなどです。
猫も人間や犬と同じように大豆イソフラボンを代謝できますが、グルクロン酸抱合ではなく硫酸化というちょっと変わった経路を用いています。代謝しきれなかったイソフラボンが甲状腺に悪影響を及ぼす危険性がありますので念頭に置いておきましょう。
ちなみにニュージーランドやアメリカで行われた調査では「キャットフードの値段が安いほど高い濃度でイソフラボンが検出された」と報告されています。大豆は非常に安価なタンパク源であり、原価を抑えたいペットフードメーカーにとっては魅力的な素材です。しかし猫にとっては「安かろう悪かろう」になってしまうかもしれませんので、安易に値段でペットフードを選ぶのではなく、しっかりとラベルを確認したほうがよいでしょう。
なお食品安全委員会によると、人間におけるイソフラボンの摂取量目安は、体重1kg当たりが2mg弱、1日のトータル摂取量が70~75mgとされています。猫における目安はまったくわかっていませんので、便宜上、人間向けの値を転用するしかありません。逆にラットにおける最小中毒量(TDLo)は体重1kg当たり5mgとされていますので摂りすぎには要注意です。
ちなみにニュージーランドやアメリカで行われた調査では「キャットフードの値段が安いほど高い濃度でイソフラボンが検出された」と報告されています。大豆は非常に安価なタンパク源であり、原価を抑えたいペットフードメーカーにとっては魅力的な素材です。しかし猫にとっては「安かろう悪かろう」になってしまうかもしれませんので、安易に値段でペットフードを選ぶのではなく、しっかりとラベルを確認したほうがよいでしょう。
なお食品安全委員会によると、人間におけるイソフラボンの摂取量目安は、体重1kg当たりが2mg弱、1日のトータル摂取量が70~75mgとされています。猫における目安はまったくわかっていませんので、便宜上、人間向けの値を転用するしかありません。逆にラットにおける最小中毒量(TDLo)は体重1kg当たり5mgとされていますので摂りすぎには要注意です。
猫とイソフラボンに関する研究
以下でご紹介するのは、猫と大豆イソフラボンに関して行われた調査報告です。原文リンクを張りましたのでご興味のある方はご自身で精読してみてください。
マッセー大学(2006年)
ダイズを原料として使っているキャットフードには、生殖機能、内分泌バランス、免疫機能に影響を及ぼすレベルのイソフラボンが含まれているかもしれません。
ニュージーランド・マッセー大学を中心としたチームはダイズを原料として使った市販のキャットフードをスーパーマーケット(117種)、ペット用品店(6種)、動物病院(15種)から合計138種類購入し、中に含まれるイソフラボンの濃度を分析しました。
商品を「ドライ-ダイズ含有(13種)」「ドライ-非ダイズ植物含有(52種)」「ウエット-ダイズ含有(7種)」「ウエット-非ダイズ植物(43種)」「ウエット-肉類(23種)」という5つのカテゴリに分類した所、すべての商品カテゴリからイソフラボンがまんべんなく検出されたといいます。検出可能レベルである「1.56μg/g」を超えていた割合は全体の75%(104/138)で、ウエットフード(83/138=60%)よりもドライフード(127/138=92%)において高い含有率が確認されました。
イソフラボンの中で最も多く含まれていたのはダイゼイン(97/138=70%)で、次いでゲニステイン(66/138=48%)、バイオカニンA(25/138=18%)、ホルモノネチン(7/138=5%)という順でした。
1日における摂取量の中央値を推測した所、「ウエット-肉類」の場合が猫の体重1kg当たり「0.03mg/kg」、「ウエット+ダイズ含有」の場合が「1.47mg/kg」、最もイソフラボンの含有量が多かった商品の場合が「8.13mg/kg」となりました。また人間において設定されている摂取上限値2mg/kgを超えていた商品の割合は19%(26/138)に達したと言います。 The isoflavone content of commercially-available feline diets in New Zealand
KM Bell, SM Rutherfurd, WH Hendriks, New Zealand Veterinary Journal 54:3 103-108, DOI: 10.1080/00480169.2006.36620
ニュージーランド・マッセー大学を中心としたチームはダイズを原料として使った市販のキャットフードをスーパーマーケット(117種)、ペット用品店(6種)、動物病院(15種)から合計138種類購入し、中に含まれるイソフラボンの濃度を分析しました。
商品を「ドライ-ダイズ含有(13種)」「ドライ-非ダイズ植物含有(52種)」「ウエット-ダイズ含有(7種)」「ウエット-非ダイズ植物(43種)」「ウエット-肉類(23種)」という5つのカテゴリに分類した所、すべての商品カテゴリからイソフラボンがまんべんなく検出されたといいます。検出可能レベルである「1.56μg/g」を超えていた割合は全体の75%(104/138)で、ウエットフード(83/138=60%)よりもドライフード(127/138=92%)において高い含有率が確認されました。
イソフラボンの中で最も多く含まれていたのはダイゼイン(97/138=70%)で、次いでゲニステイン(66/138=48%)、バイオカニンA(25/138=18%)、ホルモノネチン(7/138=5%)という順でした。
1日における摂取量の中央値を推測した所、「ウエット-肉類」の場合が猫の体重1kg当たり「0.03mg/kg」、「ウエット+ダイズ含有」の場合が「1.47mg/kg」、最もイソフラボンの含有量が多かった商品の場合が「8.13mg/kg」となりました。また人間において設定されている摂取上限値2mg/kgを超えていた商品の割合は19%(26/138)に達したと言います。 The isoflavone content of commercially-available feline diets in New Zealand
KM Bell, SM Rutherfurd, WH Hendriks, New Zealand Veterinary Journal 54:3 103-108, DOI: 10.1080/00480169.2006.36620
マッセー大学(2013年)
完全肉食動物である猫は、体内におけるフェノール類の解毒代謝経路が劣るため、イソフラボンが抱合(※代謝の一種)作用を受けない状態で高濃度で循環しているのではないかと考えられてきました。しかし実際はある程度の代謝能力を持っているようです。
ニュージーランド・マッセー大学の調査チームは、ダイズ抽出物タブレットを6頭に、ダイズ含有フードを4頭に給餌した後、血漿中のイソフラボン代謝産物を調べました。その結果、当初の予測に反して非抱合型の割合が非常に少なかったといいます。具体的にはゲニステインが非抱合型もしくは一硫酸、ダイゼインが一硫酸もしくは二硫酸もしくは非抱合型という形で検出されたとのこと。一方、β-グルクロン酸抱合物が猫の血清中から検出されなかったことから、グルクロン酸抱合能力は低いものと推測されました。
こうした結果から調査チームは、猫におけるイソフラボン(ゲニステインとダイゼイン)の抱合には、人間やげっ歯類のようなグルクロン酸ではなく硫酸が関与している可能性が高いとの結論に至りました。また硫酸化による抱合はグルクロン酸抱合に比べて飽和状態に達するのが早いため、大量のイソフラボンを摂取すると代謝が追いつかず、非抱合型のイソフラボンが体内に蓄積し、生理活性を示す可能性があるとも。非抱合型のイソフラボンの方が生理活性が高いため、長期的にイソフラボンを摂取している猫においては、生殖機能や内分泌機能に変調をきたしてもおかしくないと推測されています。 Isoflavone metabolism in domestic cats (Felis catus): Comparison of plasma metabolites detected after ingestion of two different dietary forms of genistein and daidzein
K. M. Whitehouse-Tedd, N. J. Cave, et al., American Society of Animal Science(2013) 91:1295?1306, doi:10.2527/jas2011-4812
ニュージーランド・マッセー大学の調査チームは、ダイズ抽出物タブレットを6頭に、ダイズ含有フードを4頭に給餌した後、血漿中のイソフラボン代謝産物を調べました。その結果、当初の予測に反して非抱合型の割合が非常に少なかったといいます。具体的にはゲニステインが非抱合型もしくは一硫酸、ダイゼインが一硫酸もしくは二硫酸もしくは非抱合型という形で検出されたとのこと。一方、β-グルクロン酸抱合物が猫の血清中から検出されなかったことから、グルクロン酸抱合能力は低いものと推測されました。
こうした結果から調査チームは、猫におけるイソフラボン(ゲニステインとダイゼイン)の抱合には、人間やげっ歯類のようなグルクロン酸ではなく硫酸が関与している可能性が高いとの結論に至りました。また硫酸化による抱合はグルクロン酸抱合に比べて飽和状態に達するのが早いため、大量のイソフラボンを摂取すると代謝が追いつかず、非抱合型のイソフラボンが体内に蓄積し、生理活性を示す可能性があるとも。非抱合型のイソフラボンの方が生理活性が高いため、長期的にイソフラボンを摂取している猫においては、生殖機能や内分泌機能に変調をきたしてもおかしくないと推測されています。 Isoflavone metabolism in domestic cats (Felis catus): Comparison of plasma metabolites detected after ingestion of two different dietary forms of genistein and daidzein
K. M. Whitehouse-Tedd, N. J. Cave, et al., American Society of Animal Science(2013) 91:1295?1306, doi:10.2527/jas2011-4812
タフツ大学(2002年)
ダイズを主原料とした市販のキャットフードを食べ続けていると、知らない間に甲状腺腫を発症してしまうかもしれません。
アメリカ・タフツ大学の調査チームは2000年1月から3月の期間、12のメーカーが製造している42のキャットフードを対象とし、中に含まれるイソフラボン濃度を分析しました。ドライフード(14種)、セミモイストフード(6種)、ウェットフード(22種)を調べた所、ゲニステインとダイゼインが57%(24/42, 1~163μg/g)の割合で検出されたと言います。固形ダイズ含有フードのイソフラボン含有率は38%(16/42, 11μg/g超)、ドライフードの含有率は93%(13/14)、セミモイストフードは100%(6/6)、ウェットフードは23%(5/22)という内訳でした。また、フードの価格が安いほどイソフラボンの含有濃度が高かったとも。
大豆フードを猫が食べ続けた場合の1日摂取量は、体重5kgの猫が1日50~100g食べるとした場合、体重1kg当たり0.6~4.5mgと推計されました。この値は、人間においてステロイドホルモンや甲状腺ホルモンの血清濃度に影響を及ぼす2mg/kgに近いレベルです。
甲状腺機能亢進症の発症メカニズムとしては「大豆由来のイソフラボン摂取→甲状腺ペロオキシダーゼの阻害→甲状腺ホルモン合成低下→代償性甲状腺ホルモン刺激ホルモン(TSH)増加→細胞内における過酸化水素濃度の上昇→遺伝子の変異→甲状腺腫→甲状腺機能亢進症」などが想定されます。猫においては硫酸化により摂取したイソフラボンをある程度は代謝できるものの、すぐ飽和状態になるため、体内で高濃度に蓄積すると甲状腺ペロオキシダーゼ(※甲状腺ホルモンの合成に不可欠な酵素)を阻害してしまうことがあるかもしれません。 Identification and concentration of soy isoflavones in commercial cat foods
Michael H. Court, BVSc, PhD,and Lisa M. Freeman, DVM, PhD, AJVR, Vol 63, No. 2, February 2002
アメリカ・タフツ大学の調査チームは2000年1月から3月の期間、12のメーカーが製造している42のキャットフードを対象とし、中に含まれるイソフラボン濃度を分析しました。ドライフード(14種)、セミモイストフード(6種)、ウェットフード(22種)を調べた所、ゲニステインとダイゼインが57%(24/42, 1~163μg/g)の割合で検出されたと言います。固形ダイズ含有フードのイソフラボン含有率は38%(16/42, 11μg/g超)、ドライフードの含有率は93%(13/14)、セミモイストフードは100%(6/6)、ウェットフードは23%(5/22)という内訳でした。また、フードの価格が安いほどイソフラボンの含有濃度が高かったとも。
大豆フードを猫が食べ続けた場合の1日摂取量は、体重5kgの猫が1日50~100g食べるとした場合、体重1kg当たり0.6~4.5mgと推計されました。この値は、人間においてステロイドホルモンや甲状腺ホルモンの血清濃度に影響を及ぼす2mg/kgに近いレベルです。
甲状腺機能亢進症の発症メカニズムとしては「大豆由来のイソフラボン摂取→甲状腺ペロオキシダーゼの阻害→甲状腺ホルモン合成低下→代償性甲状腺ホルモン刺激ホルモン(TSH)増加→細胞内における過酸化水素濃度の上昇→遺伝子の変異→甲状腺腫→甲状腺機能亢進症」などが想定されます。猫においては硫酸化により摂取したイソフラボンをある程度は代謝できるものの、すぐ飽和状態になるため、体内で高濃度に蓄積すると甲状腺ペロオキシダーゼ(※甲状腺ホルモンの合成に不可欠な酵素)を阻害してしまうことがあるかもしれません。 Identification and concentration of soy isoflavones in commercial cat foods
Michael H. Court, BVSc, PhD,and Lisa M. Freeman, DVM, PhD, AJVR, Vol 63, No. 2, February 2002
タフツ大学(2004年)
大豆を原料としたフードを食べた猫の体内では、甲状腺ホルモンの一種であるサイロキシン(T4)の濃度が上昇するようです。
アメリカ・タフツ大学の調査チームは18頭の臨床上健康な猫(年齢中央値5歳 | 平均5.1kg)を対象とし、大豆含有フードと大豆を含有しないフードを3ヶ月ずつ給餌したとき、血清甲状腺ホルモン濃度や尿中イソフラボン濃度がどのように変化するのかを検証しました。
その結果、大豆含有食品を給餌されていた期間においては総T4上昇(8%)、遊離T4上昇(14%)、総T3(トリヨードサイロニン)は不変、T4/T3比低下という変化が見られたといいます。また遊離T4に関し、検出上限値を超えた割合が介入前後で1/18→4/18に増加したとも。
T3値がそのままでT4値だけが増えるという現象に関し調査チームは、T4からT3に変換する酵素(5'-ヨードチロニンデヨージナーゼ)が阻害されたか、もしくはT3クリアランスが促進されたのではないかと推測しています。 Effect of dietary soy on serum thyroid hormone concentrations in healthy adult cats
Heidi L. White, DVM; Lisa M. Freeman, AJVR Vol65 No.5 May 2004
アメリカ・タフツ大学の調査チームは18頭の臨床上健康な猫(年齢中央値5歳 | 平均5.1kg)を対象とし、大豆含有フードと大豆を含有しないフードを3ヶ月ずつ給餌したとき、血清甲状腺ホルモン濃度や尿中イソフラボン濃度がどのように変化するのかを検証しました。
その結果、大豆含有食品を給餌されていた期間においては総T4上昇(8%)、遊離T4上昇(14%)、総T3(トリヨードサイロニン)は不変、T4/T3比低下という変化が見られたといいます。また遊離T4に関し、検出上限値を超えた割合が介入前後で1/18→4/18に増加したとも。
T3値がそのままでT4値だけが増えるという現象に関し調査チームは、T4からT3に変換する酵素(5'-ヨードチロニンデヨージナーゼ)が阻害されたか、もしくはT3クリアランスが促進されたのではないかと推測しています。 Effect of dietary soy on serum thyroid hormone concentrations in healthy adult cats
Heidi L. White, DVM; Lisa M. Freeman, AJVR Vol65 No.5 May 2004
ワシントン州立大学(2015年)
犬と猫が同じダイズ原料の食事を食べても、猫でだけ甲状腺機能亢進症の発症が見られることから、体内における何らかの代謝経路が疾患の発症に関わっているものと推測されています。具体的には、イソフラボンの代謝を司るグルクロン酸抱合と呼ばれる経路です。
アメリカ・ワシントン州立大学の調査チームは、犬と猫を含む13種類の動物を対象とし、動物間で見られるイソフラボン代謝能力の違いを検証しました。その結果、猫の代謝に関して以下のような特徴が見られたと言います。
それに対し猫の尿中では、元物質であるダイゼインの10%を超える濃度で検出されたといいます。エクオールはエストロゲン受容器と親和性が強く、ダイゼインよりも抗アンドロゲン 作用や抗酸化作用が強い物質です。猫の体内でエクオールが高濃度で循環しているのだとすると、何らかの生理学的な作用をもたらしてもおかしくないと考えられます。
猫、マングース、フェレットといった肉食動物においては、ゲニステイン、ダイゼインとエクオールのグルクロン酸抱合が人間や犬に比べて低い値を示しました。可能性として考えられるのは、フェノール類のグルクロン酸抱合を促進する酵素を生成する「UGT1A6遺伝子」の欠落です。しかし猫およびネコ科動物においては偽遺伝子であることが確認されているものの、マングースやフェレットではしっかり機能しています。また「UGT1A1」と呼ばれる酵素の質、量、活性度の問題ではないことも同時に確認されました。最終的に調査チームは、「UGT1A」のサブファミリーに相当する「UGT1A9」と呼ばれる酵素の欠落が、グルクロン酸抱合能力を低下させているのではないかとの推論に至りました。猫では完全に欠落しているこの酵素は、マングースやフェレットでもおそらく欠落(もしくは低活性)状態にあるものと推測されています。 Soy isoflavone metabolism in cats compared with other species: urinary metabolite concentrations and glucuronidation by liver microsomes
Joanna M. Redmon, Binu Shrestha, Rosario Cerundolo, Michael H. Court, Xenobiotica(2015), doi.org/10.3109/00498254.2015.1086038
アメリカ・ワシントン州立大学の調査チームは、犬と猫を含む13種類の動物を対象とし、動物間で見られるイソフラボン代謝能力の違いを検証しました。その結果、猫の代謝に関して以下のような特徴が見られたと言います。
猫で特徴的に見られるイソフラボン代謝
- ゲニステイン、ダイゼイン、グリシテイン、ジヒドロゲニステイン、ジヒドロダイゼイン、腸内細菌による代謝産物は犬と猫両方の尿サンプルから抱合型で検出された
- 抱合型エクオールは猫の尿から検出されたが犬ではほとんど検出されなかった
- グルクロン酸抱合を促進するβ-グルクロニダーゼを投与したところ、犬ではすべての代謝産物のグルクロン酸抱合が促進されたのに対し、猫ではダイゼイン(11%↑)とグリシテイン(37%↑)だけが促進された
- ゲニステイン、ダイゼイン、エクオールの3つに関し、猫におけるグルクロン酸抱合率は常に13動物種中最下位3位以内だった。これと同じ傾向を見せたのはフェレットとマングースだった
- 犬とは違い猫の消化管内ではエクオールが生成され、おそらく腸内細菌叢が関わっている
- 大豆由来のイソフラボンを代謝する際、猫の体内ではグルクロン酸抱合がメインの代謝回路ではなく、硫酸化などその他の回路が機能している
それに対し猫の尿中では、元物質であるダイゼインの10%を超える濃度で検出されたといいます。エクオールはエストロゲン受容器と親和性が強く、ダイゼインよりも抗アンドロゲン 作用や抗酸化作用が強い物質です。猫の体内でエクオールが高濃度で循環しているのだとすると、何らかの生理学的な作用をもたらしてもおかしくないと考えられます。
猫、マングース、フェレットといった肉食動物においては、ゲニステイン、ダイゼインとエクオールのグルクロン酸抱合が人間や犬に比べて低い値を示しました。可能性として考えられるのは、フェノール類のグルクロン酸抱合を促進する酵素を生成する「UGT1A6遺伝子」の欠落です。しかし猫およびネコ科動物においては偽遺伝子であることが確認されているものの、マングースやフェレットではしっかり機能しています。また「UGT1A1」と呼ばれる酵素の質、量、活性度の問題ではないことも同時に確認されました。最終的に調査チームは、「UGT1A」のサブファミリーに相当する「UGT1A9」と呼ばれる酵素の欠落が、グルクロン酸抱合能力を低下させているのではないかとの推論に至りました。猫では完全に欠落しているこの酵素は、マングースやフェレットでもおそらく欠落(もしくは低活性)状態にあるものと推測されています。 Soy isoflavone metabolism in cats compared with other species: urinary metabolite concentrations and glucuronidation by liver microsomes
Joanna M. Redmon, Binu Shrestha, Rosario Cerundolo, Michael H. Court, Xenobiotica(2015), doi.org/10.3109/00498254.2015.1086038