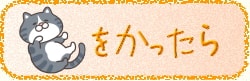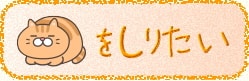詳細
調査を行ったのは、ニュージーランド・マッセー大学のチーム。2010年7月から2013年4月の期間、大学内で栄養学的な調査を行うために飼育されている猫たちを対象とし、調査スタート時点、5ヶ月時点、12ヶ月時点、16ヶ月時点、33ヶ月時点というタイミングで尿を採取して「無症候性細菌尿」の割合を算出しました。
 無症候性細菌尿の感染率と猫のプロファイルを組み合わせて調査したところ、細菌尿と体重、血清クレアチニン濃度、寿命との間に統計的な関係性は見られなかったといいます。
無症候性細菌尿の感染率と猫のプロファイルを組み合わせて調査したところ、細菌尿と体重、血清クレアチニン濃度、寿命との間に統計的な関係性は見られなかったといいます。
こうした結果から調査チームは、7歳以上のシニア猫においては無症候性細菌尿が10~13%の割合で見られ、メス猫の方がオス猫より21.2倍かかりやすいとの傾向を明らかにしました。ただし調査対象となった猫の数が少ないため、この数値を全ての猫に一般化するのは早計だとも。また耐性菌の獲得につながるリスクがあることから、症状を示していない猫に対して抗菌薬をスタンダードな治療法として採用するべきではないとしています。 Subclinical Bacteriuria in Older Cats and its Association with Survival.
White, J.D., Cave, N.J., Grinberg, A., Thomas, D.G. and Heuer, C. (2016), J Vet Intern Med, 30: 1824?1829. doi:10.1111/jvim.14598
- 無症候性細菌尿
- 何の症状もないが尿中の細菌数が正常値を超えている状態。当調査では「1,000cfu/mL超」が細菌尿の判定基準と設定された(※cfu=colony forming units)。

 無症候性細菌尿の感染率と猫のプロファイルを組み合わせて調査したところ、細菌尿と体重、血清クレアチニン濃度、寿命との間に統計的な関係性は見られなかったといいます。
無症候性細菌尿の感染率と猫のプロファイルを組み合わせて調査したところ、細菌尿と体重、血清クレアチニン濃度、寿命との間に統計的な関係性は見られなかったといいます。こうした結果から調査チームは、7歳以上のシニア猫においては無症候性細菌尿が10~13%の割合で見られ、メス猫の方がオス猫より21.2倍かかりやすいとの傾向を明らかにしました。ただし調査対象となった猫の数が少ないため、この数値を全ての猫に一般化するのは早計だとも。また耐性菌の獲得につながるリスクがあることから、症状を示していない猫に対して抗菌薬をスタンダードな治療法として採用するべきではないとしています。 Subclinical Bacteriuria in Older Cats and its Association with Survival.
White, J.D., Cave, N.J., Grinberg, A., Thomas, D.G. and Heuer, C. (2016), J Vet Intern Med, 30: 1824?1829. doi:10.1111/jvim.14598

解説
過去に行われた調査では、高齢とメスであることが尿路感染症のリスクファクターであると報告されています。今回の調査でもメス猫の方がオス猫よりも20倍以上無症候性細菌尿にかかりやすいことが示されましたので「無症候性細菌尿→症候性尿路感染症」というつながりがあるのかもしれません。おそらく尿道が短いなど、泌尿器系の解剖学的な構造が影響しているものと推測されます。
犬における無症候性細菌尿は、糖尿病、副腎皮質機能亢進症、プレドニゾロンの長期的な投与を受けている場合に多いと報告されています。猫では慢性腎不全、糖尿病、甲状腺機能亢進症を持病として抱えている場合に多く発症するとされていますが、因果関係については証明されていません。例えば今回の調査でも、腎不全の兆候を見せた猫ではほとんどが陰性でした。ですから、細菌尿が腎不全などの症状の引き金になっているという可能性は薄いのでしょう。
陽性と出た28サンプル中、細菌種が同定されたのは20サンプルで、尿路感染症を引き起こすものと同じ「グラム陰性桿菌」、「大腸菌」、「コアグラーゼ陰性ブドウ球菌」などが多かったと言います。菌が同じであるにもかかわらず症状を示したり示さなかったりする理由は、宿主の免疫力や菌の系統に個体差があったからではないかと推測されています。
人間の老齢女性を対象とした調査では、健康だろうと糖尿病を抱えていようと、無症候性細菌尿を治療することで症候性の尿路感染症、腎盂腎炎、腎不全、寿命の短縮化につながることはなかったとされています。むやみに抗生物質を投与してしまうと、耐性菌だけが生き残って宿主の健康を逆に害してしまう可能性があるため、基本的なアプローチ法は「静観」であると推奨されています。要するに、尿の中から正常範囲以上の細菌が検出されても、症状を引き起こしていないのであればひとまず様子を見ましょう、ということです。