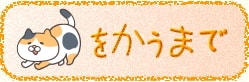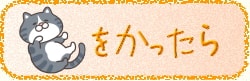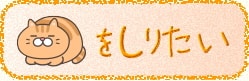外に出る猫の平均寿命は短い
以下に示すのはペットフード協会が公開している猫の平均寿命です。青い棒グラフが「外に出る機会がある猫」、緑色の棒グラフが「完全室内飼いの猫」を表しています。
全国犬猫飼育実態調査
 2014~2018年における両者の平均寿命を比較すると、外に出る猫が13.7歳であるのに対し、外に出ない猫では15.9歳となっています。こうした2歳半以上の寿命の差は、以下で解説するような様々な外飼いリスクによって生まれたものだと推測されます。
2014~2018年における両者の平均寿命を比較すると、外に出る猫が13.7歳であるのに対し、外に出ない猫では15.9歳となっています。こうした2歳半以上の寿命の差は、以下で解説するような様々な外飼いリスクによって生まれたものだと推測されます。
これから猫を飼う方も、すでに猫を飼っている方も、猫を外に出すことで寿命を縮めているという自覚を持ち、しっかりと完全室内飼いを徹底する必要があります。では具体的にどのようなメリットやデメリットが有るのでしょうか?徹底的に比較してみましょう!
↓NEXT:室内飼いのメリット
 2014~2018年における両者の平均寿命を比較すると、外に出る猫が13.7歳であるのに対し、外に出ない猫では15.9歳となっています。こうした2歳半以上の寿命の差は、以下で解説するような様々な外飼いリスクによって生まれたものだと推測されます。
2014~2018年における両者の平均寿命を比較すると、外に出る猫が13.7歳であるのに対し、外に出ない猫では15.9歳となっています。こうした2歳半以上の寿命の差は、以下で解説するような様々な外飼いリスクによって生まれたものだと推測されます。これから猫を飼う方も、すでに猫を飼っている方も、猫を外に出すことで寿命を縮めているという自覚を持ち、しっかりと完全室内飼いを徹底する必要があります。では具体的にどのようなメリットやデメリットが有るのでしょうか?徹底的に比較してみましょう!
↓NEXT:室内飼いのメリット
完全室内飼いのメリット
 完全室内飼いとは文字通り室内のみで飼う方法で、基本的に猫は家の外に出ません。放し飼いとは、猫が自由に外と家を行き来できるような飼い方で、サザエさんの「タマ」をご想像頂けると分かりやすいかと思います。
完全室内飼いとは文字通り室内のみで飼う方法で、基本的に猫は家の外に出ません。放し飼いとは、猫が自由に外と家を行き来できるような飼い方で、サザエさんの「タマ」をご想像頂けると分かりやすいかと思います。結論から申し上げると、都会などで猫を飼おうとする場合は「完全室内飼い」が望ましいでしょう。以下では「完全室内飼い」のメリット、及び「放し飼い」のデメリットを列挙(れっきょ)しますので、なぜ「完全室内飼い」が薦められるのかの参考にして下さい。
完全室内飼いのメリット
- 猫は留守番が得意猫は元来「待ち伏せ型」で狩猟を行います。何かをじっと待つことに対してそれほど苦痛は感じない動物です。
- 猫は孤独が苦痛ではない犬とは違い、猫には単独行動に対しても順応性があります。仲間がいないと寂しくて夜鳴きするということは基本的にありません。
- 猫は人間が帰宅する夕方以降に活発化する猫は夜行性(厳密に言えば薄明薄暮性)なので、太陽が沈んで薄暗くなってから本領発揮します。仕事から帰宅した飼い主と生活のリズムを合わせやすいことが多いです。
- 猫は泣き声が小さい猫は群れを成して鳴き声でコミュニケーションをはかる動物ではありません。繁殖期など特殊な時期を除いて、鳴き声が騒音となることはまれです。また、あらかじめ不妊手術を施せば、繁殖期における赤ん坊の泣き声のような騒音すらなくなります。
- 猫は狭い室内に順応してくれる猫は縄張り意識を持ちますが、たとえ支配しているテリトリーは狭くても、それ(つまり住んでいる家)が完全に守られおり、エサが充分に確保できていれば、苦痛に感じるどころか、逆に安心して暮らしていけます。
放し飼いのデメリット
室内飼いには多くのメリットがある一方で、放し飼いには逆に多々のデメリットがあります。以下で述べるように、交通量が多く、暮らしている猫の密度も濃い都会においては、猫を自由に外に出すことにはそれ相応のリスクが伴います。
↓NEXT:猫の散歩?
放し飼いのデメリット
- 交通事故に遭う危険性が高い猫は前進運動と比較して、「後ずさり」が苦手です。また、驚くと体が硬直して動かなくなる猫も多くいます。そういった理由で交通事故に遭い、命を落とす猫が後を絶ちません。
- エンジンルームに巻き込まれる猫は適度に温かくて暗いボンネットの中や車体の中(下からもぐりこむ)で居眠りすることがあります。猫がいることに気づかず自動車が発進して命を落とすというケースもあります。

- 迷子になることがある猫には基本的に帰巣本能(元いた場所に戻る能力)がありますが、100%の確率で家にたどり着けるわけではありません。保健所に連行されたり、心無い人に虐待されたりして命を落とすケースもあります。
- 他の猫とのけんか猫には自分の縄張り(テリトリー)があります。このテリトリーをめぐって他の猫と争いになり、大怪我を負うことも考えられます。
- 感染症の危険がある他の猫とのケンカしたときの傷口などから、他の猫の唾液が何らかのきっかけで体内に入ったり、交尾行動に伴う体液交換で感染症にかかるリスクが高まります。
- 無規律な繁殖をする不妊手術をしない状態で飼い猫を外に出してしまうと、無規律な繁殖から飼い主のいない子猫が増えてしまいます。オス猫の去勢手術をしないと、外でメス猫を妊娠させて野良猫の数が増えてしまいます。メス猫の避妊手術をしないと、外で妊娠して家で出産し、Twitterなどで「子猫生まれました!飼い主さん急募です!」となってしまいます。いずれにしても飼い主のいない可哀想な子猫の数が増えてしまいます。
- 猫捕りのターゲットになる世の中には「猫捕り」(猫狩り)と呼ばれる行為がしばしば見られます。1970年代までは、金銭目的での猫捕りが主流でしたが、近年は虐待目的での猫捕りが増えつつあるというのが現状です。2017年にも最低13頭の猫を対象とした陰惨な動物虐待事件が起こりました。金銭目的でも虐待目的でも猫にとって危険であることに変わりはありません。詳しくは猫さらいがいるをご参照ください。
負傷動物や路上死動物に関する詳細は放し飼いが招く猫の死をご参照ください。
猫を散歩させることの是非
「猫を放し飼いにすると危険・・だけどずっと家の中に閉じ込めておくのはかわいそう」、という考えから、猫を散歩させる人がたまにいます。この行為は猫や飼い主にとってどうなのでしょうか?結論から言うと、猫を散歩させることは望ましくない側面の方が多いでしょう。
猫を外に出してしまうと?
猫にハーネス(胴輪)などをつけて外の世界を散策させてしまうと、「外は安全な世界だ」と認識してしまう可能性があります。その結果、自分の縄張りが広がったように勘違いし、時を選ばずに外に出たがるようになるかもしれません。例えば夜中になって「ドア開けてよ!」とばかりにニャーニャー大声で鳴くなどです。
こうした状況は、外に出たくても出られない猫にとってもストレスですし、安眠を妨害される飼い主にとっても悩みの種になります。ですから安易に猫を外に連れ出すことは控えたほうがよいでしょう。 近年はソーシャルメディアサービス(SNS)が発達したことにより、誰でも気軽に画像や動画といった情報を発信することができるようになりました。しかしその反動として、猫の福祉を損なってまで話題作りに走ろうとする人が増えているのが現状です。例えば猫にサルの着ぐるみを着せるとか、海を泳がせるとか、キュウリを見せて驚かせると言ったものがその最たる例でしょう。「猫にハーネスを付けて散歩させる」という行為もその1つとしてカウントされることがあります。2017年には、イギリスの動物虐待防止協会(RSPCA)が猫をリードで散歩させるトレンドに警鐘を鳴らしました。要点は「猫は小さな犬ではないので、散策を楽しんでいると早合点しないで」というものです。
'Cat on lead' trend is causing pets distress, RSPCA warns
「インスタ映え」のために猫に外出を無理強いしている場合、映えるどころか炎上してしまう危険性すらあります。飼い主の側にそうした動機があるのなら、猫にとっても人にとってもいいことはありませんので、控えたほうがよいでしょう。なお近年は猫を散歩させる代わりに、家の敷地内に安全ゾーンを設けて散策させる「キャティオ」(Catio)というものが普及しつつあります。法律などとの兼ね合いからすべての人に可能なわけではありませんが、以下のページを参照しつつ、自宅に導入できるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
近年はソーシャルメディアサービス(SNS)が発達したことにより、誰でも気軽に画像や動画といった情報を発信することができるようになりました。しかしその反動として、猫の福祉を損なってまで話題作りに走ろうとする人が増えているのが現状です。例えば猫にサルの着ぐるみを着せるとか、海を泳がせるとか、キュウリを見せて驚かせると言ったものがその最たる例でしょう。「猫にハーネスを付けて散歩させる」という行為もその1つとしてカウントされることがあります。2017年には、イギリスの動物虐待防止協会(RSPCA)が猫をリードで散歩させるトレンドに警鐘を鳴らしました。要点は「猫は小さな犬ではないので、散策を楽しんでいると早合点しないで」というものです。
'Cat on lead' trend is causing pets distress, RSPCA warns
「インスタ映え」のために猫に外出を無理強いしている場合、映えるどころか炎上してしまう危険性すらあります。飼い主の側にそうした動機があるのなら、猫にとっても人にとってもいいことはありませんので、控えたほうがよいでしょう。なお近年は猫を散歩させる代わりに、家の敷地内に安全ゾーンを設けて散策させる「キャティオ」(Catio)というものが普及しつつあります。法律などとの兼ね合いからすべての人に可能なわけではありませんが、以下のページを参照しつつ、自宅に導入できるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
こうした状況は、外に出たくても出られない猫にとってもストレスですし、安眠を妨害される飼い主にとっても悩みの種になります。ですから安易に猫を外に連れ出すことは控えたほうがよいでしょう。
 近年はソーシャルメディアサービス(SNS)が発達したことにより、誰でも気軽に画像や動画といった情報を発信することができるようになりました。しかしその反動として、猫の福祉を損なってまで話題作りに走ろうとする人が増えているのが現状です。例えば猫にサルの着ぐるみを着せるとか、海を泳がせるとか、キュウリを見せて驚かせると言ったものがその最たる例でしょう。「猫にハーネスを付けて散歩させる」という行為もその1つとしてカウントされることがあります。2017年には、イギリスの動物虐待防止協会(RSPCA)が猫をリードで散歩させるトレンドに警鐘を鳴らしました。要点は「猫は小さな犬ではないので、散策を楽しんでいると早合点しないで」というものです。
'Cat on lead' trend is causing pets distress, RSPCA warns
「インスタ映え」のために猫に外出を無理強いしている場合、映えるどころか炎上してしまう危険性すらあります。飼い主の側にそうした動機があるのなら、猫にとっても人にとってもいいことはありませんので、控えたほうがよいでしょう。なお近年は猫を散歩させる代わりに、家の敷地内に安全ゾーンを設けて散策させる「キャティオ」(Catio)というものが普及しつつあります。法律などとの兼ね合いからすべての人に可能なわけではありませんが、以下のページを参照しつつ、自宅に導入できるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
近年はソーシャルメディアサービス(SNS)が発達したことにより、誰でも気軽に画像や動画といった情報を発信することができるようになりました。しかしその反動として、猫の福祉を損なってまで話題作りに走ろうとする人が増えているのが現状です。例えば猫にサルの着ぐるみを着せるとか、海を泳がせるとか、キュウリを見せて驚かせると言ったものがその最たる例でしょう。「猫にハーネスを付けて散歩させる」という行為もその1つとしてカウントされることがあります。2017年には、イギリスの動物虐待防止協会(RSPCA)が猫をリードで散歩させるトレンドに警鐘を鳴らしました。要点は「猫は小さな犬ではないので、散策を楽しんでいると早合点しないで」というものです。
'Cat on lead' trend is causing pets distress, RSPCA warns
「インスタ映え」のために猫に外出を無理強いしている場合、映えるどころか炎上してしまう危険性すらあります。飼い主の側にそうした動機があるのなら、猫にとっても人にとってもいいことはありませんので、控えたほうがよいでしょう。なお近年は猫を散歩させる代わりに、家の敷地内に安全ゾーンを設けて散策させる「キャティオ」(Catio)というものが普及しつつあります。法律などとの兼ね合いからすべての人に可能なわけではありませんが、以下のページを参照しつつ、自宅に導入できるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
- First Caturday
- 「First Caturday」とは、猫に外の世界を満喫してもらうため、毎月第一土曜日に場所を決めて飼い主が集うというというイベント。2015年ころカリフォルニアで始まり、その後クチコミでアメリカ国内やカナダにも広まっていきました。飼い主たちの頭の中には「猫が外の世界を楽しんでいる」という前提があるようですが、猫の本心はわかりません…。
First Caturday/Facebook

ぼんやり外を眺めているのは?
 ぼんやりと外を眺めている猫を観察していると「退屈そうだなぁ・・やっぱり外に行きたいんじゃないのかなぁ?」と飼い主は心配になるでしょう。しかし猫が外を眺めているのは、外に行きたいからではなく、自分の縄張りの番をしているという意味合いの方が大きいのです。
ぼんやりと外を眺めている猫を観察していると「退屈そうだなぁ・・やっぱり外に行きたいんじゃないのかなぁ?」と飼い主は心配になるでしょう。しかし猫が外を眺めているのは、外に行きたいからではなく、自分の縄張りの番をしているという意味合いの方が大きいのです。猫の縄張りは、食料の豊富さによって大きくなったり小さくなったりします。例えば、あまりエサがない場所における猫の生活圏が、時に1,000エーカーにまで達するのに対し、エサが十分にある環境では、0.2エーカー(100メートル×80メートル程度)にまで縮小することが確認されています。 このように猫の縄張りは食料の豊富度によって変わる流動的なものですので、常に家の中でだけエサを食べていれば、猫にとっての縄張りは家の中だけになります。猫を完全室内飼いにし、いつも家の中でおいしいエサを与えていれば、猫はそこそこ満足してくれるという訳です。
単調な生活に刺激を与えたい場合は、外に連れ出すのではなく、おもちゃなどを用いて狩猟欲求を満たしてあげた方が、はるかに効果的でしょう。具体的には以下のページをご参照ください。 ↓NEXT:首輪っているの?
猫の室内飼いと首輪
近年、猫の飼育スタイルは一昔前の「放し飼い」から「完全室内飼い」へと急速に変わりつつあります。ペットフード協会の統計データによると、2018年度において78.3%もの家庭が、猫を完全室内飼いにしているそうです。こうした飼育環境の変化に伴い、猫に首輪を装着することの意味が徐々になくなってきました。


猫の首輪の役割
これまで首輪が持っていた役割や目的を並べると、以下のようになります。「完全室内飼い」に移りつつある近年のペットライフにおいて、猫に首輪をすることの意味はかなり薄くなってきているようです。
従来の首輪の役割・目的
- 迷子札
 迷子になった時、首輪に付けられた迷子札をたどって元の飼い主が判明することがあります。しかし近年は、従来の迷子札に代わって、皮下に埋め込むマイクロチップが広く用いられるようになってきました。外れる心配がないマイクロチップの方が、より確実に飼い主を発見できるというわけです。
迷子になった時、首輪に付けられた迷子札をたどって元の飼い主が判明することがあります。しかし近年は、従来の迷子札に代わって、皮下に埋め込むマイクロチップが広く用いられるようになってきました。外れる心配がないマイクロチップの方が、より確実に飼い主を発見できるというわけです。 - 飼い猫であることを示す外を歩いている猫が、単なる野良猫ではなく、飼い猫であることを示すために首輪が取り付けられることがあります。しかし放し飼いではなく完全室内飼いをしている家庭において、この目的で首輪をつける意味はないでしょう。
- 防虫効果ダニやノミを寄せ付けない防虫効果を持った首輪があります。しかしこうした特殊な首輪は、口に入れてしまうと毒性を発揮する危険性があり、また首輪に含まれている成分にアレルギー反応を示して皮膚炎が生じてしまう可能性もあります。近年は、スポット式の防虫薬が普及しているため、防虫カラーの役割は徐々に少なくなりつつあります。
- フラップセンサー首輪の中には、「キャットフラップ」と呼ばれる猫専用の外出扉へのセンサーになっているものがあります。しかし放し飼いではなく完全室内飼いをしている家庭において、この目的で首輪をつける意味はないでしょう。
- 鈴をつけるため
 猫に鈴を装着したいがために首輪を取り付ける人がいます。そもそも鈴をつける目的は、室内における猫の居場所がすぐわかるようにすることや、屋外における鳥や野生動物の捕食を妨げることです。しかし放し飼いではなく完全室内飼いをしている家庭において、この目的で首輪をつける意味はないでしょう。また室内においても、音響ストレスという観点から、ただ単に居場所を見つけやすくするためだけに猫に鈴をつけることはお勧めできません。
猫に鈴を装着したいがために首輪を取り付ける人がいます。そもそも鈴をつける目的は、室内における猫の居場所がすぐわかるようにすることや、屋外における鳥や野生動物の捕食を妨げることです。しかし放し飼いではなく完全室内飼いをしている家庭において、この目的で首輪をつける意味はないでしょう。また室内においても、音響ストレスという観点から、ただ単に居場所を見つけやすくするためだけに猫に鈴をつけることはお勧めできません。
猫の首輪の注意点
猫の首輪に何か意味があるとすれば、「万が一迷子になった時の備え」や「ファッション」といった意味になるでしょう。もし何らかの理由により猫に首輪をつける必要が生じた場合は、以下のような注意点を念頭に置くようにします。
首輪装着の注意点
- 伸縮性のあるものは避ける伸縮性のある首輪の場合、何かの拍子に首輪が伸び、まるで拘束具のように腋の下などに挟まることがあります。
- クイックリリースを用いるクイックリリースとは、一定の力が加わると、自然に留め具が外れる仕組みのことです。何かに引っかかって猫が首吊り状態にならないよう、留め具はクイックリリースタイプにした方がよいでしょう。例えば以下はイギリス・ヨークシャー州の路上で保護された迷子猫「ナゲット」の画像です。何らかのアクシデントで首輪がたすきがけになったまま6週間過ごした結果、皮膚が圧迫を受けて壊疽を起こしてしまいました。安全首輪で外れていたらここまで悪化はしなかったでしょう。

- 首輪のゆるみは指2本首輪が緩すぎるとすぐに外れ、逆にきつすぎると首が締まってしまいます。首輪のゆるみは指2本くらいが目安です。
- 子猫の成長をよく見る子猫に首輪を装着する際は、成長の度合いをよく観察しながら選ぶようにします。猫は最初の1年間で、わずか100グラムから3~5キロにまで急成長しますので、サイズのミスマッチは首絞めの原因になります。例えば以下はアメリカ・マサチューセッツ州ボストンの路上で保護された子猫「ニッキー」の画像です。小さい首輪を装着したまま体が成長したため、首元に食い込んで皮膚が壊疽を起こしてしまいました。

- 音の出るものは避ける人間の耳と比較し、猫の耳は非常に敏感にできています。その敏感な耳のそばで、四六時中チリンチリンと音が鳴っている状態は、猫にとって多大なるストレスだと考えられます。鈴やシンバルなど、首輪に音のなるものを装着することは避けた方がよいでしょう。
- 皮膚炎に気を付ける首輪の素材に対してアレルギー反応を示したり、単に首輪が擦れることで、皮膚に炎症が生じてしまうことがあります。猫の首元は定期的にチェックするようにしましょう。
「嫌がる猫に首輪は必要か?」というページで首輪をつけるかどうかを判断する際のヒントを過去の調査データとともに紹介しています。また猫にとってストレスの少ない室内環境の設定については「猫が喜ぶ部屋の作り方」で詳しく解説してありますので参考にしてください。