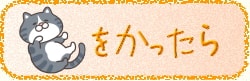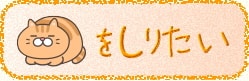フィラリア症の原因
フィラリア症とはディロフィラリアに属する線虫の一種によって引き起こされる寄生虫症のことです。ディロフィラリア属には27種ほどが確認されており、ほとんどは無害ですが、中には病原性を持ち「フィラリア症」を引き起こすものがあります。
ライフサイクル
犬と猫において問題となるのは、肺の中の細い動脈というとてもデリケートな場所に寄生する「Dirofilaria immitis」(ディロフィラリア・イミティス)と呼ばれる種です。一般的には「犬糸状虫」(犬糸状虫, heartworm)と訳されますが、実は犬だけでなく猫や人間にも感染します。ライフサイクルは以下です。
ミクロフィラリア
ミクロフィラリアとは、肺動脈付近に生息しているフィラリア成虫が生み出した子供のことです。メス成虫の体内から放出された後、宿主の血液に乗って体中を循環します。
 体内でミクロフィラリアが検出されるのは犬、オオカミ、コヨーテといったイヌ科動物がほとんどで、猫の体内で見つかるケースは20%程度です。大きさは295~325μmですので、定規に刻まれている1mm目盛りの3分の1くらいということになります。
体内でミクロフィラリアが検出されるのは犬、オオカミ、コヨーテといったイヌ科動物がほとんどで、猫の体内で見つかるケースは20%程度です。大きさは295~325μmですので、定規に刻まれている1mm目盛りの3分の1くらいということになります。
 体内でミクロフィラリアが検出されるのは犬、オオカミ、コヨーテといったイヌ科動物がほとんどで、猫の体内で見つかるケースは20%程度です。大きさは295~325μmですので、定規に刻まれている1mm目盛りの3分の1くらいということになります。
体内でミクロフィラリアが検出されるのは犬、オオカミ、コヨーテといったイヌ科動物がほとんどで、猫の体内で見つかるケースは20%程度です。大きさは295~325μmですので、定規に刻まれている1mm目盛りの3分の1くらいということになります。
L1~L3
蚊が犬の体を刺して血をチューチュー吸い取ると、血液中に含まれていたミクロフィラリアも同時に取り込むことになります。蚊の体内に移動したミクロフィラリアは、中腸で24時間ほど過ごした後でマルピーギ管に移動し、そこで脱皮を繰り返して幼虫(Larvae=L)になります。
 生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。このときの大きさは体長1.1~1.3mm程度です。
生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。このときの大きさは体長1.1~1.3mm程度です。
 生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。このときの大きさは体長1.1~1.3mm程度です。
生育の速さは温度によって変わり、必要となる最低温度は1ヶ月間平均で17.8℃以上、逆に温度が14℃以下になると生育が止まります。温度27℃湿度80%という環境では10~14日で感染能を持つ第三期子虫(L3)にまで脱皮を繰り返します。このときの大きさは体長1.1~1.3mm程度です。
L4~L5
L3は蚊の口先(口器)に移動し、蚊が犬や猫の皮膚に針を差し込むと同時に分泌される血リンパ液に乗って犬や猫の体内に侵入します。
猫の体内に侵入した体長1mmほどの第三期子虫(L3)は皮膚の下、筋膜の下、筋肉の内部、脂肪の内部、漿膜の下などを移動しながら早ければ3日くらい、おそくとも12日くらいで脱皮を始め第四期子虫(L4)になります。L4から最終ステージの幼体(L5)に進化するまでにはやや時間がかかり、猫の体内に入ってから50~70日後です。 画像元→Heartworm Disease in Dogs 十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは体内侵入から90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。
十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは体内侵入から90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。
猫の体内に侵入した体長1mmほどの第三期子虫(L3)は皮膚の下、筋膜の下、筋肉の内部、脂肪の内部、漿膜の下などを移動しながら早ければ3日くらい、おそくとも12日くらいで脱皮を始め第四期子虫(L4)になります。L4から最終ステージの幼体(L5)に進化するまでにはやや時間がかかり、猫の体内に入ってから50~70日後です。 画像元→Heartworm Disease in Dogs
 十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは体内侵入から90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。
十分な大きさと力を身につけた幼体(L5)は、ずうずうしくも血管壁を破って血流に乗り、心臓や肺後葉の末梢肺動脈に向けて移動を開始します。この移動が完了するのは体内侵入から90~120日後です。心臓や肺に到着した時点での大きさは、まだ小指の先くらいの2.5~3.8cmに過ぎません。
成虫
肺に到達した幼体は血流によって肺動脈にまで押し出され、早ければ感染から7~8ヶ月目には生殖能力を備えた成虫になります。成虫の寿命はときとして2~4年に及びます。体の大きさはメス成虫で20cm、オス成虫で10cm前後です。


犬と猫の違い
犬と猫の体内におけるフィラリアの振る舞い方は大きく異なります。この知識は治療や予防計画を立てていく上でとても重要です。
幼虫の生存率
フィラリアの幼虫は猫の体内ではなかなかうまく成長できません。体内にL3を100匹保有した犬が100頭いた場合、ほぼ全頭において60匹(60%)が成虫にまで成長します。それに対しL3を100匹保有した猫が100頭いた場合、25頭の体内では幼虫がそのまま死滅してしまいます。残った75頭の体内ではかろうじて幼虫が生き残りますが、成虫にまで成長できる幸運なものはわずか3~10匹(3~10%)しかいません。つまり全く同じ状況下に犬と猫が100頭ずついた場合、犬の成虫の保有数は6,000匹、猫のそれは225~750匹という8~27倍の格差が生まれるのです。
 猫の体内では、フィラリアの幼虫や成虫が保有する「ボルバキア」と呼ばれる共生細菌に対する抗体(排除しようとする力)が感染から1~2ヶ月後に高まるといいます(Morcho, 2004)。犬と猫で見られるフィラリア幼虫の死滅率の違いは、免疫反応の違いを反映しているのかもしれません。
猫の体内では、フィラリアの幼虫や成虫が保有する「ボルバキア」と呼ばれる共生細菌に対する抗体(排除しようとする力)が感染から1~2ヶ月後に高まるといいます(Morcho, 2004)。犬と猫で見られるフィラリア幼虫の死滅率の違いは、免疫反応の違いを反映しているのかもしれません。
 猫の体内では、フィラリアの幼虫や成虫が保有する「ボルバキア」と呼ばれる共生細菌に対する抗体(排除しようとする力)が感染から1~2ヶ月後に高まるといいます(Morcho, 2004)。犬と猫で見られるフィラリア幼虫の死滅率の違いは、免疫反応の違いを反映しているのかもしれません。
猫の体内では、フィラリアの幼虫や成虫が保有する「ボルバキア」と呼ばれる共生細菌に対する抗体(排除しようとする力)が感染から1~2ヶ月後に高まるといいます(Morcho, 2004)。犬と猫で見られるフィラリア幼虫の死滅率の違いは、免疫反応の違いを反映しているのかもしれません。
成虫の数
肺にまで到達する成虫の数は犬では1~250匹です。それに対し猫では多くとも6匹未満で、たいていは1~2匹しかいません。
成虫の性別
猫の体内における成虫の3分の1は単性寄生、すなわちオスだけかメスだけしかいないという状態です。猫の体内でミクロフィラリアがほとんど検出されない理由は、単性寄生であるためそもそも生殖行動を行えないからです。またネコ科動物に属するオセロット、ピューマ、ウンピョウ、ユキヒョウ、ベンガルトラ、ライオンでもフィラリアの感染が確認されていますが、猫(イエネコ)と同じようにミクロフィラリアを体内に保有する病原巣(reservoir)にはなりえないと考えられています。
成虫の寿命
犬の体内における成虫の寿命は5~7年ですが、猫の体内においては2~4年と短くなります。
成虫の大きさ
犬の体内における成虫の大きさはメス成虫で長さ25~31cm(直径1.0~1.3mm)、オス成虫で12~20cm(直径0.7~0.9mm)程度です。しかし猫やフェレットに感染した成虫はこれよりも小さいとの報告があります。宿主の体の大きさに合わせた結果なのでしょうか。
フィラリア感染率
2000年から2008年にかけてアメリカ国内で行われた抗体検査では、4.2%~15.9%の猫が幼虫に感染したことがあると報告されています。また最も高いところとしてはカリフォルニア州オーバーン(33%)やフロリダ州マイアミ(21%)が確認されたとも。
一方、直近の2017年における報告では、アメリカとカナダにある1,353の動物病院から集められた合計26,707の血液サンプル、および125の動物保護施設から集められた合計8,268の血液サンプルのうち、アメリカの35州における血清陽性率が0.4%だったのに対し、カナダでは0%だったと言います では日本における陽性率はどの程度なのでしょうか?断片的な資料しかありませんが、以下のような数値が参考になるでしょう。
一方、直近の2017年における報告では、アメリカとカナダにある1,353の動物病院から集められた合計26,707の血液サンプル、および125の動物保護施設から集められた合計8,268の血液サンプルのうち、アメリカの35州における血清陽性率が0.4%だったのに対し、カナダでは0%だったと言います では日本における陽性率はどの程度なのでしょうか?断片的な資料しかありませんが、以下のような数値が参考になるでしょう。
日本猫のフィラリア陽性率
先述した北米とカナダの調査では「外に出る機会がある猫は出る機会がない猫のおよそ3倍の陽性率」と報告されています。屋外において蚊と接する機会が増えると、それだけフィラリアの幼虫をもらってしまうリスクも高まってしまうということです。
フィラリア症の症状
フィラリアに感染した猫における症状は3つに区分されます。1つは感染してすぐの頃に引き起こされる急性症状、1つは肺や心臓に到達した成虫の死骸によって引き起こされる症状、そしてもう1つは成虫の寄生が長引いて組織や器官に永続的な病変が生じた慢性症状です。
感染初期の急性症状
フィラリアの幼虫が体内に侵入してから3~6ヶ月後、肺動脈に到達したタイミングで喘息やアレルギー性気管気管支炎に似た症状を示すことがあります。大きな特徴は、フィラリアが幼虫の段階でも症状を引き起こしうるという点です。「フィラリア幼虫性肺症」とか「犬糸状虫随伴性呼吸器疾患」(HARD)と呼ばれる猫特有の症状は以下です。
これらの急性症状は成虫が大きくなるにつれて自然と緩和していきます。おそらく、成虫から放出される何らかの物質によって免疫反応が抑えられるからなのでしょう。
HARDの症状
- 喘息に似た咳
- 吐く・嘔吐
- 食欲不振
- 疲労困憊
これらの急性症状は成虫が大きくなるにつれて自然と緩和していきます。おそらく、成虫から放出される何らかの物質によって免疫反応が抑えられるからなのでしょう。
成虫が死んだ時の症状
猫の体内における成虫の寿命は2~4年です。寿命が来て成虫が肺動脈から離れると、血流に押されて血管の奥の方に流れ込み、肺梗塞(部分的な細胞死)を引き起こすことがあります。また成虫の死骸を異物とみなした体が、免疫反応を引き起こしたり血栓を形成したりして血管の目詰まりにつながってしまうことがあります。成虫が死んだときに見られる主な症状は以下です。
成虫の死骸による症状
- 呼吸が荒い
- ショック症状
- 呼吸困難
- 喀血・血が混じった咳
- 吐く・嘔吐
- 下痢
- 失神
- 痴呆症状
- 運動失調
- ぐるぐる回る
- 頭が傾く
- 視覚障害
- 発作
- 突然死
感染後期の慢性症状
猫の体内における成虫の寿命は、犬の5~7年に比べると短く2~4年程度です。また虫の数も6匹を超えることはほとんどありません。結果として、長期的な寄生に伴う肺高血圧症、右心の肥大、うっ血性心不全といった肺や心臓の変性はあまり見られないという特徴があります。とはいえ可能性はゼロではなく、肺動脈の中にフィラリア成虫がずっととどまったままだと、以下に述べるような慢性症状につながることがあります。
長期感染による症状
- 呼吸が荒い
- 断続的な咳
- 努力性呼吸・息苦しそう
- 食欲不振
- 体重減少
- 食事とは無関係な嘔吐
- 腹水
- 胸水
- 乳び胸
- 膿胸
- 運動失調
- 発作
- 失神
- 突然死
成虫の迷入
迷入とは、フィラリアの幼虫や成虫が本来の生息場所である肺動脈とは違う場所にたどり着いてしまった状態のことです。猫においては脳、硬膜上腔、体腔、前眼房、硝子体、皮下組織、腸骨動脈、大腿動脈などの症例が報告されています。
例えば以下はカリフォルニア州ロサンゼルスに暮らしている猫の「ストーミー」(シャム | 4歳 | メス)の症例です。 突如として右後足に力が入らないという症状を示した後、「大腿動脈へのフィラリア成虫の迷入」と診断されました。虫を除去してからは血流が元に戻ったものの、依然として予断を許さない状況で、神経や筋肉が正常に回復しない場合は、下肢切断という可能性を考慮する必要があるとのこと。
突如として右後足に力が入らないという症状を示した後、「大腿動脈へのフィラリア成虫の迷入」と診断されました。虫を除去してからは血流が元に戻ったものの、依然として予断を許さない状況で、神経や筋肉が正常に回復しない場合は、下肢切断という可能性を考慮する必要があるとのこと。
体が小さい猫においては、こうした迷入もまた心配しなければならない厄介事の一つです。重要な臓器につながる動脈の中で目詰まりを起こしてしまうと、ある日突然死んでしまうこともありえます。
例えば以下はカリフォルニア州ロサンゼルスに暮らしている猫の「ストーミー」(シャム | 4歳 | メス)の症例です。
 突如として右後足に力が入らないという症状を示した後、「大腿動脈へのフィラリア成虫の迷入」と診断されました。虫を除去してからは血流が元に戻ったものの、依然として予断を許さない状況で、神経や筋肉が正常に回復しない場合は、下肢切断という可能性を考慮する必要があるとのこと。
突如として右後足に力が入らないという症状を示した後、「大腿動脈へのフィラリア成虫の迷入」と診断されました。虫を除去してからは血流が元に戻ったものの、依然として予断を許さない状況で、神経や筋肉が正常に回復しない場合は、下肢切断という可能性を考慮する必要があるとのこと。体が小さい猫においては、こうした迷入もまた心配しなければならない厄介事の一つです。重要な臓器につながる動脈の中で目詰まりを起こしてしまうと、ある日突然死んでしまうこともありえます。
人間のフィラリア症
フィラリア(犬糸状虫)は犬だけでなく猫や人間にも感染します。人間に感染した場合、皮膚の下に潜り込んで結節を形成したり、少数の成虫が肺動脈の中に潜んで部分的な機能不全を招くというパターンが大半です。
「おできが割れて中から虫が出てきた!」とか「目の中で虫がウヨウヨしている!」といった場合を除き、症状は軽微ですので多くの人は感染していることにすら気づきません。幸い猫のように突然死を引き起こすということはありませんが、エックス線やCTスキャン検査を行った際、肺の中に「コイン様病変」(銭形陰影)と呼ばれる所見が見られた場合は厄介です。この病変部が腫瘍なのかフィラリアによる梗塞なのかを確かめるため、経皮的な生検や高額な検査を行う必要性が生じてしまうのです。
家の中でも外でも蚊に刺されないように気をつけることは、犬や猫だけでなく人間のフィラリア症を予防する上でもとても重要です。
「おできが割れて中から虫が出てきた!」とか「目の中で虫がウヨウヨしている!」といった場合を除き、症状は軽微ですので多くの人は感染していることにすら気づきません。幸い猫のように突然死を引き起こすということはありませんが、エックス線やCTスキャン検査を行った際、肺の中に「コイン様病変」(銭形陰影)と呼ばれる所見が見られた場合は厄介です。この病変部が腫瘍なのかフィラリアによる梗塞なのかを確かめるため、経皮的な生検や高額な検査を行う必要性が生じてしまうのです。
家の中でも外でも蚊に刺されないように気をつけることは、犬や猫だけでなく人間のフィラリア症を予防する上でもとても重要です。
フィラリア症の検査
猫のフィラリアを検査する方法は大きく分けて3つあります。1つはミクロフィラリアを検出するための「ミクロフィラリア検査」、1つは幼虫(L1~L5)を検出するための「抗体検査」、そして1つは成虫を検出するための「抗原検査」です。残念ながら今のところ、どの検査を行ったとしても高い精度で感染の有無を確認することはできません。推奨されているのは「抗体検査」と「抗原検査」を合わせて行うというものです。
ミクロフィラリア検査
ミクロフィラリア検査とは、血液中にフィラリアの子供である「ミクロフィラリア」が存在しているかどうかを確認するための検査です。採取した血液をスライドグラスの上に薄く伸ばして観察する「直接塗抹観察法」や、遠心分離機にかけて一箇所に集めた上で観察する集虫法(ヘマトクリット法やアセトン集虫法)などがあります。
画像元→BloodSmear

 しかしどのような観察法を用いたとしても、猫の体内でミクロフィラリアの存在を確認することは困難です。なぜなら、そもそも血中にミクロフィラリアを保有してる猫の割合はおよそ20%しかないからです。さらに血中にミクロフィラリアが現れる場合、早くとも感染から195日目以降で、228日目を過ぎる頃にはもうどこかに消えてしまいます。つまり猫の体の中では、およそ1ヶ月という極めて限定的な期間しかミクロフィラリアは生きていられないのです。
しかしどのような観察法を用いたとしても、猫の体内でミクロフィラリアの存在を確認することは困難です。なぜなら、そもそも血中にミクロフィラリアを保有してる猫の割合はおよそ20%しかないからです。さらに血中にミクロフィラリアが現れる場合、早くとも感染から195日目以降で、228日目を過ぎる頃にはもうどこかに消えてしまいます。つまり猫の体の中では、およそ1ヶ月という極めて限定的な期間しかミクロフィラリアは生きていられないのです。
犬の体内でミクロフィラリアはおよそ2年間生存することが可能です。また猫の体から成虫を取り出して犬の体内に移動させると、それまで放出していなかったミクロフィラリアを突然放出し始めるといいます。こうした事実から考え、猫の体内には成虫がミクロフィラリアを放出できなくするような何らかの免疫メカニズムがあるものと推測されます。

 しかしどのような観察法を用いたとしても、猫の体内でミクロフィラリアの存在を確認することは困難です。なぜなら、そもそも血中にミクロフィラリアを保有してる猫の割合はおよそ20%しかないからです。さらに血中にミクロフィラリアが現れる場合、早くとも感染から195日目以降で、228日目を過ぎる頃にはもうどこかに消えてしまいます。つまり猫の体の中では、およそ1ヶ月という極めて限定的な期間しかミクロフィラリアは生きていられないのです。
しかしどのような観察法を用いたとしても、猫の体内でミクロフィラリアの存在を確認することは困難です。なぜなら、そもそも血中にミクロフィラリアを保有してる猫の割合はおよそ20%しかないからです。さらに血中にミクロフィラリアが現れる場合、早くとも感染から195日目以降で、228日目を過ぎる頃にはもうどこかに消えてしまいます。つまり猫の体の中では、およそ1ヶ月という極めて限定的な期間しかミクロフィラリアは生きていられないのです。犬の体内でミクロフィラリアはおよそ2年間生存することが可能です。また猫の体から成虫を取り出して犬の体内に移動させると、それまで放出していなかったミクロフィラリアを突然放出し始めるといいます。こうした事実から考え、猫の体内には成虫がミクロフィラリアを放出できなくするような何らかの免疫メカニズムがあるものと推測されます。
フィラリア抗原検査
抗原検査とはフィラリアの成虫がいるかどうかを確認するための検査です。メスの成虫だけが放出する特殊な分子(抗原=こうげん)を検知することで虫の有無を判断します。感染して7~8ヶ月が経過し、成虫になって生殖能力を獲得したメスが、最低3匹寄生していると高い感度で陽性反応が得られます。海外で報告されているデータとしては、陽性を正しく陽性と判定する感度が68~86%、陰性を正しく陰性と判定する特異度が78~99%といったものがありますので参考になるでしょう。なお抗原抗体複合体による偽陰性を避けるため104℃で10分間加熱するという裏技が報告されていますが、犬においても猫においても推奨されていません。
画像元→How to Perform a 4DX SNAP test
 犬においては抗原検査がフィラリア検査のゴールドスタンダードとされており、病院内で簡単に使用できる検査キットもたくさん販売されています(上の写真参照)。しかし猫においてはそれほど信頼のおける検査法とは言えないこと、および採算が取れないことなどから猫専用の検査キットは流通しておらず、ラボに外注しなければなりません。「信頼のおける検査法とは言えない」主な理由は以下。
犬においては抗原検査がフィラリア検査のゴールドスタンダードとされており、病院内で簡単に使用できる検査キットもたくさん販売されています(上の写真参照)。しかし猫においてはそれほど信頼のおける検査法とは言えないこと、および採算が取れないことなどから猫専用の検査キットは流通しておらず、ラボに外注しなければなりません。「信頼のおける検査法とは言えない」主な理由は以下。
 犬においては抗原検査がフィラリア検査のゴールドスタンダードとされており、病院内で簡単に使用できる検査キットもたくさん販売されています(上の写真参照)。しかし猫においてはそれほど信頼のおける検査法とは言えないこと、および採算が取れないことなどから猫専用の検査キットは流通しておらず、ラボに外注しなければなりません。「信頼のおける検査法とは言えない」主な理由は以下。
犬においては抗原検査がフィラリア検査のゴールドスタンダードとされており、病院内で簡単に使用できる検査キットもたくさん販売されています(上の写真参照)。しかし猫においてはそれほど信頼のおける検査法とは言えないこと、および採算が取れないことなどから猫専用の検査キットは流通しておらず、ラボに外注しなければなりません。「信頼のおける検査法とは言えない」主な理由は以下。
猫における抗原検査の難しさ
- 単性寄生猫の場合およそ3分の1では単性寄生、すなわちメスだけかオスだけしか寄生していません。抗原はメスだけが放出する分子ですので、もし体内にオスしかいなかった場合、いくら抗原検査をしても「いませんよ」という誤った判定(偽陰性)しか出ないことになります。
- 少数寄生猫の体内に寄生している成虫の数は多くの場合1~2匹です。抗原検査はメスが3匹以上寄生しているときに精度が高まりますので、少数寄生の猫においては、仮に体内にいたとしても十分な量の抗原を検知できず「いませんよ」という誤った判定(偽陰性)が出てしまうかもしれません。
フィラリア抗体検査
抗体検査とは、フィラリアの幼虫や成虫を排除しようと体内で生成された抗体の有無を確認するための検査です。感染から少なくとも2ヶ月が経過し、体内に十分な量の抗体が形成されてから検出が可能となります。抗原検査と同様、動物病院内で簡単にできる検査キットがありませんので、ラボなどに外注する必要があります。
感染している個体を「感染している」と正しく判定できる感度に関し、実験感染例では98%、自然感染例では32~89%と報告されています。しかしどのステージにおける抗体を検出するかによって成績は変動するようです。例えばフィラリア陽性猫31頭を対象とし、6種類の異なる抗体を検出するテストを行ったところ、21頭(68%)では少なくとも1つの抗体が陰性と判定されたといいます。
また幼虫に感染した後、いったいどのくらいの期間、体内に抗体がとどまるのかがよくわかっていないというのも問題です。例えば抗体検査で陽性判定を受けたとしましょう。しかし検出された抗体が、現在体内にいる幼虫を排除するために生成されたばかりものなのか、それとも3年前にいた幼虫を排除するために生成された残りなのかがわかりません。結果として、「感染したことがある」ことは確実にわかりますが、「現在体内に幼虫や成虫がいる」という重要な項目がはっきりわからないままになってしまいます。
感染している個体を「感染している」と正しく判定できる感度に関し、実験感染例では98%、自然感染例では32~89%と報告されています。しかしどのステージにおける抗体を検出するかによって成績は変動するようです。例えばフィラリア陽性猫31頭を対象とし、6種類の異なる抗体を検出するテストを行ったところ、21頭(68%)では少なくとも1つの抗体が陰性と判定されたといいます。
また幼虫に感染した後、いったいどのくらいの期間、体内に抗体がとどまるのかがよくわかっていないというのも問題です。例えば抗体検査で陽性判定を受けたとしましょう。しかし検出された抗体が、現在体内にいる幼虫を排除するために生成されたばかりものなのか、それとも3年前にいた幼虫を排除するために生成された残りなのかがわかりません。結果として、「感染したことがある」ことは確実にわかりますが、「現在体内に幼虫や成虫がいる」という重要な項目がはっきりわからないままになってしまいます。
その他の補助検査
フィラリアの感染しているかどうかは、抗体検査や抗原検査の結果に、以下に述べるような様々な補助的な検査結果を加味して判断されます。
エックス線検査
心エコー検査
心臓に超音波を当てて中の様子を探る「心エコー検査」は、猫においては最も信頼度の高い検査法と考えられています。しかし主肺動脈やその枝、右心室、房室ジャンクションなど、比較的わかりやすい場所に成虫がいてくれないとなかなか視認できません。肺動脈や右心室に成虫がいる場合、この検査でおよそ3/4が発見されます。成虫がいるときの目印は、0.5~1cmくらいの短い平行な2本線(イコールマーク)です。


血液検査・生化学検査
フィラリア症にだけ特異的に見られる血液検査項目はありません。寄生から4~7ヶ月後、末梢血液中の好酸球増加を示すのは1/3~2/3程度です。1/3では再生不良性貧血が見られることもあります。また肺動脈疾患や血栓塞栓症を患っている場合、好中球増加症、単球増加症、血小板減少症、DIC(播種性血管内凝固症候群)などが確認されることもあります。
死後解剖
猫のフィラリア症における大きな特徴の一つは、突然死してしまう症例が結構あるという点です。生前の検査ではわからなかったものの、死後解剖に回してようやく死因がフィラリアと特定されることもあります。
死後解剖においては大静脈や右心のほか、肺動脈およびそこから肺の中に枝分かれする末端部まで細かく検査されます。これは血流によって押し流された成虫の死骸が細い血管の中に詰まっている可能性があるためです。成虫がそのままの姿を残して死んでいる場合、血管の中から回収されたり目詰まりの元(塞栓子)の中から回収されたりします。しかし死骸が未成熟だったりばらばらになっている時は見落とされることもしばしばです。その他、迷入の可能性を考慮し、腹腔、脳、脊柱管、その他の動脈も綿密に検査されます。
死後解剖においては大静脈や右心のほか、肺動脈およびそこから肺の中に枝分かれする末端部まで細かく検査されます。これは血流によって押し流された成虫の死骸が細い血管の中に詰まっている可能性があるためです。成虫がそのままの姿を残して死んでいる場合、血管の中から回収されたり目詰まりの元(塞栓子)の中から回収されたりします。しかし死骸が未成熟だったりばらばらになっている時は見落とされることもしばしばです。その他、迷入の可能性を考慮し、腹腔、脳、脊柱管、その他の動脈も綿密に検査されます。
フィラリア症の治療
フィラリアに感染した猫は異なるステージのフィラリアを体内に保有していることが少なくありません。具体的には血液中にミクロフィラリアがいる状態、蚊からもらった幼虫が体内をウヨウヨと移動している状態、成虫がすでに肺動脈に寄生してしまっている状態、上記すべての複合などです。
成虫の自然死を待つ
猫における治療の第一選択肢は、無症状の場合「成虫の自然死を待つ」というものです。成虫が死んだ場合、4~5ヶ月で血中の抗原が消えますので、半年~1年に1回のペースで検査を行って状態をモニタリングします。
急性症例に対しては肺の炎症を抑える目的での糖質コルチコイド(プレドニゾン)漸減投与の他、輸液、気管支拡張薬、酸素吸入などが行われます。寄生虫の寿命自体が短いため多くの症例では自然治癒しますが、成虫の死滅、迷入、移動による突然死の可能性も覚悟しておかなければなりません。
イタリアで行われた調査では、フィラリア陽性の猫43頭を長期的に観察したところ、34頭(79%)が18~49ヶ月以内に自然治癒したといいます。その一方、3頭(7%)は38~40ヶ月後に突然死し、6頭(14%)は8~41ヶ月のフォロー期間中に死亡したとのこと。さらにイタリアで行われた別の調査では、フィラリア陽性で無症状だった猫77頭を追跡調査したところ、45頭(58%)で臨床症状が現れ、そのうちおよそ3分の1(15頭)がフィラリアに関連した後遺症で死亡したそうです。
フィラリアに感染した状態は、心臓の付近に爆弾を埋め込まれた状態と同じで、20~30%では最悪の結末を招いてしまうようです。成虫が猫の体にどのような悪影響を及ぼすかはほとんど運によりますので、何事もなく自然治癒するのを祈るしかありません。また成虫を放置している間に、肺の血管や心臓に永続的な病変が生じてしまう可能性も受け入れなければなりません。
急性症例に対しては肺の炎症を抑える目的での糖質コルチコイド(プレドニゾン)漸減投与の他、輸液、気管支拡張薬、酸素吸入などが行われます。寄生虫の寿命自体が短いため多くの症例では自然治癒しますが、成虫の死滅、迷入、移動による突然死の可能性も覚悟しておかなければなりません。
イタリアで行われた調査では、フィラリア陽性の猫43頭を長期的に観察したところ、34頭(79%)が18~49ヶ月以内に自然治癒したといいます。その一方、3頭(7%)は38~40ヶ月後に突然死し、6頭(14%)は8~41ヶ月のフォロー期間中に死亡したとのこと。さらにイタリアで行われた別の調査では、フィラリア陽性で無症状だった猫77頭を追跡調査したところ、45頭(58%)で臨床症状が現れ、そのうちおよそ3分の1(15頭)がフィラリアに関連した後遺症で死亡したそうです。
フィラリアに感染した状態は、心臓の付近に爆弾を埋め込まれた状態と同じで、20~30%では最悪の結末を招いてしまうようです。成虫が猫の体にどのような悪影響を及ぼすかはほとんど運によりますので、何事もなく自然治癒するのを祈るしかありません。また成虫を放置している間に、肺の血管や心臓に永続的な病変が生じてしまう可能性も受け入れなければなりません。
成虫駆除薬を投与する
成虫駆除薬であるメラルソルミンを投与し、積極的に成虫を体内から駆除しようとする治療法は最後の手段です。成虫駆除薬で生存期間が伸びたとする報告はなく、またメラルソルミンは3.5mg/kgで致死的とされています。成虫が駆除されると同時に猫まで命を落としてしまっては何の意味もないでしょう。
メラルソルミン以外では、幼虫と同時に成虫に対してもある程度の殺虫効果を持つ「イベルメクチン」(24μg/kg)を毎月のペースで2年間投与したところ、65%の症例で虫数が減ったという報告もあります。しかし虫が死んだ際の過剰なアレルギー反応であるアナフィラキシーの危険性があることや、死んだ虫体による塞栓症の危険性があることなどから、予防薬を駆除薬として代用する「スロー・キル・プロトコル」は今のところ推奨されていません。
メラルソルミン以外では、幼虫と同時に成虫に対してもある程度の殺虫効果を持つ「イベルメクチン」(24μg/kg)を毎月のペースで2年間投与したところ、65%の症例で虫数が減ったという報告もあります。しかし虫が死んだ際の過剰なアレルギー反応であるアナフィラキシーの危険性があることや、死んだ虫体による塞栓症の危険性があることなどから、予防薬を駆除薬として代用する「スロー・キル・プロトコル」は今のところ推奨されていません。
外科手術で成虫を摘出する
レントゲン検査や心エコー検査などで成虫の存在が確認され、なおかつ重篤な症状を示しているような場合は、外科手術によって成虫を摘出するという治療法がとられることがあります。
大静脈や右心房にいる場合は右の頚静脈から、心室、心房、肺動脈にいる時は心室切開術でアプローチするというのが正攻法です。成虫を摘出するときはブラッシュストリング、バスケットカテーテル、ループスネア、フレキシブルアリゲーター鉗子といった医療器具が用いられますが、どの機器を用いるにしても虫の体をちぎらないよう気を付けなければなりません。もし虫体がちぎれて細い管内に詰まってしまうと、医原性の肺塞栓症を引き起こしてしまいます。 外科手術による摘出は投薬治療に比べればいくらか望ましいとされていますが、過去のデータでは5頭中2頭が死亡するといった怖い報告もありますので、かなり危ない賭けになるでしょう。犬に比べて体が小さい猫においては、それだけ手術の難易度が高まります。また「フレキシブルアリゲーター鉗子」の入手が困難といった事情もありますので、どこの動物病院でも簡単に行える手術というわけではありません。
外科手術による摘出は投薬治療に比べればいくらか望ましいとされていますが、過去のデータでは5頭中2頭が死亡するといった怖い報告もありますので、かなり危ない賭けになるでしょう。犬に比べて体が小さい猫においては、それだけ手術の難易度が高まります。また「フレキシブルアリゲーター鉗子」の入手が困難といった事情もありますので、どこの動物病院でも簡単に行える手術というわけではありません。
大静脈や右心房にいる場合は右の頚静脈から、心室、心房、肺動脈にいる時は心室切開術でアプローチするというのが正攻法です。成虫を摘出するときはブラッシュストリング、バスケットカテーテル、ループスネア、フレキシブルアリゲーター鉗子といった医療器具が用いられますが、どの機器を用いるにしても虫の体をちぎらないよう気を付けなければなりません。もし虫体がちぎれて細い管内に詰まってしまうと、医原性の肺塞栓症を引き起こしてしまいます。
 外科手術による摘出は投薬治療に比べればいくらか望ましいとされていますが、過去のデータでは5頭中2頭が死亡するといった怖い報告もありますので、かなり危ない賭けになるでしょう。犬に比べて体が小さい猫においては、それだけ手術の難易度が高まります。また「フレキシブルアリゲーター鉗子」の入手が困難といった事情もありますので、どこの動物病院でも簡単に行える手術というわけではありません。
外科手術による摘出は投薬治療に比べればいくらか望ましいとされていますが、過去のデータでは5頭中2頭が死亡するといった怖い報告もありますので、かなり危ない賭けになるでしょう。犬に比べて体が小さい猫においては、それだけ手術の難易度が高まります。また「フレキシブルアリゲーター鉗子」の入手が困難といった事情もありますので、どこの動物病院でも簡単に行える手術というわけではありません。
ボルバキアはどうする?
1975年以降の電子顕微鏡の発達に伴い、フィラリアの体内には「ボルバキア」と呼ばれる共生細菌が生息していることが明らかになりました。メスの生殖器に生息していること、および細菌を持たないメスは生殖機能を失いやがて死んでしまうことから考え、フィラリアにとってこの細菌は生存に不可欠な存在だと考えられています。
 犬では抗生物質(ドキシサイクリン)を30日間ほど投与してボルバキアを退治してから成虫駆除に入るというのが一般的な治療法です。しかし猫においてはデータ不足のため、この細菌に対する扱い方は定まっていません。
犬では抗生物質(ドキシサイクリン)を30日間ほど投与してボルバキアを退治してから成虫駆除に入るというのが一般的な治療法です。しかし猫においてはデータ不足のため、この細菌に対する扱い方は定まっていません。
 犬では抗生物質(ドキシサイクリン)を30日間ほど投与してボルバキアを退治してから成虫駆除に入るというのが一般的な治療法です。しかし猫においてはデータ不足のため、この細菌に対する扱い方は定まっていません。
犬では抗生物質(ドキシサイクリン)を30日間ほど投与してボルバキアを退治してから成虫駆除に入るというのが一般的な治療法です。しかし猫においてはデータ不足のため、この細菌に対する扱い方は定まっていません。
フィラリア症の予防
ここまでお読みいただいた方はすでに、「フィラリアが成虫にまで成長してしまったら安全な治療法はもうない!猫を守るには予防するしかない」という事実にお気づきでしょう。フィラリアを予防する方法は「そもそも蚊に刺されないようにすること」と「蚊から幼虫を移されても成虫になる前にとっとと殺してしまうこと」です。
蚊を予防する
日本においてフィラリアを媒介するのはイエカ属、ヤブカ属、アノフェレス属の昆虫類です。具体的にはトウゴウヤブカ、コガタアカイエカ、ヒトスジシマカなどのありふれた蚊が含まれます。動物の皮膚に針を指して血を吸い取るのは産卵前のメスだけですので、必然的に犬にフィラリアを移すのは100%メスということになります。
 一般的な蚊のライフサイクルは以下です。繁殖に最適な温度域が22℃~27℃くらいで、4月下旬~11月中旬が主な活動期間です。しかし冬でも生きている種がいますので油断はできません。
一般的な蚊のライフサイクルは以下です。繁殖に最適な温度域が22℃~27℃くらいで、4月下旬~11月中旬が主な活動期間です。しかし冬でも生きている種がいますので油断はできません。


 一般的な蚊のライフサイクルは以下です。繁殖に最適な温度域が22℃~27℃くらいで、4月下旬~11月中旬が主な活動期間です。しかし冬でも生きている種がいますので油断はできません。
一般的な蚊のライフサイクルは以下です。繁殖に最適な温度域が22℃~27℃くらいで、4月下旬~11月中旬が主な活動期間です。しかし冬でも生きている種がいますので油断はできません。
蚊のライフサイクル

- 卵水分と温度で孵化する。条件がそろわない場合は、最適な季節が来るまで乾燥した環境で越冬できる。
- 幼虫ボウフラとも呼ばれる。水中で5~14日かけて脱皮を繰り返し、徐々に大きくなる。
- さなぎ水面近くに生息し、数日かけて成虫へと近づく。
- 成虫オスは植物などをエサとし、寿命は約1週間。メスは動物の血液をエサとし、寿命は約1ヶ月。フィラリアの伝播に関係しているのはメスの成虫のみ。

室内における防虫
人間と猫は1つ屋根の下に暮らしていますので、飼い主が蚊に刺されないよう気を付けていれば、猫もまた蚊に刺されにくくなります。近年は1度室内に噴射するだけで24時間防虫効果を保ってくれる便利な商品なども開発されていますので利用しましょう。こうした商品は天井や壁など、猫の口と接する可能性が少ない場所にとどまって蚊を殺してくれますので比較的安全です。
なお蚊の攻撃を避ける方法はたくさんありますが、以下の方法は推奨されません。 猫とは違い、犬は体内にミクロフィラリアを保有できる病原巣(reservoir)になりうる動物です。もし犬のフィラリア治療を行っておらず、血中にミクロフィラリアが大量に循環している状態だと、蚊が犬から血を吸い取った後に同居している猫の体に取り付き、幼虫を体内に移してしまうというシナリオが考えられます。
猫とは違い、犬は体内にミクロフィラリアを保有できる病原巣(reservoir)になりうる動物です。もし犬のフィラリア治療を行っておらず、血中にミクロフィラリアが大量に循環している状態だと、蚊が犬から血を吸い取った後に同居している猫の体に取り付き、幼虫を体内に移してしまうというシナリオが考えられます。
犬と猫が同居している家庭においては、犬に対しても猫に対してもフィラリア対策を行わなければ不十分です。
なお蚊の攻撃を避ける方法はたくさんありますが、以下の方法は推奨されません。
室内における蚊の予防法
- 蚊取り線香蚊取り線香は夏の風物詩として有名ですが、独特の匂いによって猫の具合が悪くなってしまうかもしれません。また被毛に匂いがついてしまう可能性もあります。特に猫においてはお線香や煙など、PM2.5と呼ばれる微小分子を吸い込むことによって呼吸器系の疾患を発症する危険性が懸念されていますので使用は避けたほうがよいでしょう。
- 殺虫剤の噴霧部屋の中で蚊を見つけると「喰らえ!」と叫びながら殺虫剤をかけたくなりますが、部屋の中に噴霧された殺虫成分は床や食器など、猫の口と接触する可能性がある場所に付いてしまいます。間違って舐めとると具合が悪くなるかもしれませんので避けたほうがよいでしょう。
- 虫除け剤を猫にふりかける体にふりかける形の虫除け剤(リペラント)が人間用に開発されていますが、こうした商品はペットに使用することを想定していません。猫にかけてしまうと被毛に付いた成分を舐めとってしまうかもしれませんので、人間用の製品を安易に転用するのはやめたほうがよいでしょう。
 猫とは違い、犬は体内にミクロフィラリアを保有できる病原巣(reservoir)になりうる動物です。もし犬のフィラリア治療を行っておらず、血中にミクロフィラリアが大量に循環している状態だと、蚊が犬から血を吸い取った後に同居している猫の体に取り付き、幼虫を体内に移してしまうというシナリオが考えられます。
猫とは違い、犬は体内にミクロフィラリアを保有できる病原巣(reservoir)になりうる動物です。もし犬のフィラリア治療を行っておらず、血中にミクロフィラリアが大量に循環している状態だと、蚊が犬から血を吸い取った後に同居している猫の体に取り付き、幼虫を体内に移してしまうというシナリオが考えられます。犬と猫が同居している家庭においては、犬に対しても猫に対してもフィラリア対策を行わなければ不十分です。
屋外における防虫
屋外における防虫対策の基本は、「そもそも猫を外に出さない」ということです。外には寄生虫のほか感染症、迷子、交通事故、心無い人間による虐待などたくさんの危険が待ち受けています。室内環境さえ整えればストレスを貯め込むことなく暮らしていくこともできますので、まずは「完全室内飼い」を基本スタイルにしましょう。具体的には以下のページを参考にしてレイアウトしてみてください。
地域猫など屋外にいる時間が長い猫においては、蚊の攻撃を避けるための忌避剤を用いることがディフェンスの基本方針となります。
猫用の蚊除けアイテム
- 虫除けカラー(首輪)市販されている虫除けカラー(首輪)の多くは、ノミ、ダニ、蚊を寄せ付けないという効果を謳(うた)っています。しかし首に装着するという関係上、顔や頭に対しては防虫効果があるかもしれませんが、首輪から遠くにある体幹、腰、後ろ足まではガードしてくれません。また首輪に含まれる防虫成分によって皮膚炎を起こしてしまうこともあります。
- 虫除け滴下薬蚊を寄せ付けないという名目で売られている滴下薬(スポット薬)が市販されています。月一回の投与でおよそ1ヶ月間の効果があるとされていますが本当のところは不明です。
- フィラリア予防薬フィラリア予防薬は蚊を遠ざけてくれる効果も併せ持っているかもしれません。ミクロフィラリアを体内に保有した犬が蚊に刺される割合が47%だったのに対し、予防薬を投与された犬が刺される割合は6.7~12.9%だったといいます(Cancrini, 2006)。人間においてもマラリア原虫に感染した人ほど蚊に刺されやすくなるといいますので、体内に幼虫や原虫を抱え込むことで体温、発汗、呼吸リズム、体臭などが微妙に変化し、蚊のレーダーに引っかかりやすくなるのかもしれません。もし事実なら、後述するフィラリア予防薬を投与することがそのまま蚊の予防にもなってくれるでしょう。
幼虫の発育を予防する
たとえ蚊からフィラリアの幼虫をもらったとしても、成虫になる前に退治してしまえば大事には至りません。予防薬は早ければ生後8週齢から投与が可能で、蚊が活動する時期のみならず、できれば通年で投与するのが理想です。
猫用のフィラリア予防薬
フィラリアの幼虫駆除に用いられるのはマクロライド(12員環以上の大環状ラクトン)と呼ばれる薬剤です。マクロライドはさらにアベルメクチン系(イベルメクチン・セラメクチン・エプリノメクチン)とミルベマイシン系(ミルベマイシンオキシム・モキシデクチン)に細分されます。日本国内で猫用に認可されている代表的なマクロライド系予防薬は以下です。血中にミクロフィラリアが大量に循環している場合、殺ミクロフィラリア薬によって一度に大量の死骸が発生し、猫が体調不良に陥ることがあります。初回投与から3~7時間くらいは猫の様子をよく観察しておいたほうがよいでしょう。
猫用フィラリア予防薬
- レボリューション✓主成分=セラメクチン
✓投与方法=滴下(スポット)
✓その他の効能=ノミ・ミミヒゼンダニ - アドボケート猫用✓主成分=モキシデクチン
✓投与方法=滴下(スポット)
✓その他の効能=ノミ・ミミヒゼンダニ・回虫・鉤虫 - ブロードライン✓主成分=エプリノメクチン
✓投与方法=滴下(スポット)
✓その他の効能=ノミ・マダニ・回虫・鉤虫・条虫
予防薬を投与上の注意
猫は薬を口から食べさせることが難しいため、使えるのはスポットタイプ(滴下薬)だけです。体重ごとに投与量が決まっていますので、月に1回のペースで首の後ろに垂らします。
犬用の商品にはイベルメクチンを含んだものがたくさんあります。しかしイベルメクチンはフィラリア成虫に対する駆虫効果もある程度もっているため、投与することによって成虫が死んでしまうかもしれません。体が小さな猫にとっては、たった1匹の死骸でも時として命取りになってしまいます。ですので犬用のイベルメクチン予防薬を自己判断で猫に投与するのは絶対にNGです!
また要指示薬であるフィラリア予防薬をネットで売買することは法律で禁じられています。ネット通販で購入した予防薬を、獣医師の処方箋がない状態で投与すると、上記したような理由により時として猫の命を奪ってしまいますので十分にご注意ください。
犬用の商品にはイベルメクチンを含んだものがたくさんあります。しかしイベルメクチンはフィラリア成虫に対する駆虫効果もある程度もっているため、投与することによって成虫が死んでしまうかもしれません。体が小さな猫にとっては、たった1匹の死骸でも時として命取りになってしまいます。ですので犬用のイベルメクチン予防薬を自己判断で猫に投与するのは絶対にNGです!
また要指示薬であるフィラリア予防薬をネットで売買することは法律で禁じられています。ネット通販で購入した予防薬を、獣医師の処方箋がない状態で投与すると、上記したような理由により時として猫の命を奪ってしまいますので十分にご注意ください。
薬が効かない理由と解決法
予防薬の効果は100%ではありません。さまざまな理由で「有効性の欠如」(lack of efficacy, LOE)が生じます。フィラリア予防薬におけるLOEの主な原因とそれに対応した解決法は以下です。
猫を守れるのは飼い主だけです。昨日まで元気だったペットと突然のお別れにならないよう、しっかりと予防しましょう。
LOEの原因と解決策
- 投薬忘れ 最も多いパターンが飼い主によるうっかりミスです。本来30日であるべき投薬間隔が50日になってしまうと、フィラリアの幼虫がL5にまで発育している可能性が十分ありますので、予防薬が効かずフィラリア症に発展する危険性が高まってしまいます。
【LOEの予防・解決策】
月に1回必ず行うことと予防薬の投与をリンクすることで投薬忘れを予防することができます。例えば家賃を払う、電気料金を払う、スケジュール帳の新しいページを開く、カレンダーをめくる、給料の振込みを確認するなどです。パソコンやスマホについている「リマインダー」機能を利用するのもよいでしょう。 - 容量の間違い 投与量が多過ぎるとが逆に少なすぎるといった容量の間違いもよく起こります。スポット薬を絞っている最中に猫に逃げられたとか、チューブをしっかり最後まで絞りきらなかったなどが過少投与の主な原因です。また犬用の予防薬を使った場合は逆に過剰投与の危険性が高まります。
【LOEの予防・解決策】
処方箋をよく読み、容量が正しいことを確認します。うっかり投薬を忘れたからといって薬の量を2倍にしても副作用のリスクが高まるだけですので控えましょう。特に獣医師の処方箋がないにもかかわらず、ネット通販でフィラリア予防薬を購入した時などは、投与量も投与スケジュールもいい加減になりがちですので要注意です。
最後に
猫のフィラリア症は両極端です。80%は軽症のまま自然治癒しますが、残りの20%は5年以内に突然死もしくは慢性症状によって死亡してしまいます。フィラリアがひとたび成虫にまで成長してしまうと、もはやリスクを伴わない治療法はありませんので、まずは猫を完全室内飼いにして家の中における蚊の予防に努めてください。また犬と同居している場合は家庭内感染を避けるためそちらの予防も必要です。詳しくは姉妹サイト内「犬のフィラリア症」をご参照ください。猫を守れるのは飼い主だけです。昨日まで元気だったペットと突然のお別れにならないよう、しっかりと予防しましょう。
 その他の重要所見は肺の過拡張と横隔膜の平坦化、気管支の間質性浸潤、肺浸潤、膿胸などです。一般的に慢性症状である心臓の肥大は見られません。
その他の重要所見は肺の過拡張と横隔膜の平坦化、気管支の間質性浸潤、肺浸潤、膿胸などです。一般的に慢性症状である心臓の肥大は見られません。