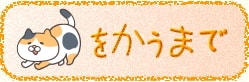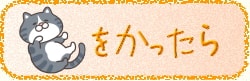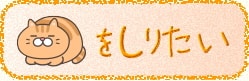詳細
調査を行ったのはイギリスとオーストリアの大学から成る共同チーム。2016年4月から6月の期間、ブラジル(31.8%)、イギリス(19.2%)、ポルトガル(9.0%)、アメリカ(7.8%)、オーストラリア(4.5%)など複数の国に暮らす猫の飼い主を対象としたオンライン・アンケートを行い、猫の問題行動の代表格である「おしっこの失敗」(トイレの外の床やカーペットで放尿してしまう粗相+壁などに少量のおしっこをスプレーするマーキング)に関する統計調査を行いました。猫たちの基本属性は以下です。
Ana Maria Barcelos, Kevin McPeake et al., Front. Vet. Sci., 28 May 2018 | https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00108
調査対象猫の基本属性
- 性別オス125頭(51.1%) | メス114頭(46.5%) | 不明6頭(2.5%)
- 品種ミックス208頭 | シャム12頭 | ペルシャ9頭 | ベンガル3頭 | バーミーズ3頭 | メインクーン2頭 | ノルウェジャンフォレストキャット2頭 | ラグドール2頭 | サイベリアン1頭
- 去勢・避妊手術手術済み229頭(93.5%) | 未手術16頭(6.5%)
粗相
- 多頭飼い↑問題なし42.5% | マーキング82.5% | 粗相63.0%(OR2.3)
- うんちの失敗↑問題なし14.2% | マーキング27.5% | 粗相44.6%(OR5)
- 制限付きで外に出られる↓問題なし33.6% | マーキング27.5% | 粗相19.6%
- 飼い主への強度依存↓問題なし25.6% | マーキング20.0% | 粗相4.3%
マーキング
- 高齢↑問題なし6.26歳 | マーキング8.78歳 | 粗相5.19歳
- 多頭飼い↑問題なし42.5% | マーキング82.5%(OR6.4) | 粗相63.0%
- キャットフラップ(猫用扉)↑問題なし17.7% | マーキング37.5%(OR2.7) | 粗相13.0%
- 制限なしの放し飼い↑問題なし14.2% | マーキング32.5%(OR2.9) | 粗相12.0%
- 性格がのんびり屋↓問題なし71.7% | マーキング52.5% | 粗相60.9%
Ana Maria Barcelos, Kevin McPeake et al., Front. Vet. Sci., 28 May 2018 | https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00108

解説
家の中に1頭以上他の猫が同居しているという「多頭飼育」により、粗相とマーキング両方のリスクが高まりました。先住猫と新入り猫の顔を合わせをした後、どちらかの猫もしくは両方の猫がおしっこの失敗をしてしまうという状況はある程度覚悟しておいたほうがよいでしょう。特に粗相のリスクが2倍に対しマーキングのリスクが6倍と推計されていますので、床よりも壁が汚れてしまう状況が考えられます。
 OlmとHouptの調査(1988・アメリカ)ではマーキング猫の84.0%、粗相猫の74.0%が多頭飼育環境だったと言います。またPryorらの調査(2001・アメリカ)ではマーキング猫の89%が多頭飼育環境だったと言います。時間を超えて似たような数値に着地したことから、多頭飼育と粗相やマーキングの関係性はかなり普遍(不変)的なものであると推測されます。
外に出られる猫(制限付きor 無制限)においては粗相のリスクが完全室内飼い猫のおよそ半分になると推計されました(OR0.49)。一方、制限なしの放し飼い状態の猫においてはマーキングのリスクが3倍に高まると推定されました(OR2.9)。外に出ることができる猫において粗相のリスクが減った理由は、単純に外でおしっこしてくる機会が増えるからだと推測されます。「粗相を家の中ではなく外でした」と言い換えることもできるでしょう。
OlmとHouptの調査(1988・アメリカ)ではマーキング猫の84.0%、粗相猫の74.0%が多頭飼育環境だったと言います。またPryorらの調査(2001・アメリカ)ではマーキング猫の89%が多頭飼育環境だったと言います。時間を超えて似たような数値に着地したことから、多頭飼育と粗相やマーキングの関係性はかなり普遍(不変)的なものであると推測されます。
外に出られる猫(制限付きor 無制限)においては粗相のリスクが完全室内飼い猫のおよそ半分になると推計されました(OR0.49)。一方、制限なしの放し飼い状態の猫においてはマーキングのリスクが3倍に高まると推定されました(OR2.9)。外に出ることができる猫において粗相のリスクが減った理由は、単純に外でおしっこしてくる機会が増えるからだと推測されます。「粗相を家の中ではなく外でした」と言い換えることもできるでしょう。
一方、逆にマーキングのリスクが高まる理由は、屋外で他の猫と接することにより縄張り意識にスイッチが入り、帰宅した時に「ここは自分のテリトリーだから入ってくるなよ!」という牽制行動につながった結果かもしれません。今回の調査では93.5%の猫が不妊手術済みでしたが、屋外で異性の猫と出会うことにより忘れかけた色気が芽生え、異性に対するセックスアピールとして家の中におしっこをまき散らしたというパターンも考えられます。 今回の調査では、過去にリスクファクターとして挙げられている様々な項目が統計的に有意とは判断されませんでした。例えばトイレのタイプ(数・置き場所・大きさ etc)、猫砂のタイプ(大きさや香り)、犬との同居、近隣猫の存在などです。こうした項目が必ずしも否定されたわけではありませんが、猫のおしっこの失敗に悩んでいる時は「多頭飼育環境の見直し」と「屋外へのアクセス調整」を優先的に行うと、早期解決につながる可能性があります。具体的には「トイレの数を増やす」「隠れ場所を増やして仲が悪い猫同士が遭遇しにくくする」「完全室内飼いに切り替える」などです。猫の年齢や性格を変える事はできませんが、上記したような住環境のアレンジならすぐにでもできるでしょう。
今回の調査では、過去にリスクファクターとして挙げられている様々な項目が統計的に有意とは判断されませんでした。例えばトイレのタイプ(数・置き場所・大きさ etc)、猫砂のタイプ(大きさや香り)、犬との同居、近隣猫の存在などです。こうした項目が必ずしも否定されたわけではありませんが、猫のおしっこの失敗に悩んでいる時は「多頭飼育環境の見直し」と「屋外へのアクセス調整」を優先的に行うと、早期解決につながる可能性があります。具体的には「トイレの数を増やす」「隠れ場所を増やして仲が悪い猫同士が遭遇しにくくする」「完全室内飼いに切り替える」などです。猫の年齢や性格を変える事はできませんが、上記したような住環境のアレンジならすぐにでもできるでしょう。
 OlmとHouptの調査(1988・アメリカ)ではマーキング猫の84.0%、粗相猫の74.0%が多頭飼育環境だったと言います。またPryorらの調査(2001・アメリカ)ではマーキング猫の89%が多頭飼育環境だったと言います。時間を超えて似たような数値に着地したことから、多頭飼育と粗相やマーキングの関係性はかなり普遍(不変)的なものであると推測されます。
外に出られる猫(制限付きor 無制限)においては粗相のリスクが完全室内飼い猫のおよそ半分になると推計されました(OR0.49)。一方、制限なしの放し飼い状態の猫においてはマーキングのリスクが3倍に高まると推定されました(OR2.9)。外に出ることができる猫において粗相のリスクが減った理由は、単純に外でおしっこしてくる機会が増えるからだと推測されます。「粗相を家の中ではなく外でした」と言い換えることもできるでしょう。
OlmとHouptの調査(1988・アメリカ)ではマーキング猫の84.0%、粗相猫の74.0%が多頭飼育環境だったと言います。またPryorらの調査(2001・アメリカ)ではマーキング猫の89%が多頭飼育環境だったと言います。時間を超えて似たような数値に着地したことから、多頭飼育と粗相やマーキングの関係性はかなり普遍(不変)的なものであると推測されます。
外に出られる猫(制限付きor 無制限)においては粗相のリスクが完全室内飼い猫のおよそ半分になると推計されました(OR0.49)。一方、制限なしの放し飼い状態の猫においてはマーキングのリスクが3倍に高まると推定されました(OR2.9)。外に出ることができる猫において粗相のリスクが減った理由は、単純に外でおしっこしてくる機会が増えるからだと推測されます。「粗相を家の中ではなく外でした」と言い換えることもできるでしょう。一方、逆にマーキングのリスクが高まる理由は、屋外で他の猫と接することにより縄張り意識にスイッチが入り、帰宅した時に「ここは自分のテリトリーだから入ってくるなよ!」という牽制行動につながった結果かもしれません。今回の調査では93.5%の猫が不妊手術済みでしたが、屋外で異性の猫と出会うことにより忘れかけた色気が芽生え、異性に対するセックスアピールとして家の中におしっこをまき散らしたというパターンも考えられます。
 今回の調査では、過去にリスクファクターとして挙げられている様々な項目が統計的に有意とは判断されませんでした。例えばトイレのタイプ(数・置き場所・大きさ etc)、猫砂のタイプ(大きさや香り)、犬との同居、近隣猫の存在などです。こうした項目が必ずしも否定されたわけではありませんが、猫のおしっこの失敗に悩んでいる時は「多頭飼育環境の見直し」と「屋外へのアクセス調整」を優先的に行うと、早期解決につながる可能性があります。具体的には「トイレの数を増やす」「隠れ場所を増やして仲が悪い猫同士が遭遇しにくくする」「完全室内飼いに切り替える」などです。猫の年齢や性格を変える事はできませんが、上記したような住環境のアレンジならすぐにでもできるでしょう。
今回の調査では、過去にリスクファクターとして挙げられている様々な項目が統計的に有意とは判断されませんでした。例えばトイレのタイプ(数・置き場所・大きさ etc)、猫砂のタイプ(大きさや香り)、犬との同居、近隣猫の存在などです。こうした項目が必ずしも否定されたわけではありませんが、猫のおしっこの失敗に悩んでいる時は「多頭飼育環境の見直し」と「屋外へのアクセス調整」を優先的に行うと、早期解決につながる可能性があります。具体的には「トイレの数を増やす」「隠れ場所を増やして仲が悪い猫同士が遭遇しにくくする」「完全室内飼いに切り替える」などです。猫の年齢や性格を変える事はできませんが、上記したような住環境のアレンジならすぐにでもできるでしょう。