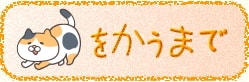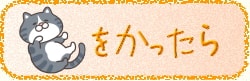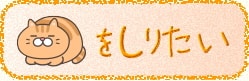S. felisの薬剤耐性
Staphylococcus felisは1989年、ブドウ球菌の新種として同定されたコアグラーゼ陰性菌。猫(felis catus)の尿路、皮膚、呼吸器、鼻腔、耳、眼球などに生息しているものの病原性は低く、免疫力が低下した個体において日和見感染する程度です。感染症の実例としては外耳炎、皮膚感染症、尿路感染症などが報告されています。
今回の報告を行ったのはサンリツセルコバ検査センターを中心とした調査チーム。日本国内における疫学データがほとんどない同菌に着目し、抗菌薬適正使用支援の観点から薬剤耐性の現況を調査しました。
今回の報告を行ったのはサンリツセルコバ検査センターを中心とした調査チーム。日本国内における疫学データがほとんどない同菌に着目し、抗菌薬適正使用支援の観点から薬剤耐性の現況を調査しました。
調査対象
調査対象となったのは2023年11月から2024年5月までの期間、日本全国に点在する動物病院から検査センターに送られてきた120の検査サンプル。患猫たちは全て何らかの細菌感染症と診断された83頭です。ブドウ球菌の検出に優れた検査機器にかけてS. felisと同定した上で以下抗生剤に対する感受性を調べていきました。
代表的な抗菌薬
- ペニシリン
- オキサシリン
- ゲンタマイシン・ミノサイクリン・クリンダマイシン
- エリスロマイシン
- クロラムフェニコール
- スルファメトキサゾール -トリメトプリム
- レボフロキサシン
- リファンピシン
- バンコマイシン
- テイコプラニン
- リネゾリド
調査結果
薬剤耐性調査の結果、「耐性あり」と判断された割合は以下のようになりました。判断基準はCLSI(臨床・検査標準協会)のカットラインに準拠しています。
Kakeru IZUMI, Yuzo TSUYUKI, Kazuki HARADA, Journal of Veterinary Medical Science(2025), DOI:10.1292/jvms.24-0452
薬剤抵抗性
- ペニシリン=33.3%
- エリスロマイシン=15.8%
- クリンダマイシン=13.3%
- レボフロキサシン=5.0%
- ゲンタマイシン=2.5%
- クロラムフェニコール=2.5%
- リファンピシン=0.8%
Kakeru IZUMI, Yuzo TSUYUKI, Kazuki HARADA, Journal of Veterinary Medical Science(2025), DOI:10.1292/jvms.24-0452

投薬治療する際の注意
当調査では51.7%(62/120)ものサンプルが他の菌とともに検出されました。このデータは患猫たちの感染症の原因がS. felisであると断定できないことを意味しています。
菌の変遷
30年以上前に日本国内で行われた調査では膿瘍からの検出率が少なかったと報告されています。一方、今回の調査では膿瘍由来の菌が23.3%と2番目に多い割合になっています。またポーランドで行われた調査では鼻腔と眼球からの検出が多かったと報告されています。一方、今回の調査では尿路と膿瘍からの検出が多かったようです。
こうした事実から場所や時間が変わることで菌の分布が容易に変化する可能性が見て取れます。
こうした事実から場所や時間が変わることで菌の分布が容易に変化する可能性が見て取れます。
第一選択薬にペニシリンはNG
薬剤抵抗性に関してはペニシリンが33.3%とかなり高い割合を占めていました。これはオーストラリアで行われた先行調査と比較しても高い数値です。国内の臨床におけるペニシリンの使用頻度を反映していると考えられますが、調査チームは感染部位にかかわらずペニシリンを第一選択薬とすることは推奨されないと警告しています。
多剤耐性菌(3種以上薬剤に耐性を持つ)は9.2%(11/120)という割合でした。高いのか低いのか判断が難しいですが、少なくともオーストラリアやサウジアラビアでは見られなかった傾向です。特筆すべきは11サンプルすべてがペニシリン耐性をもち、11サンプル中10サンプルまでもがエリスロマイシンとクリンダマイシン耐性を持っていた点で、これらは菌のリボソーム結合部位における構成上の変異を示唆していると考えられます。
多剤耐性菌(3種以上薬剤に耐性を持つ)は9.2%(11/120)という割合でした。高いのか低いのか判断が難しいですが、少なくともオーストラリアやサウジアラビアでは見られなかった傾向です。特筆すべきは11サンプルすべてがペニシリン耐性をもち、11サンプル中10サンプルまでもがエリスロマイシンとクリンダマイシン耐性を持っていた点で、これらは菌のリボソーム結合部位における構成上の変異を示唆していると考えられます。
免疫力低下者は注意を
調査チームが指摘している通り、猫から人に感染する確率は極めて低いと推定されます。しかし2023年、オランダにおいて猫から人へ感染したと思われるケース報告があったことから、まるきり無視するわけにもいきません( :G.J.Sips, 2023)。
:G.J.Sips, 2023)。
報告にあったのは58歳の女性。術部(椎弓切除術)における感染症の原因菌を調べた結果、女性が飼育している猫3頭のうち1頭から単離した菌と合致したといいます。またゲノム解析の結果、推定上の病原性因子(病原性を発揮するために最低限必要となる微生物産生性の化学物質)も検出されたとも。こうした事実から家庭内で人獣感染した可能性が高く警戒が必要であると指摘されています。
臨床上健康な人は頭の片隅に置く程度でよいですが、免疫力が低下した人においては当菌に用心するに越したことはありません。具体的には高齢者、免疫抑制剤服用者、免疫不全疾患患者などです。当調査における採取部位は以下ですので、接触する機会があった場合は手指をきれいにするよう心がけましょう。
 :G.J.Sips, 2023)。
:G.J.Sips, 2023)。報告にあったのは58歳の女性。術部(椎弓切除術)における感染症の原因菌を調べた結果、女性が飼育している猫3頭のうち1頭から単離した菌と合致したといいます。またゲノム解析の結果、推定上の病原性因子(病原性を発揮するために最低限必要となる微生物産生性の化学物質)も検出されたとも。こうした事実から家庭内で人獣感染した可能性が高く警戒が必要であると指摘されています。
臨床上健康な人は頭の片隅に置く程度でよいですが、免疫力が低下した人においては当菌に用心するに越したことはありません。具体的には高齢者、免疫抑制剤服用者、免疫不全疾患患者などです。当調査における採取部位は以下ですので、接触する機会があった場合は手指をきれいにするよう心がけましょう。
S. felisの検出場所
- 尿路=28.3%(34)
- 膿瘍=23.3%(28)
- 耳=22.5%(27)
- 鼻腔=10.8%(13)
- 眼球=5.8%(7)
- 皮膚=5.0%(6)
- その他=4.2%(5)