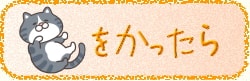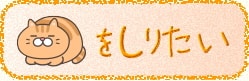詳細
症例報告を行ったのは、アメリカ・タフツ大学の医療チーム。10歳になるオス猫が8ヶ月間継続する喘鳴(呼吸する時のゼーゼー)と逆くしゃみを主症状としてタフツ大学カミングス獣医学校を受診しました。口腔内の検査やCTスキャンをした結果、下された診断名は空気の通り道がいちじるしく狭くなる「鼻咽頭虚脱」。
早速全身麻酔(40分)が施され、口を開いた状態で内視鏡検査を行うとともに、バルーンによる虚脱部の復元が行われました。しかし治療成果がいまいちで、なおかつ鼻咽頭部を肥大化した組織が占有している疑いがあったため、翌日改めて麻酔(25分間)を実行。術野を確保するため10cmの開口器(マウスギャグ)を用い、鼻切開が行われました。 手術自体は滞りなく進みましたが、麻酔から覚めたタイミングで猫が「足をバタバタ動かす」、「伸筋が硬直する」といった神経症状を呈し始めたといいます。さらに驚愕反応(目の前に急に物を差し出してまばたきするかどうかを確認するテスト)が見られないことから、目が見えなくなっていることも確認されました。この神経症状は回復する気配を見せず、術後32時間には突如として呼吸が停止。蘇生には成功したものの再び呼吸停止に陥り、福祉上の観点から最終的には飼い主が安楽死を決断しました。
手術自体は滞りなく進みましたが、麻酔から覚めたタイミングで猫が「足をバタバタ動かす」、「伸筋が硬直する」といった神経症状を呈し始めたといいます。さらに驚愕反応(目の前に急に物を差し出してまばたきするかどうかを確認するテスト)が見られないことから、目が見えなくなっていることも確認されました。この神経症状は回復する気配を見せず、術後32時間には突如として呼吸が停止。蘇生には成功したものの再び呼吸停止に陥り、福祉上の観点から最終的には飼い主が安楽死を決断しました。
死後の検証の結果、猫の呼吸器症状を引き起こしたのは麻酔そのものではなく、猫の口を開いた状態で固定するために用いていた「スプリング式開口器」である可能性が浮上。最終的には開口による脳への血流障害が原因であると判断されました。 Global cerebral ischemia with subsequent respiratory arrest in a cat after repeated use of a spring-loaded mouth gag
Emily A Hartman, Robert J McCarthy and Mary A Labato, Journal of Feline Medicine and Surgery, DOI: 10.1177/2055116917739126
早速全身麻酔(40分)が施され、口を開いた状態で内視鏡検査を行うとともに、バルーンによる虚脱部の復元が行われました。しかし治療成果がいまいちで、なおかつ鼻咽頭部を肥大化した組織が占有している疑いがあったため、翌日改めて麻酔(25分間)を実行。術野を確保するため10cmの開口器(マウスギャグ)を用い、鼻切開が行われました。
 手術自体は滞りなく進みましたが、麻酔から覚めたタイミングで猫が「足をバタバタ動かす」、「伸筋が硬直する」といった神経症状を呈し始めたといいます。さらに驚愕反応(目の前に急に物を差し出してまばたきするかどうかを確認するテスト)が見られないことから、目が見えなくなっていることも確認されました。この神経症状は回復する気配を見せず、術後32時間には突如として呼吸が停止。蘇生には成功したものの再び呼吸停止に陥り、福祉上の観点から最終的には飼い主が安楽死を決断しました。
手術自体は滞りなく進みましたが、麻酔から覚めたタイミングで猫が「足をバタバタ動かす」、「伸筋が硬直する」といった神経症状を呈し始めたといいます。さらに驚愕反応(目の前に急に物を差し出してまばたきするかどうかを確認するテスト)が見られないことから、目が見えなくなっていることも確認されました。この神経症状は回復する気配を見せず、術後32時間には突如として呼吸が停止。蘇生には成功したものの再び呼吸停止に陥り、福祉上の観点から最終的には飼い主が安楽死を決断しました。死後の検証の結果、猫の呼吸器症状を引き起こしたのは麻酔そのものではなく、猫の口を開いた状態で固定するために用いていた「スプリング式開口器」である可能性が浮上。最終的には開口による脳への血流障害が原因であると判断されました。 Global cerebral ischemia with subsequent respiratory arrest in a cat after repeated use of a spring-loaded mouth gag
Emily A Hartman, Robert J McCarthy and Mary A Labato, Journal of Feline Medicine and Surgery, DOI: 10.1177/2055116917739126

解説
口を大きく開くことで脳への血流がせき止められ、低酸素から神経症状を示すという症例は、2000年に入ってからちらほらと報告されていました。長らく発症メカニズムは不明でしたが、近年行われた調査により、猫に特有の解剖学的な構造が原因であることが判明しています。
人間の場合、脳に血液を送る血管には「外頚動脈」と「内頚動脈」があり、一方が何らかの理由でダメになっても他方が血流を補うようにできています。しかし猫の場合、なぜか「内頚動脈」が機能しておらず、実質的に「外頚動脈」が脳への栄養補給を担っています。
この「外頚動脈」は分岐した後「顎動脈」となり、名前が示すとおり顎の近くを通過しますが、あまりにも口を大きく開けてしまうと、下顎骨の一部が顎動脈を圧迫し、血流障害を招いてしまうのです。 顎動脈は目の網膜や耳(内耳)に血液を送って栄養補給していますので、この動脈がせき止められると両器官に障害が生じ、目の場合は「視力の喪失」、耳の場合は「聴力やバランス感覚の喪失」という形で発現します。さらに症例は少ないものの、今回の調査報告のように大脳が低酸素状態に陥り、呼吸器症状につながってしまうものもあります。
顎動脈は目の網膜や耳(内耳)に血液を送って栄養補給していますので、この動脈がせき止められると両器官に障害が生じ、目の場合は「視力の喪失」、耳の場合は「聴力やバランス感覚の喪失」という形で発現します。さらに症例は少ないものの、今回の調査報告のように大脳が低酸素状態に陥り、呼吸器症状につながってしまうものもあります。
発症頻度は少ないとされていますが、2012年に行われた調査では、6頭中3頭で大なり小なり血流障害が起こったとされていますので、症状として発現するかどうかは別として、動脈への圧迫と一時的な血流障害自体は頻繁に起こっているものと推測されます(→出典)。 臨床の現場で開口器を用いる場面は、内視鏡検査、鼻咽頭部の異物除去、鼻咽頭部の手術などです。こうした治療を受ける猫にとっては、麻酔以外にも開口性の脳血流障害というリスクを負わなければなりません。血流障害には左右どちらか一方だけに発生するパターンもあり、その場合視力障害や聴力障害がどちらか一方にしか出ません。その結果、目や耳が片方障害を受けているにも関わらず、獣医師も飼い主もそのことに気づかないという状況も起こりえます。
臨床の現場で開口器を用いる場面は、内視鏡検査、鼻咽頭部の異物除去、鼻咽頭部の手術などです。こうした治療を受ける猫にとっては、麻酔以外にも開口性の脳血流障害というリスクを負わなければなりません。血流障害には左右どちらか一方だけに発生するパターンもあり、その場合視力障害や聴力障害がどちらか一方にしか出ません。その結果、目や耳が片方障害を受けているにも関わらず、獣医師も飼い主もそのことに気づかないという状況も起こりえます。
開口器にはスプリング式で持続的に圧をかけ続けるもののほか、開口角度を自由に設定できる調節式のものもあります。治療を受ける前に医療機関に確認したほうがよいでしょう。
この「外頚動脈」は分岐した後「顎動脈」となり、名前が示すとおり顎の近くを通過しますが、あまりにも口を大きく開けてしまうと、下顎骨の一部が顎動脈を圧迫し、血流障害を招いてしまうのです。
 顎動脈は目の網膜や耳(内耳)に血液を送って栄養補給していますので、この動脈がせき止められると両器官に障害が生じ、目の場合は「視力の喪失」、耳の場合は「聴力やバランス感覚の喪失」という形で発現します。さらに症例は少ないものの、今回の調査報告のように大脳が低酸素状態に陥り、呼吸器症状につながってしまうものもあります。
顎動脈は目の網膜や耳(内耳)に血液を送って栄養補給していますので、この動脈がせき止められると両器官に障害が生じ、目の場合は「視力の喪失」、耳の場合は「聴力やバランス感覚の喪失」という形で発現します。さらに症例は少ないものの、今回の調査報告のように大脳が低酸素状態に陥り、呼吸器症状につながってしまうものもあります。発症頻度は少ないとされていますが、2012年に行われた調査では、6頭中3頭で大なり小なり血流障害が起こったとされていますので、症状として発現するかどうかは別として、動脈への圧迫と一時的な血流障害自体は頻繁に起こっているものと推測されます(→出典)。
 臨床の現場で開口器を用いる場面は、内視鏡検査、鼻咽頭部の異物除去、鼻咽頭部の手術などです。こうした治療を受ける猫にとっては、麻酔以外にも開口性の脳血流障害というリスクを負わなければなりません。血流障害には左右どちらか一方だけに発生するパターンもあり、その場合視力障害や聴力障害がどちらか一方にしか出ません。その結果、目や耳が片方障害を受けているにも関わらず、獣医師も飼い主もそのことに気づかないという状況も起こりえます。
臨床の現場で開口器を用いる場面は、内視鏡検査、鼻咽頭部の異物除去、鼻咽頭部の手術などです。こうした治療を受ける猫にとっては、麻酔以外にも開口性の脳血流障害というリスクを負わなければなりません。血流障害には左右どちらか一方だけに発生するパターンもあり、その場合視力障害や聴力障害がどちらか一方にしか出ません。その結果、目や耳が片方障害を受けているにも関わらず、獣医師も飼い主もそのことに気づかないという状況も起こりえます。開口器にはスプリング式で持続的に圧をかけ続けるもののほか、開口角度を自由に設定できる調節式のものもあります。治療を受ける前に医療機関に確認したほうがよいでしょう。