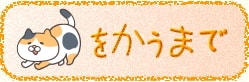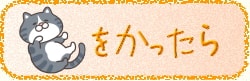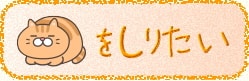詳細
調査を行ったのはオレゴン州立大学のボーラー・エリーさん。屋外をうろついている飼い主のいない猫に不妊手術を施し、元の場所に戻してあげる「TNR」に関しては、非常にうまくいったとする報告がある一方、あまりうまくいかなかったという報告もちらほらと散見されます。そこでエリーさんは、TNRの成否を決定づける要素が何なのかを明らかにするため、人間に養われている飼い猫と、「非飼育自由行動猫」(FRU)を対象とし、生殖能力に関する比較調査を行いました。なお、ここで言う猫たちの定義は以下です。
 次に、2015年の8月~9月の期間、地元の動物愛護協会に避妊手術のために訪れた「メスの飼い猫」(4ヶ月齢未満5頭+4~6ヶ月齢2頭)と「メスの非飼育自由行動猫」(4ヶ月齢未満10頭+4~6ヶ月齢7頭)を比較したところ、以下のような事実が明らかになったといいます(※未熟な=4ヶ月齢未満/成熟した=4~6ヶ月齢)。
次に、2015年の8月~9月の期間、地元の動物愛護協会に避妊手術のために訪れた「メスの飼い猫」(4ヶ月齢未満5頭+4~6ヶ月齢2頭)と「メスの非飼育自由行動猫」(4ヶ月齢未満10頭+4~6ヶ月齢7頭)を比較したところ、以下のような事実が明らかになったといいます(※未熟な=4ヶ月齢未満/成熟した=4~6ヶ月齢)。
 野生環境で暮らしているオスの非飼育自由行動猫とメスの非飼育自由行動猫、および人間に養われている飼い猫を比較した結果、非飼育自由行動猫はオスにしてもメスにしても、一般的に考えられている「生後8ヶ月齢」という性成熟時期よりもかなり早い段階で生殖能力を獲得しているという可能性が浮き彫りとなりました。TNRの失敗例は、上記「生後8ヶ月齢」を目安に不妊手術を行っていたため、その前の段階で産み落とされた子猫たちの数までは減らせなかったからだと推測されています。今後TNRを成功させるためには、性別にかかわらず生後4ヶ月を目安に不妊手術を行っていく必要があるだろうとしています。また生殖能力を一時的に失わせるワクチンなど、手術以外による不妊法と合わせて行えば、より効果的であるとも。
Determining the Onset of Reproductive Capacity in Free-Roaming, Unowned Cats
野生環境で暮らしているオスの非飼育自由行動猫とメスの非飼育自由行動猫、および人間に養われている飼い猫を比較した結果、非飼育自由行動猫はオスにしてもメスにしても、一般的に考えられている「生後8ヶ月齢」という性成熟時期よりもかなり早い段階で生殖能力を獲得しているという可能性が浮き彫りとなりました。TNRの失敗例は、上記「生後8ヶ月齢」を目安に不妊手術を行っていたため、その前の段階で産み落とされた子猫たちの数までは減らせなかったからだと推測されています。今後TNRを成功させるためには、性別にかかわらず生後4ヶ月を目安に不妊手術を行っていく必要があるだろうとしています。また生殖能力を一時的に失わせるワクチンなど、手術以外による不妊法と合わせて行えば、より効果的であるとも。
Determining the Onset of Reproductive Capacity in Free-Roaming, Unowned Cats
- 野猫側に近づくことも手懐けることもできず、人間の世話にならなくても生きていける猫
- 地域猫側に近づくことも手懐けることもできないが、人間の世話にならないと生きていけない猫
- 非飼育自由行動猫野猫と地域猫を合わせた概念
- 飼い猫食糧や寝床を完全に人間に頼りながら生きている猫
オス猫に関する調査
- 性器棘の保有率●2~6ヶ月齢→30.7%(4/13)
●6ヶ月齢以上→100%(16/16) - 正常な精子●2~6ヶ月齢→77±11%
●6ヶ月齢以上→81±13% - 精子形成能力●2~2.5ヶ月齢→0%
●3~4ヶ月齢→17%
●5~6ヶ月齢→67%
●12~24ヶ月齢→100% - 精細管の直径●2~2.5ヶ月齢→88.10±10.88μm
●3~4ヶ月齢→109.8±8.89μm
●5~6ヶ月齢→142.2±16.89μm
●12~24ヶ月齢→237.90±52.45μm
 次に、2015年の8月~9月の期間、地元の動物愛護協会に避妊手術のために訪れた「メスの飼い猫」(4ヶ月齢未満5頭+4~6ヶ月齢2頭)と「メスの非飼育自由行動猫」(4ヶ月齢未満10頭+4~6ヶ月齢7頭)を比較したところ、以下のような事実が明らかになったといいます(※未熟な=4ヶ月齢未満/成熟した=4~6ヶ月齢)。
次に、2015年の8月~9月の期間、地元の動物愛護協会に避妊手術のために訪れた「メスの飼い猫」(4ヶ月齢未満5頭+4~6ヶ月齢2頭)と「メスの非飼育自由行動猫」(4ヶ月齢未満10頭+4~6ヶ月齢7頭)を比較したところ、以下のような事実が明らかになったといいます(※未熟な=4ヶ月齢未満/成熟した=4~6ヶ月齢)。
メス猫に関する調査
- 胞状卵胞●未熟な非飼育自由行動猫→33%
●未熟な飼い猫→17% - 卵胞のサイズ●未熟な非飼育自由行動猫→581.6±53.65μm
●未熟な飼い猫→502.0±74.51μm
●成熟した飼い猫→469.4±121.48μm - 子宮と卵巣の総重量●未熟な非飼育自由行動猫→0.93±0.28g
●成熟した非飼育自由行動猫→1.18±0.31g
 野生環境で暮らしているオスの非飼育自由行動猫とメスの非飼育自由行動猫、および人間に養われている飼い猫を比較した結果、非飼育自由行動猫はオスにしてもメスにしても、一般的に考えられている「生後8ヶ月齢」という性成熟時期よりもかなり早い段階で生殖能力を獲得しているという可能性が浮き彫りとなりました。TNRの失敗例は、上記「生後8ヶ月齢」を目安に不妊手術を行っていたため、その前の段階で産み落とされた子猫たちの数までは減らせなかったからだと推測されています。今後TNRを成功させるためには、性別にかかわらず生後4ヶ月を目安に不妊手術を行っていく必要があるだろうとしています。また生殖能力を一時的に失わせるワクチンなど、手術以外による不妊法と合わせて行えば、より効果的であるとも。
Determining the Onset of Reproductive Capacity in Free-Roaming, Unowned Cats
野生環境で暮らしているオスの非飼育自由行動猫とメスの非飼育自由行動猫、および人間に養われている飼い猫を比較した結果、非飼育自由行動猫はオスにしてもメスにしても、一般的に考えられている「生後8ヶ月齢」という性成熟時期よりもかなり早い段階で生殖能力を獲得しているという可能性が浮き彫りとなりました。TNRの失敗例は、上記「生後8ヶ月齢」を目安に不妊手術を行っていたため、その前の段階で産み落とされた子猫たちの数までは減らせなかったからだと推測されています。今後TNRを成功させるためには、性別にかかわらず生後4ヶ月を目安に不妊手術を行っていく必要があるだろうとしています。また生殖能力を一時的に失わせるワクチンなど、手術以外による不妊法と合わせて行えば、より効果的であるとも。
Determining the Onset of Reproductive Capacity in Free-Roaming, Unowned Cats
解説
2016年に行われた調査では、正中線ではなく脇腹からアプローチする卵巣除去術を用いれば、たとえ子猫が生後12週齢(3ヶ月齢)未満という若齢でも、安全に避妊手術を施すことができるとの結果が出ています(→出典)。野生環境で暮らしている野良猫の繁殖と、その結果としての子猫の殺処分数を減らすためには、「生後8ヶ月齢」というこれまでの不妊手術の目安を「生後4~6ヶ月齢」に置き換える必要があるようです。